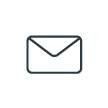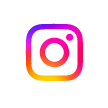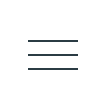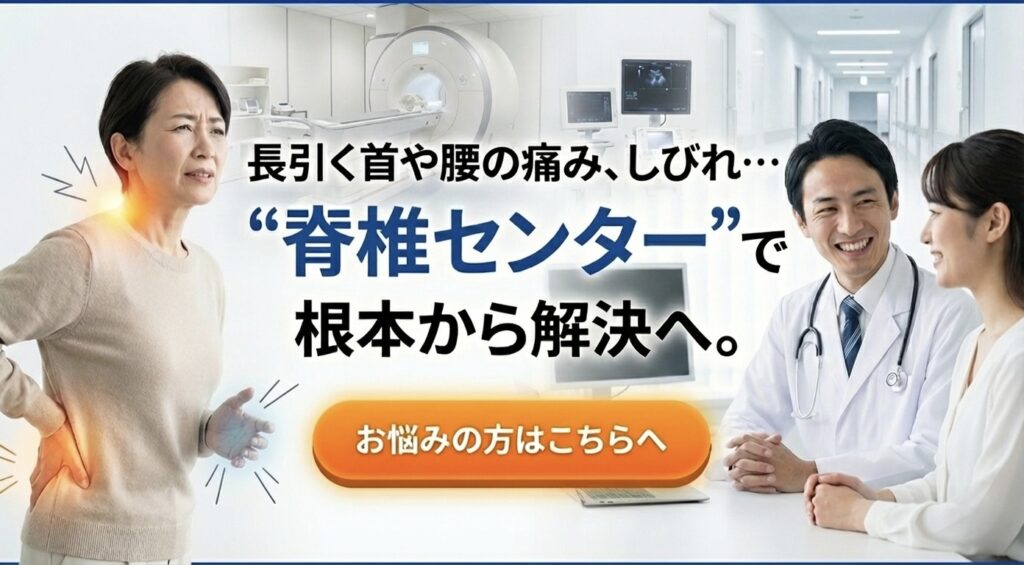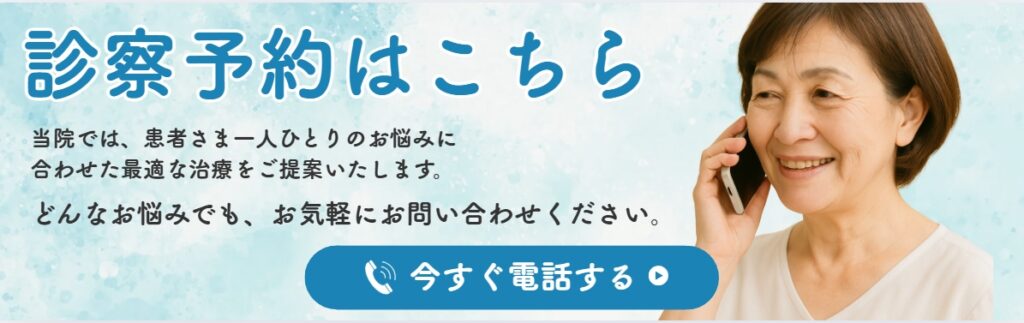椎間板ヘルニアは何科を受診すべき?症状別の診療科選びと治療法
急に襲ってくる腰の激痛や、足がじんじんとしびれる不快感。
「椎間板ヘルニアかもしれない」と、不安に思ったとき「何科を受診すればいいの?」と、疑問に感じていませんか。
椎間板ヘルニアの治療は、最初の診療科選びが重要です。この記事では、症状に合わせた最適な診療科の選び方から、代表的な治療法、再発を防ぐための日常生活の工夫まで詳しく解説します。自分に合った治療への第一歩を踏み出し、つらい痛みやしびれの適切な対処法を学びましょう。
当院では、椎間板ヘルニアをはじめとした整形外科疾患に対し、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。不安な症状がある方も安心してご相談いただけるよう、以下の記事で診察の流れや受付方法を詳しくまとめています。
>>診察のご案内について

記事監修:川口 慎治
大室整形外科 脊椎・関節クリニック 医師
経歴:
徳島大学医学部卒業後、洛和会音羽病院に勤務
京都大学医学部整形外科学教室入局
学研都市病院脊椎脊髄センター勤務
2023年より 大室整形外科 脊椎・関節クリニック勤務
専門分野:脊椎・脊髄外科
資格:
日本専門医機構認定 整形外科専門医
日本整形外科学会認定 脊椎脊髄病医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科指導医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科専門医
椎間板ヘルニアで受診すべき診療科
腰痛の原因はヘルニアだけとは限りません。似た症状でも、まったく違う病気が隠れていることもあります。基本となる診療科を知り、ご自身の症状に合った専門医に相談することから始めましょう。椎間板ヘルニアの際に受診すべき診療科は、以下の3つです。
- 整形外科
- 脳神経外科(手足の麻痺や強い痛みがある場合)
- ペインクリニック(痛みの緩和に特化)
整形外科
腰痛や足のしびれなど、椎間板ヘルニアを疑う症状が出た場合、最初に相談すべき診療科は「整形外科」です。
整形外科は、骨や関節、筋肉、そして神経といった、体を動かすための器官(運動器)の専門家です。椎間板ヘルニアは、背骨のクッション(椎間板)が飛び出して神経を圧迫する病気なので、整形外科の専門分野です。整形外科では、次の流れで診察を進めます。
- 問診:いつから、体のどこが、どのように痛むのかを詳しく聞く
- 身体診察:医師が直接、体の動きや感覚、足の力の入り具合を確認する
- 画像検査:「レントゲン」や「MRI」を使用し、椎間板ヘルニアの状態を正確に把握する
治療は、痛み止めの薬やリハビリテーションなどの、体に負担の少ない「保存療法」から始めるのが基本です。多くの場合、保存療法で症状は少しずつ和らいでいきます。
以下の記事では、椎間板ヘルニアの基本的な原因や症状、整形外科で行われる治療法の流れについて、ポイントをわかりやすく解説しています。
>>椎間板ヘルニアとは?原因・症状・治療法を解説
脳神経外科(手足の麻痺や強い痛みがある場合)
症状によっては「脳神経外科」が適していることもあります。脳神経外科は、脳や脊髄、末梢神経といった「神経そのもの」を専門とする診療科です。次のような強い神経症状がある場合は、脳神経外科の受診を検討するか、かかりつけの整形外科医と相談しましょう。
| 症状 | 具体例 |
| 強い麻痺や筋力低下 | ・足に力が入らず、スリッパが意図せず脱げてしまう ・つま先立ちができない、足首を動かしにくい ・片足だけ、触られた感覚が鈍い感じがする |
| 排尿や排便の異常(膀胱直腸障害) | ・おしっこが出にくい、または自分の意思と関係なく漏れてしまう ・便意を感じにくくなった、急にひどい便秘になった |
| 我慢できないほどの激しい痛み | ・痛みで夜も眠れず、じっとしていられない ・どんな姿勢をとっても痛みが少しも和らがない |
上記の症状は、神経が強く圧迫されている危険なサインの可能性があります。放置すると後遺症が残ることもあるため、早急な対応が必要です。
脳神経外科では、神経の圧迫を取り除くための、より精密な手術を得意としています。病院によっては、整形外科と脳神経外科が協力して治療にあたる「脊椎外科」や「脊椎センター」を設けていることもあります。
ペインクリニック(痛みの緩和に特化)
つらい痛みをすぐにでも和らげたい方は、ペインクリニックをおすすめします。ペイン(Pain)とは「痛み」のことで、さまざまな病気による「痛みの治療」を専門に行う診療科です。以下のような方におすすめです
- 痛み止めの飲み薬を続けているが、あまり効果を感じられない方
- 痛みが長期間続いて、仕事や日常生活に大きな支障が出ている方
- 手術はできるだけ避けたいが、痛みはしっかり抑えたい方
ペインクリニックの代表的な治療法に「神経ブロック注射」があります。痛みの原因となっている神経の近くに、麻酔薬などを直接注射する治療法です。痛みの信号が脳に伝わるのを一時的に遮断(ブロック)することで、つらい症状を素早く和らげる効果が期待できます。
ペインクリニックは痛みの緩和が主な目的です。ヘルニアそのものを治すためには、整形外科などと連携しながら、根本的な治療を進めていくことが大切です。
医療機関を探す際のポイント
自分に合った医療機関を見つけるために、次の3つのポイントを参考にしてみてください。
- 地域
- 実績・専門性
- 治療方針(医師との相性)
地域
通いやすさは治療を継続するための重要ポイントです。椎間板ヘルニアの治療は、リハビリテーションや定期的な通院が必要なことが多く、痛みが強い状態での移動は、心身ともに大きな負担です。無理なく通える距離にある医療機関を選ぶことで、身体的・精神的な負担を減らし、治療の継続と回復につなげやすくなります。
自宅や職場からアクセスしやすい場所の優先が、結果的に治療効果を高めるポイントです。
実績・専門性
安心して治療を受けるために、医療機関の専門性を確認することも重要です。以下のような情報を調べましょう。
- 脊椎(せきつい)を専門とする医師の在籍
- MRIなど精密検査の設備の有無
- 具体的な治療実績の公開
整形外科の中でも、特に脊椎疾患の経験が豊富な医師を選ぶことで、より精度の高い診断や治療が期待できます。神経の圧迫具合を正確に把握するには、MRI検査が欠かせません。正しい診断を得るために、設備の整った医療機関の受診がおすすめです。
年間の手術件数を公表している施設もあります。例えば「脊椎手術年間500件以上」などの実績は、経験の豊富さを判断する目安になります。
治療方針(医師との相性)
医師がどのような考えで治療を進めるのか、ご自身の希望と合っているかを確認することが大切です。治療方針のチェック項目として以下が挙げられます。
- すぐに手術を勧めず、保存療法の選択肢も丁寧に説明してくれるか
- 体への負担が少ない内視鏡手術など、幅広い治療法に対応しているか
- 治療のメリットだけでなく、考えられるリスクやデメリットも話してくれるか
- 患者さんの不安な気持ちや、生活での困りごとをしっかり聞いてくれるか
ご自身が納得できる医療機関を選び、信頼できる医師と一緒に治療に取り組んでいきましょう。
椎間板ヘルニアの代表的な治療法3つ
椎間板ヘルニアの代表的な3つの治療法を、以下の項目に沿って解説します。
- 保存療法(薬物療法・コルセット・リハビリテーション)
- 神経ブロック注射
- 手術療法(内視鏡手術など)
保存療法(薬物療法・コルセット・リハビリテーション)
椎間板ヘルニアと診断された場合の約8割は、手術以外の方法で症状の改善が期待できます。治療の第一歩は、体に負担の少ない「保存療法」から始めるのが基本です。保存療法は、主に「薬物療法」「コルセット」「リハビリテーション」の3つを組み合わせて行います。
薬物療法は、痛みやしびれの原因である、神経の炎症を抑えることが目的です。症状に応じて以下の薬が使われます。
| 薬の種類 | 目的・効果 |
| 消炎鎮痛薬 | 飲み薬や貼り薬で神経の炎症を抑え、痛みを直接的に軽くする |
| 筋弛緩薬 | 緊張した腰回りの筋肉をほぐし、血行を改善する |
| 神経障害性疼痛治療薬 | しびれ・ピリピリとした神経由来の痛みに効果がある |
痛みが特に強い急性期には、コルセットで腰を固定します。腰の動きを一時的に制限することで、椎間板への負担を減らし、症状の悪化を防ぎます。ただし、長期間の使用は腰回りの筋力低下につながるため、医師の指示に従って適切に使いましょう。
リハビリテーションでは、理学療法士などの専門家が、一人ひとりの状態に合わせて運動プログラムを立てます。温めたり電気を流したりして血行を良くし、痛みを和らげる「物理療法」や、体幹の筋肉を鍛える「運動療法」などを行います。
保存療法は症状を和らげることを目的とした方法です。飛び出してしまった椎間板そのものを、元に戻すわけではないことを理解しておく必要があります。
神経ブロック注射
神経ブロック注射は、痛みの原因となっている神経のすぐ近くに、局所麻酔薬などを直接注射する治療法です。神経ブロック注射には、主に以下の目的があります。
- 痛みを直接取り除く
- 痛みの悪循環を断ち切る
- リハビリテーションをスムーズに進める
痛みの信号を伝えている神経の働きを一時的に遮断(ブロック)し、痛みを抑えることで、筋肉のこわばりや血行不良などの悪循環を断ち切ることが期待できます。痛みが軽くなることで、運動療法などに取り組めるようになり、根本的な改善へとつながる可能性があります。
注射は、専門医が透視装置やエコー(超音波)などで神経の場所を確認しながら、安全に配慮して行うこともあります。痛みをコントロールするための選択肢の一つとなる場合があります。
手術療法(内視鏡手術など)
保存療法やブロック注射を数か月続けても症状が改善しないときや、以下のサインが現れた場合には「手術療法」を検討します。
- 足の麻痺が進行し、歩くのが難しい
- 尿や便が出にくくなる(膀胱直腸障害)
手術の目的は、神経を圧迫している椎間板ヘルニアを物理的に取り除き、症状の根本原因を解消することです。近年では、患者さんの体への負担を最小限に抑える「低侵襲手術」が主流となっており「内視鏡手術」が代表的です。内視鏡手術と従来の手術の違いは以下のとおりです。
| 手術方法 | 傷の大きさ | 筋肉への影響 | 入院期間 | 社会復帰 |
| 内視鏡手術(MED法など) | 小さい(約1〜2cm) | 筋肉を温存しやすい | 短い傾向 | 早い傾向 |
| 従来の手術(一例) | 比較的大きい | 筋肉を切開する必要がある | 長い傾向 | 時間がかかる傾向 |
ただし、現在の医療では、手術でヘルニアを取り除いても、一度傷んだ椎間板の構造を完全に元通りに修復することは難しいのが現状です。椎間板の機能低下は、患者さんの生活の質を著しく下げ、公衆衛生上の大きな課題となっています。
現在、再生医療技術は研究段階にあり、実用化には時間を要します。医師は、最新の研究動向に注目しながら、現在利用可能な治療法の中から患者さん一人ひとりにとって適切な選択肢を提供できるよう努めています。
以下の記事では、椎間板ヘルニアの具体的な治療法や、回復を助ける日常生活の工夫について詳しく解説しています。
>>椎間板ヘルニアの治療法!回復に役立つ生活習慣も紹介
日常生活での工夫
椎間板ヘルニアの治療の効果を最大限に引き出し、つらい症状の再発を防ぐためには、毎日の生活習慣を見直すことが、何より大切です。今日からできる生活の工夫を以下の項目に沿って解説します。
- 正しい姿勢(座り方・立ち方)
- 物の持ち方・動作
- ストレッチ・筋力トレーニング
- 職業別の対策(デスクワーク・立ち仕事・力仕事)
正しい姿勢(座り方・立ち方)
椎間板への圧力を軽減するには、正しい姿勢の習慣が不可欠です。長時間同じ姿勢を続ける方は、日常動作を意識的に見直しましょう。座る際に意識したいポイントは以下のとおりです。
- お尻を背もたれにつけて深く腰掛ける
- 骨盤を立ててS字カーブを保つ
- 腰を反らせすぎず、背筋は自然に伸ばす
- 膝は90度、足裏は床にしっかりつける
- 足を組まない
- 背もたれとの隙間にクッションやタオルを活用する
立ち方のポイントは以下の4つです。
- 両足に均等に体重をかける
- お腹に軽く力を入れて体幹を安定させる
- あごを軽く引いて、頭が前に出ないようにする
- 長時間立つ場合は足台を使い、片足ずつ交互に乗せる
正しい姿勢を維持することは、椎間板にかかる圧力を軽減し、腰痛や神経症状の予防・改善につながります。特に座位は、見た目以上に腰への負担が大きいため、日常的にデスクワークや車の運転が多い人は注意が必要です。
姿勢の崩れは習慣によって無意識に起こるため「意識して直す」ことが重要です。正しい姿勢を意識しやすくするために、椅子や作業環境を調整するのも効果が期待できます。
特に長時間立ちっぱなし・座りっぱなしになる場面では、姿勢を変える工夫や休憩を取り入れることが、腰の負担軽減に役立ちます。
物の持ち方・動作
椎間板ヘルニアの悪化や再発は日常のふとした瞬間に起こることがあります。特に危険なのが、膝を伸ばしたまま腰を曲げる「中腰」の姿勢です。重い物はもちろん、床に落ちたペンを拾うような軽い動作でも、守ってほしい基本の動きは以下のとおりです。
- 物にしっかり近づく:体から物が離れているほど、てこの原理で腰にかかる負担は何倍にも増える
- 膝を曲げて腰を落とす:腰から曲げずに、背筋は伸ばしたまま、股関節と膝をしっかり曲げて、スクワットのように腰を落とす
- 体に引き寄せて持つ:物をお腹に引き寄せるように、体の中心でしっかりと抱える
- 足の力で立ち上がる:太ももの大きな筋肉を使って、地面を押すようにゆっくり立ち上がる
他にも、日常の何気ない動作の中にも腰に負担をかけやすいものがあります。以下のような工夫をすると負担の軽減が期待できます。
- 顔を洗うときは膝を軽く曲げ、片手を洗面台につく
- くしゃみや咳は壁や机に手をついて衝撃を和らげる
- ベッドから起きるときは横向きになり、手で支えてゆっくり起きる
ストレッチ・筋力トレーニング
症状が落ち着いてきたら、積極的な再発予防に取り組みましょう。背骨を支えるお腹周りの筋肉(体幹筋)は「天然のコルセット」とも呼ばれます。体幹を鍛え、筋肉の柔軟性を高めることが、椎間板への負担を減らすことにつながります。
ただし、痛みやしびれがあるときは運動を避けてください。神経に炎症がある状態で無理に動かすと、症状が悪化する可能性があります。自己流でのトレーニングは腰に負担をかける危険があるため、必ず医師や理学療法士に相談し、自分の状態に合った指導を受けましょう。
自宅でできるケアの一例を以下に紹介します。
| トレーニング名 | 方法 |
| 体幹トレーニング(ドローイン) | 1.仰向けに寝て、膝を軽く立てる 2.息をゆっくりと「ふーっ」と吐きながら、おへそを背骨に近づけるイメージでお腹をへこませる 3.へこませた状態を呼吸を止めずに10〜30秒キープする |
| お尻のストレッチ(大殿筋) | 1.椅子に座り、片方の足首を反対側の膝の上に乗せる 2.背筋を伸ばしたまま、ゆっくりと体を前に倒していく |
上記のケアを行う際は、専門家の許可を得てから実施しましょう。
以下の記事では、椎間板ヘルニアの方におすすめのストレッチ方法や、実践時の注意点について詳しく解説しています。
>>椎間板ヘルニアのストレッチ方法|症状を和らげるポイントも解説
職業別の対策(デスクワーク・立ち仕事・力仕事)
仕事の内容によって、腰への負担のかかり方は大きく異なります。ご自身の職業に合わせた対策を取り入れ、大切な腰を守りましょう。職業タイプ別の対策を以下にまとめます。
| 職業タイプ | 主な対策のポイント |
| デスクワーク | ・椅子や机の高さを調整し、正しい座り方を保つ ・少なくとも1時間に1回は立ち上がり、軽く歩いたり伸びをしたりする |
| 立ち仕事 | ・クッション性の高い、ご自身の足に合った靴を選ぶ ・可能であれば、足元に疲労軽減マットを敷く ・足台を利用して時々片足を休ませ、こまめに姿勢を変える |
| 力仕事 | ・「物の持ち方」の基本動作を、徹底する ・台車やリフターといった補助具を積極的に活用する ・一人で無理をせず、複数人で協力して作業を行う |
仕事に集中していると、つい無理な姿勢をしがちです。意識的に体をいたわる習慣をつけることが、長く健康に働き続けるための重要な投資となります。
以下の記事では、椎間板ヘルニアになりやすい人の特徴をわかりやすく解説しています。再発や悪化を防ぎたい方はぜひご覧ください。
>>椎間板ヘルニアになりやすい人の特徴とは?リスクを高める要因と予防法を解説
まとめ
急な腰の痛みや足のしびれに襲われたとき、最初に相談すべきは「整形外科」です。強い麻痺や排尿の異常などがあれば「脳神経外科」、とにかく痛みを和らげたい場合は「ペインクリニック」も選択肢になります。
大切なのは、自己判断で痛みを我慢したり、間違ったケアをしたりしないことです。ご自身の症状に合った適切な治療を受け、腰をいたわる生活習慣を心がけることが、つらい毎日から抜け出すための確実な一歩になります。一人で抱え込まず、専門医の力を借りて、安心できる日々を取り戻しましょう。
当院の受診をご希望の方は、まずはお電話にてご予約ください。詳しいアクセス方法は、以下のページをご覧ください。
>>大室整形外科へのアクセスはこちら
参考文献
Liu Z, Zhang Q, Li Y, Wang G, Fu C, Sun Y, Ding J. Biomaterial-based treatments for structural reconstruction in intervertebral disc degeneration. Biomaterials, 2026, 324, p.123426.