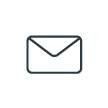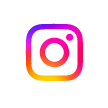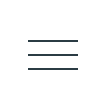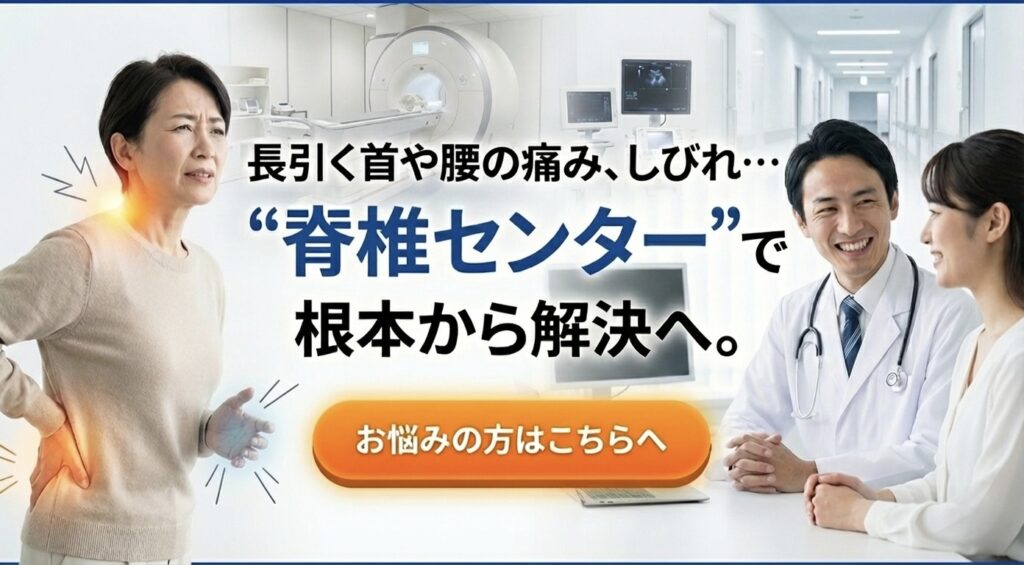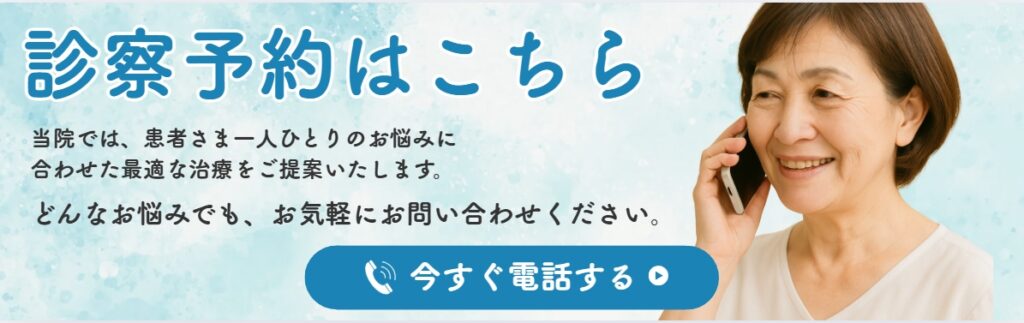椎間板ヘルニアは一生治らない?完治までの道のりと症状改善の可能性を解説
椎間板ヘルニアは、一生治らないと不安を抱えている方は少なくありません。腰や足の痛みやしびれは、日常生活に影響を及ぼします。研究では、椎間板ヘルニアは適切な治療を行うことで、約1年で症状が軽快する場合があると報告されています。体の免疫反応により、飛び出した椎間板が吸収される「自然退縮」のためです。
個人差はありますが、保存療法で7割程度の患者さんの症状が改善するという報告もあります。本記事では、椎間板ヘルニアの完治までの道のりや症状改善の可能性、具体的な治療法、再発を防ぐための5つの方法を解説します。
当院では、椎間板ヘルニアをはじめとした整形外科疾患に対し、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。不安な症状がある方も安心してご相談いただけるよう、以下の記事で診察の流れや受付方法を詳しくまとめています。
>>診察のご案内について

記事監修:川口 慎治
大室整形外科 脊椎・関節クリニック 医師
経歴:
徳島大学医学部卒業後、洛和会音羽病院に勤務
京都大学医学部整形外科学教室入局
学研都市病院脊椎脊髄センター勤務
2023年より 大室整形外科 脊椎・関節クリニック勤務
専門分野:脊椎・脊髄外科
資格:
日本専門医機構認定 整形外科専門医
日本整形外科学会認定 脊椎脊髄病医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科指導医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科専門医
椎間板ヘルニアは約1年で治る場合が多い
多くの椎間板ヘルニアは、約1年で症状が軽快する場合があります。「自然退縮」という現象が起こるためです。自然退縮は、体にとって異物である椎間板の一部を、白血球などが攻撃し分解・吸収していく体の防御システムによるものです。
保存療法を続けると、7割程度の患者さんの症状が軽快するという報告もあります。保存療法は、薬物療法や理学療法、装具療法などがあり、患者さんの状態に合わせ、適切な治療法を選択します。
椎間板ヘルニアは、多くの場合、完治または寛解(かんかい:日常生活に支障がない状態)を目指せる病気と言えます。痛みやしびれなどの症状が気になる場合は、医師に相談しましょう。
以下の記事では、椎間板ヘルニアの方におすすめのストレッチ方法や、実践時の注意点について詳しく解説しています。
>>椎間板ヘルニアのストレッチ方法|症状を和らげるポイントも解説
椎間板ヘルニアが治るまでの経過
多くの場合、適切な治療とセルフケアによって、日常生活は支障なく過ごせるようになります。椎間板ヘルニアが治るまでの経過は、以下の流れです。
- 急性期
- 亜急性期
- 慢性期
- 長期経過
急性期
急性期は、発症〜約2週間までの期間を指します。急性期は、飛び出した椎間板の一部である髄核によって神経が強く圧迫され、炎症反応が活発に起こります。激しい腰痛や坐骨神経痛(お尻から太ももの裏、ふくらはぎにかけての痛みやしびれ)に悩まされます。くしゃみや咳といった動作で腹圧がかかり、痛みが増すこともあります。
電気が走るような、鋭い痛みやしびれを訴える患者さんもいます。急性期では、安静が大切です。炎症を抑えるために、消炎鎮痛剤などの薬物療法や患部を冷やすなどの処置が行われることもあります。痛みが強い場合は、安静度を高めるためにコルセットを装着することもあります。
急性期は、痛みが強く、体を動かすことが困難なため、日常生活にも大きな支障が出ます。焦らず、痛みと炎症を抑えることに専念しましょう。
亜急性期
亜急性期は、発症から2週間~3か月までの期間を指します。急性期に比べると痛みは徐々に軽減しますが、強弱を繰り返すこともあります。炎症は落ち着き始め、少しずつ体を動かすリハビリテーションが開始されます。理学療法士の指導のもと、ストレッチや軽い筋力トレーニングなどを行います。
筋肉の柔軟性、筋力の向上が期待されます。痛みが強い場合は、神経根ブロック注射などの治療を行うこともあります。日常生活では、無理のない範囲で活動量を増やすことが大切です。再発予防のため、医師や理学療法士の指示に従い、徐々に体を動かすようにしましょう。
慢性期
慢性期は、発症から3か月~1年までの期間を指します。慢性期は、日常生活に支障のない程度まで痛みが軽減することが多いです。一方で、しびれなどの症状が残っている方もいます。慢性期のリハビリテーションでは、体幹の筋力トレーニングを中心に行い、再発しにくい体づくりを目指します。
日常生活動作の指導なども行い、正しい姿勢や体の使い方を身につけることで、椎間板への負担を軽減します。重いものを持ち上げない、長時間の同じ姿勢を避けるなど、椎間板への負担を減らす工夫をしましょう。
長期経過
1年以上経過すると、多くの場合、症状が軽快し、日常生活が支障なく過ごせるようになります。再発予防には、体幹の筋力トレーニングやストレッチ、正しい姿勢を心がけるなど、日常生活における注意点を守ることが大切です。禁煙や適正体重の維持などは、再発リスクを低減する効果が期待できます。
ヘルニアの突出方向や大きさ、喫煙や肥満、重労働といった生活習慣、早期のリハビリも改善を左右する要因です。椎間板ヘルニアの治療は、保存療法以外に注射療法や手術療法などがあります。
麻痺や排尿障害などが出現した場合は、緊急手術が必要なこともあります。症状が改善しない場合、新たな症状が出現した場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。
椎間板ヘルニアの治療法
椎間板ヘルニアの治療法は、患者さんの症状や経過、状態に合わせて組み合わせることもあります。治療法について、以下の3つを解説します。
- 保存療法:薬物療法、理学療法、装具療法など
- 注射療法:神経根ブロック、硬膜外ブロックなど
- 手術療法:内視鏡手術、顕微鏡手術など
保存療法:薬物療法、理学療法、装具療法など
保存療法は、手術をせず、痛みやしびれなどの症状を和らげ、日常生活を楽にするための治療法です。治療法は、患者さんの状態に合わせ、組み合わせて行われます。
薬物療法は、医師の指示のもと、痛みや炎症を抑える薬を内服します。代表的な薬剤には、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)やアセトアミノフェンなどがあります。神経の興奮を抑える薬や筋肉の緊張を和らげる薬が併用されることもあります。
理学療法は、理学療法士の指導のもと、ストレッチや筋力トレーニングなどを行います。腰や背骨周りの筋肉を鍛え、柔軟性を高めることで、椎間板への負担を軽減し、姿勢を改善します。日常生活動作の指導や、物理療法(温熱療法、電気刺激療法など)を組み合わせることもあります。
装具療法は、コルセットなどの装具を着用することで、腰を安定させ、痛みを軽減させます。コルセットは、腰への負担を軽くし、正しい姿勢の維持を助ける一方、長期間の使用は筋力低下につながる可能性もあります。医師の指示に従い、使用しましょう。
注射療法:神経根ブロック、硬膜外ブロックなど
注射療法は、炎症や痛みを起こしている神経に直接薬を注射することで、症状を和らげる治療法です。保存療法で十分な効果が得られない場合、注射療法を検討します。
神経根ブロックは、痛みの原因である神経の根元に直接薬を注射します。局所麻酔薬やステロイド薬を注射することで、神経の炎症を抑え、痛みをブロックします。
硬膜外ブロックは、脊髄を覆っている硬膜の外側の硬膜外腔に薬を注入します。神経根ブロックと同様に、局所麻酔薬やステロイド薬を注射することで、広範囲の神経の炎症を抑え、痛みを和らげます。
効果や持続時間は個人差がありますが、注射により症状の軽減が期待されます。効果は一時的なため、痛みが軽減した頃に筋力強化などを併せて取り組むことが大切です。
手術療法:内視鏡手術、顕微鏡手術など
手術が必要になるのは、以下の3つの場合です。
- 保存療法や注射療法で効果がない場合
- 足のしびれや筋力低下が進行する場合
- 排尿・排便障害がある場合
手術療法は、飛び出した椎間板の一部を取り除き、神経の圧迫を解消する治療法です。近年では、内視鏡手術や顕微鏡手術なども選択肢の一つとなっています。
内視鏡手術は、傷口が小さく、体への負担が少ない手術法です。入院期間も短く、早期の社会復帰が期待できます。局所麻酔で行う場合もあり、患者さんの負担軽減につながります。
顕微鏡手術は、顕微鏡を使って手術を行うため、より精密な操作が可能です。神経を傷つけるリスクを最小限に抑えながら、ヘルニアを取り除くことができます。
手術には感染や神経損傷、再発などのリスクが伴います。医師とよく相談し、メリットとデメリットを理解したうえで判断することが大切です。麻痺や排尿障害が出ている場合は、緊急手術の検討が必要です。
手術を受ける際には治療効果だけでなく、費用面の確認も欠かせません。術式による費用の違いや、保険適用の条件、自己負担額の目安を事前に把握しておくことにより、安心して治療に臨むことができます。以下の記事では、椎間板ヘルニア手術の費用相場や保険適用の条件、自己負担額について解説しています。
>>椎間板ヘルニア手術の費用相場は?保険適用の条件や自己負担額を解説
椎間板ヘルニアの再発を防ぐ5つの方法
椎間板ヘルニアの再発の主な要因は、過度な運動や労働、長時間のデスクワーク、不適切な姿勢、肥満、喫煙などです。正しい知識と適切なケアにより、再発のリスクを減らすことができます。椎間板ヘルニアの再発を防ぐ方法について、以下の5つを解説します。
- 適度に運動する
- 食生活に気を配る
- 十分な睡眠を確保する
- ストレスを管理する
- 定期的に受診する
適度に運動する
適度な運動は、椎間板ヘルニアの再発予防の効果が期待できます。有酸素運動は、腰への負担が比較的少ないと言われています。運動の種類や効果などは、表のとおりです。
| 運動の種類 | 効果 | 頻度 | 注意点 |
| ウォーキング | 血液循環改善、筋力強化、腰痛軽減 | 週3回以上 | ・適切な靴を履くこと ・無理のないペースで行うこと |
| 水泳 | 腰への負担軽減、全身運動 | 週2回以上 | ・水温に注意すること ・疲れない程度に行うこと |
| ストレッチ | 柔軟性向上、筋肉の緊張緩和、腰痛軽減 | 毎日 | 痛みを感じない範囲で行うこと |
運動不足は、腰椎を支える筋肉を衰えさせ、椎間板への負担を増大させます。適度な運動は、筋肉を強化し、腰椎の安定性を高める効果があります。腹筋や背筋、大殿筋などの筋肉を鍛えることは、腰椎を支え、椎間板への負担を軽減する役割が期待されます。
間違った方法で行うと、腰を痛めてしまう可能性があるため、医師や理学療法士の指導のもと、適切な方法と強度で行いましょう。
食生活に気を配る
バランスの良い食生活は、椎間板ヘルニアの再発予防にも大切です。骨や筋肉の健康に重要な栄養素として、以下の食品の摂取を推奨しています。
- カルシウム:牛乳、ヨーグルト、チーズなどの乳製品、小魚、緑黄色野菜
- ビタミンD:鮭、マグロ、卵黄
- タンパク質:肉、魚、卵、大豆製品
適度な日光浴は、ビタミンDの生成を促進することが期待されます。バランスの良い食事とともに、日常生活の中で心がけましょう。肥満は、腰椎への負担を増大させ、椎間板ヘルニアの再発リスクを高める要因です。食生活に気を配り、適正体重を維持しましょう。暴飲暴食を避け、腹八分目を心がけることが大切です。
十分な睡眠を確保する
睡眠不足は、免疫機能を低下させ、痛みを増幅させる可能性があります。十分な睡眠によって、体の修復機能を高め、椎間板ヘルニアの再発予防につなげることができます。睡眠不足は、自律神経のバランスを崩し、筋肉の緊張を高める要因にもなります。
筋肉が緊張すると血行が悪くなり、椎間板への栄養供給が滞り、椎間板の変性を促進する可能性もあります。毎日同じ時間に寝起きし、睡眠時間を一定に保つことで、質の高い睡眠を得ることができます。寝る前のカフェイン摂取や、長時間スマートフォンを見ることは避け、リラックスして眠りにつけるよう工夫しましょう。
ストレスを管理する
ストレスは、自律神経のバランスを崩し、筋肉の緊張を高め、椎間板ヘルニアの再発リスクを高める可能性があります。ストレスを発散し、心身のリラックスを図ることは、再発予防に大切です。ストレスを軽減するために、適度な運動や趣味、リラックスタイムなどを設けましょう。
ウォーキングなどの軽い運動は、ストレス発散の一つの方法です。好きな音楽を聴いたり、読書をしたり、趣味に没頭する時間もストレス解消の方法になります。
定期的に受診する
椎間板ヘルニアの症状が落ち着いたら、定期的に整形外科を受診し、経過観察の機会を設けましょう。定期的な診察によって、再発の兆候を早期に発見し、適切な治療を受けることができます。医師から日常生活での注意点や運動療法の指導を受けることは、再発予防にもつながります。
受診頻度は症状や経過によって異なるため、医師と相談のうえ、適切な間隔で受診しましょう。
椎間板ヘルニアにおいて、避けるべき動作や習慣を正しく知っておくことも予防・再発防止に役立ちます。以下の記事では、椎間板ヘルニアの方が「やってはいけないこと」について、具体例を挙げながら詳しく解説しています。
>>椎間板ヘルニアでやってはいけないこと7つ|悪化させない方法
まとめ
椎間板ヘルニアは、適切な治療と日頃のケアにより、多くは1年程度で症状が軽快し、日常生活も支障なく過ごせるようになります。痛みやしびれのピークは、急性期、亜急性期、慢性期と徐々に回復に向かいます。経過に合わせた治療法と、日常生活での注意点を守ることが大切です。
保存療法で効果がない場合や症状が重い場合は、注射療法や手術療法などの選択肢もあります。医師とよく相談しましょう。再発を防ぐためには、適度な運動やバランスの良い食事、十分な睡眠、ストレス管理、定期的な受診が大切です。
ポイントを意識することで、椎間板ヘルニアの再発リスクを減らし、快適な毎日を送れるようにしましょう。
当院の受診をご希望の方は、まずはお電話にてご予約ください。詳しいアクセス方法は、以下のページをご覧ください。
>>大室整形外科へのアクセスはこちら
参考文献
- Peng-fei Yu, Fang-Da Jiang, Jin-Tao Liu, Hong Jiang.Outcomes of conservative treatment for ruptured lumbar disc herniation.Acta Orthop. Belg.,2013,79,,p.726-730
- Lin Xie, Chenpeng Dong, Hanmo Fang, Min Cui, Kangcheng Zhao, Cao Yang, Xinghuo Wu.Prevalence, clinical predictors, and mechanisms of resorption in lumbar disc herniation: a systematic review.Orthopedic Reviews,2024