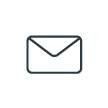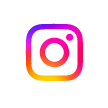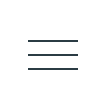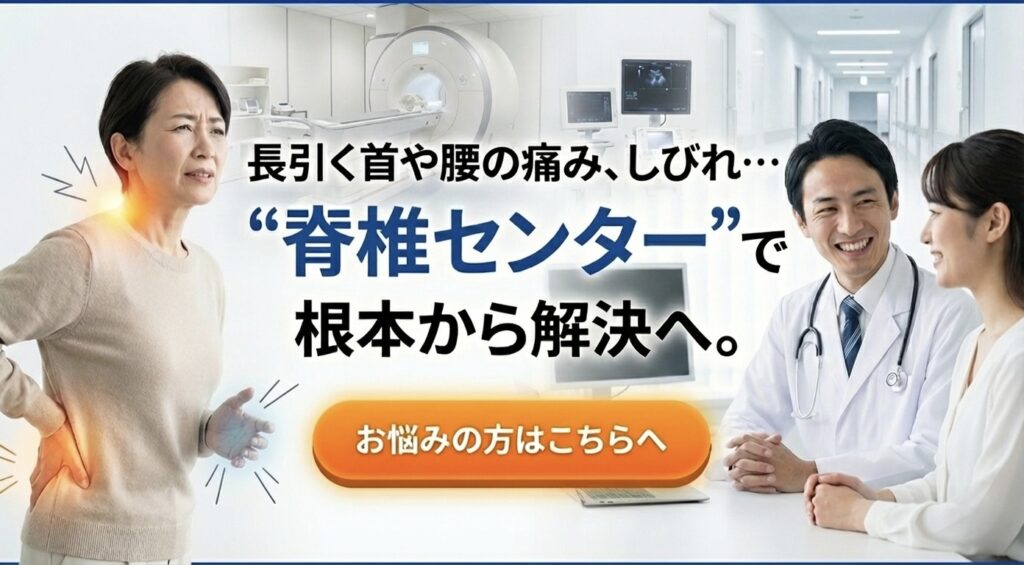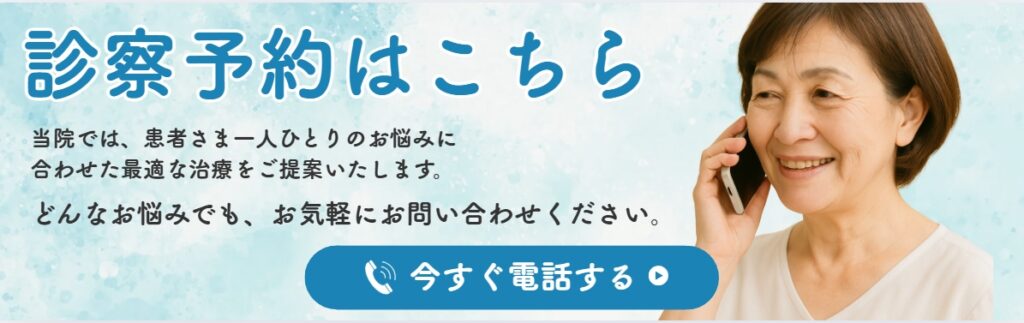坐骨神経痛とはどんな症状?原因や治療法、ストレッチ法も解説
お尻から足にかけて走る鋭い痛みや、しびれる不快な感覚などの症状の原因がわからず、不安に感じていませんか?「坐骨神経痛」とは病名ではなく、さまざまな原因によって引き起こされる症状の総称です。一般的に20〜40代に多い「腰椎椎間板ヘルニア」や、50代以降に増える「腰部脊柱管狭窄症」など人によって原因が異なります。
原因を正しく知ることが、改善への第一歩と考えられています。この記事では、坐骨神経痛の考えられる原因や最新の治療法、自宅でできるセルフケアまで詳しく解説します。ご自身の症状と照らし合わせ、つらい痛みを和らげるためのヒントを見つけてください。
当院では、坐骨神経痛をはじめとした整形外科疾患に対し、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。不安な症状がある方も安心してご相談いただけるよう、以下の記事で診察の流れや受付方法を詳しくまとめています。
>>診察のご案内について

記事監修:川口 慎治
大室整形外科 脊椎・関節クリニック 医師
経歴:
徳島大学医学部卒業後、洛和会音羽病院に勤務
京都大学医学部整形外科学教室入局
学研都市病院脊椎脊髄センター勤務
2023年より 大室整形外科 脊椎・関節クリニック勤務
専門分野:脊椎・脊髄外科
資格:
日本専門医機構認定 整形外科専門医
日本整形外科学会認定 脊椎脊髄病医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科指導医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科専門医
坐骨神経痛とはお尻から足先にかけての痛みやしびれのこと
坐骨神経痛は、特定の病気の名前ではなく、症状を表す言葉です。お尻から足にかけて現れる「痛み」や「しびれ」をまとめて「坐骨神経痛」と呼びます。体には「坐骨神経」と呼ばれる太くて長い神経があります。坐骨神経は、腰からお尻の筋肉を通り、太ももの裏側から足先まで続いています。
坐骨神経痛は、長い神経のどこかで神経が圧迫されると症状が出ることがあります。症状の現れ方は人によってさまざまです。具体的な症状は、以下の表にまとめています。
| 分類 | 内容 |
| 痛みの場所 | ・お尻 ・太ももの裏 ・ふくらはぎ ・足の指先 |
| 痛みの種類 | ・電気が走るような鋭い痛み ・焼けるようなジンジンと熱い痛み ・ピリピリとしびれるような痛み |
| 感覚の異常 | ・しびれ ・足の皮膚の感覚が鈍い ・足に力が入りにくい ・足が冷たい |
初めは軽い違和感でも、放置すると日常生活に支障が出るほどの強い痛みにつながる可能性があるため、早めに専門医へご相談ください。
坐骨神経痛の原因
坐骨神経痛を引き起こす代表的な原因は、以下のとおりです。
- 腰椎椎間板ヘルニア
- 腰部脊柱管狭窄症
- 梨状筋症候群
- 坐骨神経痛を悪化させる生活習慣
腰椎椎間板ヘルニア
坐骨神経痛の代表的な原因の一つが「腰椎椎間板ヘルニア」です。20〜40代の比較的若い世代の方によく見られます。背骨は「椎骨」という骨がブロックのように積み重なっています。骨と骨の間でクッションの役割を果たしているのが「椎間板」です。
椎間板は、外側の硬い膜と、中の「髄核」というゼリー状の組織でできています。腰椎椎間板ヘルニアは、椎間板の中のゼリーが、何らかの理由で外に飛び出してしまう病気です。飛び出したゼリーが、すぐ近くを通る神経にぶつかると、強い炎症や圧迫が起こり、痛みやしびれなどの症状が出ます。症状が出やすい動作は、以下のとおりです。
- 前かがみになったとき
- 長時間イスに座っているとき
- 急に重いものを持ち上げたとき
- くしゃみや咳をした瞬間
腰椎椎間板ヘルニアは、症状の程度によって生活への影響が大きく変わります。以下の記事では、症状のレベル別の特徴や、手術以外も含めた治療法について詳しく解説しています。
>>腰椎椎間板ヘルニアの症状レベル別の特徴!治療法も解説
腰部脊柱管狭窄症
50歳を過ぎた頃から増えてくる原因が「腰部脊柱管狭窄症」です。背骨の中には、脳から続く大事な神経の束が通るトンネルがあります。このトンネルを「脊柱管」と呼び、年齢を重ねると骨が変形したり、靭帯が分厚くなったりします。腰部脊柱管狭窄症は、脊柱管が狭くなることで起こります。
脊柱管が狭くなると、中を通る神経が圧迫され、坐骨神経痛の症状として足の痛みやしびれ、力が入りにくいなどの症状が現れます。腰部脊柱管狭窄症の症状で代表的なのは「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」です。間欠性跛行は、歩くと足に痛みやしびれが生じますが、やや前かがみになって休むと症状が和らぎます。
姿勢によっても症状が変化することが特徴です。腰を後ろに反らすと脊柱管が狭くなるため症状が悪化し、反対に前かがみになると脊柱管が広がり、症状が楽になります。腰部脊柱管狭窄症は、高齢者を中心に増加しており、重症化すると歩行が大きく制限されることがあります。保存療法で改善しない場合、手術が検討されることもあります。
以下の記事では、腰部脊柱管狭窄症に対する手術の成功率やリスク、回復までの流れについて詳しく解説しています。
>>腰部脊柱管狭窄症の手術成功率は?リスクや回復までの流れを解説
梨状筋症候群
坐骨神経痛は「梨状筋(りじょうきん)症候群」のように、お尻の筋肉が原因で起こることもあります。梨状筋は、股関節を支える役割を担う、お尻の奥深くにある筋肉です。坐骨神経は、梨状筋のすぐ下、あるいは人によっては梨状筋の中を通っています。
長時間のデスクワークや運転、スポーツなどで梨状筋が硬くなると、硬い筋肉で神経を締め付ける状態になります。坐骨神経が圧迫され、お尻から足に痛みやしびれが出ます。レントゲン検査で骨に異常が見られないのに症状がある場合、筋症候群が原因の可能性があります。
坐骨神経痛を悪化させる生活習慣
坐骨神経を悪化させる生活習慣は、以下のとおりです。
| 悪化させる要因 | 具体的な内容 |
| 長時間同じ姿勢でいること | デスクワークや立ち仕事は、腰やお尻の筋肉を硬くし、血行を悪くする |
| 悪い姿勢の癖 | 猫背や反り腰、足を組む癖は骨盤の歪みを招き、腰に負担をかける |
| 運動不足 | 体を支える体幹の筋力が低下すると、背骨が不安定になり症状が出やすくなる |
| 体の冷え | 体が冷えると筋肉がこわばり、血流が悪くなり、痛みを感じやすくなる |
| 肥満(体重増加) | 体重が増えるほど、腰のクッションである椎間板や関節への負担が大きくなる |
| 精神的なストレス | ストレスは無意識に全身の筋肉を緊張させ、痛みをより強く感じさせる |
坐骨神経痛を悪化させる要因は、積み重なることで大きな負担です。症状の改善と再発予防のために、生活習慣を見直しましょう。
受診すべき危険なサイン
ほとんどの坐骨神経痛は、命の危険は少ないですが、まれに緊急の対応が必要な場合があります。以下の症状がみられた際は、神経に深刻なダメージが起きている可能性があります。
- 排尿・排便の異常:尿が出にくい、または尿意を感じない
- 感覚の異常:足の感覚がまったくない、皮膚を触っても鈍い感じがする
- 運動の麻痺:急に歩けなくなった、頻繁につまずくようになった
- その他の症状:激しい痛みが続く、発熱や原因不明の体重減少を伴う
危険なサインは「馬尾(ばび)症候群」と呼ばれる、緊急性の高い状態の可能性があります。放置すると、足の麻痺や排尿障害などの後遺症が残る危険性があります。すぐに整形外科を受診するか、夜間であれば救急外来に相談してください。
坐骨神経痛の治療法
坐骨神経痛の治療法は、以下が挙げられます。
- レントゲン・MRI検査による原因の特定
- 保存療法(薬物療法・リハビリテーション)
- ブロック注射
- 手術療法
- オゾン療法
レントゲン・MRI検査による原因の特定
坐骨神経痛の治療を始めるために、レントゲン検査やMRI検査などの画像検査を行い、原因を特定します。レントゲン検査は、骨の形や並び、骨折の有無などを確認する基本的な検査です。神経や椎間板そのものは写らないという欠点はあります。
MRI検査は磁気の力を利用して体の内部を詳しく撮影する検査です。レントゲン検査では見えない神経や椎間板、筋肉などの状態を鮮明に映し出すことができるとされています。レントゲン検査やMRI検査の結果と診察所見を総合的に判断し、一人ひとりに適切な治療計画を立てます。
坐骨神経痛の背景には、椎間板ヘルニアなど腰椎に関連する病気が隠れていることもあります。以下の記事では、椎間板ヘルニアになりやすい人の特徴やリスク要因、予防のポイントを詳しく解説しています。
>>椎間板ヘルニアになりやすい人の特徴とは?リスクを高める要因と予防法を解説
保存療法(薬物療法・リハビリテーション)
坐骨神経痛の治療は、多くの場合、手術をしない「保存療法」から始めます。保存療法は、お薬とリハビリテーションを組み合わせ、症状を和らげる方法です。痛みをコントロールしながら、体の機能の回復を待ちます。薬物療法には、以下の種類があります。
- 非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs):炎症を抑え、痛みを和らげる
- 神経障害性疼痛治療薬:ピリピリとした痛みやしびれを緩和する
- 筋弛緩薬:筋肉の緊張をほぐし、血行を改善する
- ビタミンB12製剤:傷ついた末梢神経の働きを助け、回復をサポートする
リハビリテーション(理学療法)は、痛み止めの薬で症状が和らいだ後に、理学療法士と取り組む治療です。リハビリテーションには、以下の2種類があります。
- 運動療法:ストレッチで筋肉の柔軟性を高めたり体幹を鍛えたりする
- 物理療法:電気や温熱を利用して血行を促進し、痛みを和らげる
ブロック注射
飲み薬やリハビリテーションを続けても痛みが改善しない場合に検討するのが、ブロック注射です。ブロック注射は、痛みの原因となる神経の近くに麻酔薬などを直接注射します。麻酔薬とともに炎症を強力に抑えるステロイド薬を使うこともあります。痛みを伝える神経の働きを一時的に止め、つらい痛みを緩和します。
痛みが和らぐことで、困難だった運動療法にも取り組みやすくなる可能性があります。
手術療法
坐骨神経痛の治療で、手術が必要になるケースは多くありませんが、以下の場合には手術を検討することがあります。
- 保存療法で効果が見られない:数か月間治療を続けても痛みが改善しない
- 麻痺が進行している場合:足に力が入らない、感覚が鈍くなる
- 排尿・排便の障害がある場合:尿や便が出にくい、あるいは漏れてしまう
手術の方法は、原因となる病気によって異なります。最近では、内視鏡を使った体への負担が少ない手術も普及しています。
症状を和らげるセルフケア
坐骨神経痛の症状を和らげるセルフケアについて、以下の3つをご紹介します。
- ストレッチや体操で筋肉を緩める
- 姿勢や寝方を見直す
- 冷却・温熱で痛みをやわらげる
ストレッチや体操で筋肉を緩める
梨状筋や腰まわりの筋肉をストレッチでほぐすことで、症状の緩和が期待できます。血行が良くなるお風呂上がりなど、体が温まっているときに行うのが良いとされます。寝ながらできる梨状筋のストレッチの手順は、以下のとおりです。
- 仰向けに寝て、両膝を立てる
- ストレッチしたい方の足首を、反対側の膝の上に乗せる
- 反対側の足の太ももの裏を両手で持ち、ゆっくりと胸の方へ引き寄せる
- お尻の奥の筋肉が「気持ちよく伸びている」と感じる場所で止める
- ゆっくり呼吸しながら20~30秒ほどその姿勢を保つ
- ゆっくりと元の姿勢に戻し、反対側の足も同じように行う
「キャット&ドッグ」と呼ばれる体操は、背骨全体の動きを滑らかにし、腰周りの筋肉の緊張を和らげます。キャット&ドッグの方法は、以下のとおりです。
- 肩の真下に手、股関節の真下に膝がくるように四つん這いになる
- 息をゆっくり吐きながら、おへそを覗き込むように背中を丸める
- 息を吸いながら、ゆっくりと背中を反らせる
- 「丸める」「反らす」の動きを、10回ほど繰り返す
姿勢や寝方を見直す
坐骨神経痛の再発予防のためには、腰に負担をかけない生活習慣を身につけることが重要です。長時間座るときは、1時間に1回は立ち上がって体を動かしましょう。座る際には、椅子の背もたれにお尻がつくまで深く腰掛けます。
背もたれを利用して背筋を伸ばし、骨盤を立てるように意識しましょう。腰と背もたれの間に丸めたタオルやクッションを挟むと、骨盤を立てやすくなります。椅子の高さを調整して膝の角度を90度にし、足裏全体を床につけることも重要です。
仰向けで寝るときは、膝の下に枕などを入れることで腰の反りが緩やかになり、筋肉の緊張が和らぎます。横向きで寝るときは、抱き枕やクッションを両膝の間に挟むと骨盤の高さが左右でずれるのを防ぎ、体が安定しやすいです。うつ伏せの姿勢は腰が反りやすく、首にも負担がかかるため避けましょう。
冷却・温熱で痛みを和らげる
急な痛みは冷やし、慢性的な痛みは温めましょう。腰に強い痛みが出たときや、患部が熱っぽくズキズキ痛むときは「急性期」と呼ばれ、炎症が起きている可能性があります。炎症を抑え、痛みの感覚を鈍くする効果が期待できます。
冷却は、氷のうや保冷剤をタオルで包み、1回15分程度を目安に痛みのある部分に当てて行います。冷やしすぎは血行不良や凍傷の原因になるため、直接肌に当てないようにしましょう。
急な痛みが落ち着き、鈍い痛みやこわばりが続いている「慢性期」には温めます。患部を温めて血行を良くすることで、硬くなった筋肉がほぐれて痛みの緩和が期待できます。温熱の方法は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 方法 | ・38〜40℃程度のぬるめのお風呂にゆっくり浸かる ・蒸しタオルやカイロを腰やお尻に当てる |
| 注意点 | 炎症が起きている急性期に温めると、痛みが強くなることがある |
冷やすのか温めるのか判断に迷う場合や、症状が悪化する場合は、自己判断せず医療機関へ相談しましょう。
当院(大室整形外科 脊椎・関節クリニック)は、脊椎センター・人工関節センターの2つを軸にしたクリニックです。腰や関節の痛み、リハビリなどでお悩みの方へ、専門医が丁寧に相談に応じます。JR姫路駅からは無料送迎バスを利用できますので、お気軽にご来院ください。
>>診察のご案内について
まとめ
お尻から足にかけてのつらい痛みやしびれは、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症など、さまざまな原因によって引き起こされます。「ただの腰痛だろう」と自己判断するのは危険です。原因を正確に突き止めることが、症状改善への大切な第一歩です。
治療法は手術だけでなく、お薬やリハビリテーション、生活習慣の見直しなど、症状に合わせた多様な選択肢があります。つらい症状を我慢せず、専門医へ相談してください。原因に合った適切なケアで、快適な毎日を取り戻しましょう。
特に腰部脊柱管狭窄症は高齢者に多く見られる病気であり、症状が進むと手術が検討される場合もあります。以下の記事では、手術の成功率やリスク、回復までの流れをわかりやすく解説しています。
>>腰部脊柱管狭窄症の手術成功率は?リスクや回復までの流れを解説