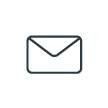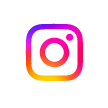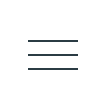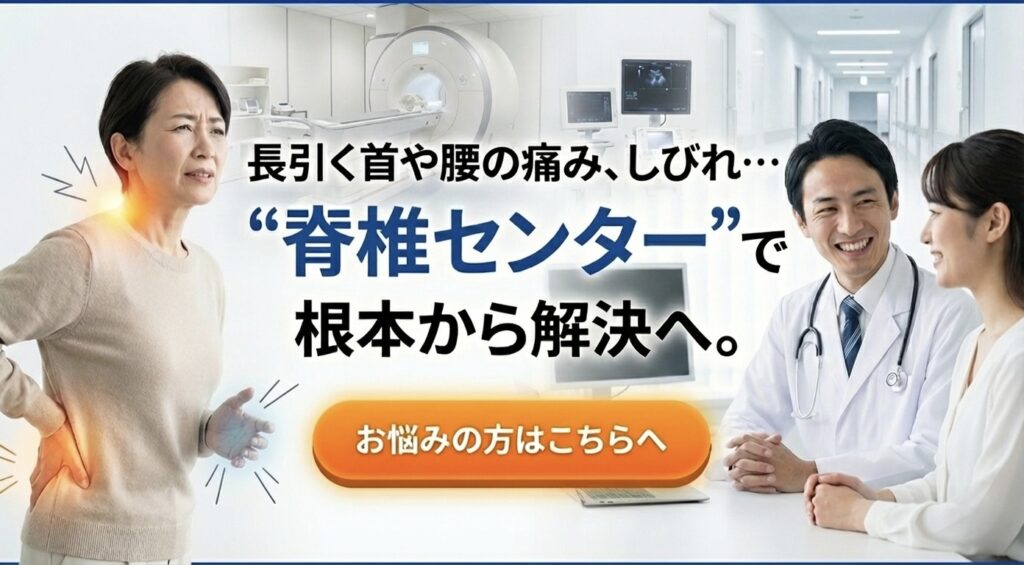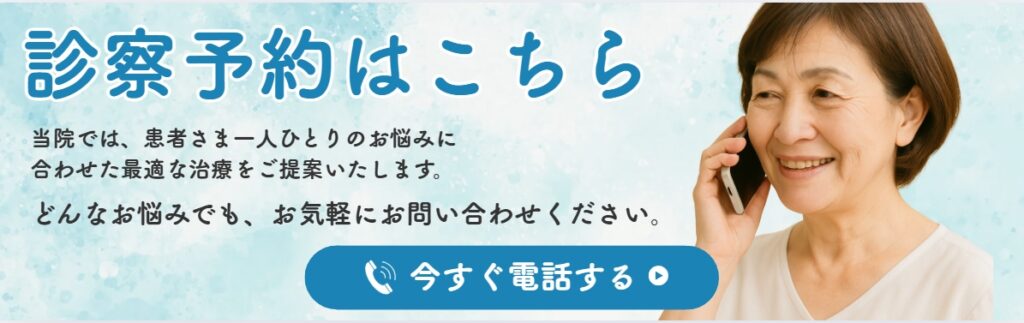片足だけのふくらはぎがだるい|足のしびれの原因や症状、自宅でもできる対処法
「片方のふくらはぎだけジンジンする」「なんだか重くてだるい」などの不快な症状を「ただの疲れ」だと見過ごしていませんか?不快な症状の裏には神経の圧迫や血管の詰まりといった、放置すると危険な病気が隠れている可能性があります。だるさやしびれの原因は、主に「神経」や「血管」「筋肉」からのSOSサインです。
急なむくみや激痛を伴う「エコノミークラス症候群」のように、命に関わる病気の初期症状である可能性もあります。この記事では、片足の不調を引き起こす原因を解説します。危険なサインの見分け方から、今すぐ自宅でできる簡単な対処法、専門的な治療法までを詳しくご紹介します。自分の体からの警告を見逃さないためにも、原因を確認しておきましょう。
当院では、片足のふくらはぎのだるさや足のしびれなどの症状に対し、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。不安な症状がある方も安心してご相談いただけるよう、以下の記事で診察の流れや受付方法を詳しくまとめています。
>>診察のご案内について

記事監修:川口 慎治
大室整形外科 脊椎・関節クリニック 医師
経歴:
徳島大学医学部卒業後、洛和会音羽病院に勤務
京都大学医学部整形外科学教室入局
学研都市病院脊椎脊髄センター勤務
2023年より 大室整形外科 脊椎・関節クリニック勤務
専門分野:脊椎・脊髄外科
資格:
日本専門医機構認定 整形外科専門医
日本整形外科学会認定 脊椎脊髄病医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科指導医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科専門医
片足のふくらはぎにしびれやだるさを引き起こす主な原因
片方のふくらはぎにしびれやだるさを引き起こす主な原因は、以下のとおりです。
- 神経の圧迫
- 血管のトラブル
- 筋肉の疲労や血行不良
神経の圧迫
腰から足にかけて伸びている神経が何かに押さえつけられる(圧迫される)と、ふくらはぎにしびれや痛みが出ることがあります。正座を続けた後に足がビリビリとしびれるのと同じ原理で、神経が圧迫されて、うまく情報を伝えられない状態です。神経の圧迫は、腰部に原因が隠れているケースが多く見られます。
神経が圧迫される主な病気は、以下のとおりです。
- 腰椎椎間板ヘルニア(ようついついかんばん):椎間板の中身が飛び出して神経を圧迫する病気
- 腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう):神経が通る脊椎管が狭くなる病気
- 坐骨神経痛:神経が圧迫されて出る症状の総称
上記の病気では、ふくらはぎの症状だけでなく、腰痛やお尻、太ももの裏にも痛みやしびれを伴うことが多いのが特徴です。
これらの病気は進行の程度によって、症状や治療方針が異なります。早期に対応することで悪化を防げる場合もあるため、症状の特徴を把握しておくことが大切です。以下の記事では、腰椎椎間板ヘルニアの症状をレベル別に整理し、それぞれに合った治療法について解説しています。
>>腰椎椎間板ヘルニアの症状レベル別の特徴!治療法も解説
血管のトラブル
足のしびれやだるさは、血液の流れが悪くなることでも起こります。血液は、体中に酸素や栄養を届ける大切な役割があります。血液の流れが滞ると、足の細胞が酸素不足や栄養不足になり、しびれやだるさなどのSOSサインを出します。特に片足だけに症状が出る場合、症状のある足の血管に問題が起きている可能性があります。
血管が原因で起こる主な病気を、以下の表にしました。
| 名称 | 起きる場所 | 主な原因 | 特徴的な症状 |
| 閉塞性動脈硬化症 | 心臓から足へ血液を送る動脈 | 動脈硬化による血管(動脈)の狭窄・閉塞 | 歩くとふくらはぎが痛くなり、少し休むと治まる |
| 深部静脈血栓症 | 足から心臓に戻る深い静脈 | 血管(静脈)内の塊(血栓)の詰まり | 片足の腫れや痛み、赤紫色の皮膚変色がみられる |
| 下肢静脈瘤(かしじょうみゃくりゅう) | 足の表面近くの静脈 | 静脈の弁が壊れて血液が逆流・うっ滞 | ボコボコ浮き出た血管や足のだるさ、重さ、むくみがみられる |
血管のトラブルが原因の場合、しびれやだるさに加えて、以下の症状を伴うことが多くあります。
- 足が冷たい
- 足の指の色が悪い
- むくみがひどい
筋肉の疲労や血行不良
特別な病気がなくても、日常生活の習慣が原因でしびれやだるさを感じることがあります。筋肉が疲れて硬くなっている状態や、疲れに伴う血行不良が関係しています。筋肉に負担をかける主な原因は、以下のとおりです。
- 長時間の立ち仕事やデスクワーク
- 慣れない運動による筋肉の使いすぎ
- 運動不足による筋力低下
- ストレスや自律神経の乱れによる筋肉の緊張
- 体の冷え
筋肉が疲れて硬くなると、近くを通る血管を圧迫し血行が悪くなり、筋肉の中に乳酸などの疲労物質が溜まります。溜まった疲労物質が「だるさ」や「重さ」として感じられるのです。血行不良によって神経への酸素や栄養が不足し、しびれとして感じることもあります。
多くの場合、十分な休息やストレッチで症状は和らぎます。セルフケアをしても症状が続いたり、ひどくなったりする場合は、神経や血管の病気が隠れている可能性も考えられます。
受診を検討すべき危険なサイン
受診を検討すべき危険なサインは、以下のとおりです。
- 激しい痛みや急なむくみ
- 皮膚の色の変化
- 麻痺症状
- 発熱
激しい痛みや急なむくみ
これまでに感じたことのないような激しい痛みやむくみは危険なサインです。以下の症状には注意が必要です。
- 強い打撲のようなふくらはぎの痛みがある
- 急に足が重だるくなり、動かしにくさがある
- 片方のふくらはぎだけが急激に腫れる
激しい痛みや急なむくみは「深部静脈血栓症」の可能性があります。俗に「エコノミークラス症候群」とも呼ばれる状態です。血栓(血の塊)が血管(静脈)の壁から剥がれて血の流れに乗ると、肺の血管に詰まることがあり、これを「肺塞栓症(はいそくせんしょう)」と言います。肺塞栓症は命に関わる危険な状態であるため、早急な対応が必要です。
激しい痛みや急なむくみのある場合は、自分でマッサージすることは避けてください。血栓が肺へ飛んでしまうきっかけになりかねません。すぐに整形外科や循環器内科を受診しましょう。
皮膚の色の変化
ふくらはぎのしびれやだるさと一緒に、足の皮膚の色が変わってきた場合も危険なサインです。血液の流れが悪くなっている可能性があり、足の動脈が硬くなる「閉塞性動脈硬化症」が疑われます。白っぽい・青白いなどの皮膚の色は、血液が足りていないサインです。触ってみると、氷のように冷たく感じることが多いです。
赤紫色・暗い紫色などの皮膚の色は、血液が心臓に戻れず、足によどんでいるサインです。むくみを伴うこともあります。皮膚の色の変化を放っておくと、足の細胞が死んでしまう「壊死(えし)」に進むこともあります。足が冷たく、色もおかしいと感じたら、血管の専門医に相談することが大切です。
麻痺症状
「麻痺(まひ)」は、最初は「少し感覚がおかしいな」という軽い症状から始まります。しびれに加えて以下の症状があると、麻痺のサインの可能性が考えられます。
- 足の皮膚を触っても、感覚が鈍い
- まるで厚いタイツの上から触られているような感覚がある
- 砂利の上を歩いているような、変な感覚がある
- 力が入りにくい
- スリッパやサンダルが、脱げやすくなる
- 何もないところで、よくつまずくようになる
- 足首や足の指に力が入らず、つま先立ちができない
- 階段をスムーズに上り下りできない
麻痺は、腰の骨(腰椎)の病気で神経が圧迫されていることが多いです。神経へのダメージが長く続くと、回復が難しくなることもあります。違和感がある場合は、早めに整形外科を受診しましょう。
排尿・排便のコントロールが困難になる「膀胱(ぼうこう)直腸障害」は、危険なサインです。馬尾(ばび)神経という大事な神経の束が、圧迫されていることを示しています。症状に気づいたら、夜間や休日でもすぐに病院へ連絡してください。
麻痺症状を引き起こす病気の一つに「腰部脊柱管狭窄症」があります。進行すると歩行障害や強いしびれを伴い、生活に大きな支障を及ぼすことがあります。
以下の記事では、腰部脊柱管狭窄症の症状や原因、しびれの特徴、治療法について詳しく解説しています。
>>腰部脊柱管狭窄症の症状とは?痛くなる原因やしびれの特徴、治療法まで解説
発熱
足のしびれや痛みに加えて、熱が出ている場合も注意が必要です。体温が高い、あるいは足だけが熱を持つときは、体の中で細菌と戦っているサインかもしれません。考えられる病気の例としては、次のようなものがあります。
- 蜂窩織炎(ほうかしきえん):皮膚の小さな傷から細菌が侵入し、足が赤く腫れて強い痛みや熱が出る
- 化膿性脊椎炎(かのうせいせきついえん):背骨に感染が起こり、腰痛や足のしびれと高熱を伴う
- 細菌感染症:体の中で細菌が増殖し、強い炎症や全身症状を引き起こす
これらは抗菌薬による治療がすぐに必要になるケースが多く、放置すると重症化する危険があります。関節リウマチなどの自己免疫疾患でも、しびれや痛みとともに発熱がみられることがあります。しびれや痛みに熱が加わっているときは単なる疲れではなく、医療機関で早めに原因を調べることが大切です。
症状を和らげるためのセルフケア
症状を和らげるためのセルフケアは、以下のとおりです。
- 静的ストレッチでじっくり伸ばす
- 姿勢を整える
- 体の冷えを防ぐ
静的ストレッチでじっくり伸ばす
「静的ストレッチ」は、ご自宅でも安全に行いやすく、血行改善に役立つ可能性があります。ふくらはぎのストレッチの手順は、以下のとおりです。
- 壁の前に立ち、両手を壁につく
- しびれやだるさがある方の足を、一歩大きく後ろに下げる
- 後ろ足のかかとを床につけたまま、前の足のひざをゆっくり曲げる
- ふくらはぎが「気持ちよく伸びる」と感じる場所で30秒止める
太ももの裏側(ハムストリングス)のストレッチは、以下の流れで行います。
- 椅子に少し浅めに座る
- 伸ばしたい方の足を前にまっすぐ伸ばし、かかとを床につける
- 背中が丸まらないように、胸を張ったまま体をゆっくり前に倒す
- 太ももの裏側が伸びているのを感じる場所で30秒止める
ストレッチをする際は、強さ・呼吸・動きに注意しましょう。「痛い」と感じるまで伸ばさず「気持ちいい」で止めましょう。息は止めずに、ゆっくり吐きながら伸ばします。反動をつけず、じっくりと筋肉を伸ばすことを意識しましょう。
姿勢を整える
しびれやだるさを悪化させないためには、毎日の姿勢も大切です。座っているときの注意点は、以下のとおりです。
- 足を組まない
- 両足の裏を床につけて深く座る
- 30分に一度は立ち上がる
足を組む癖は、骨盤のゆがみにつながります。ゆがみは腰やお尻の筋肉に負担をかけ、神経を圧迫する原因になります。30分に一度立ち上がって少し歩くと、血行が良くなります。立っているときは、両足へ均等に体重をかけましょう。
無意識に片方の足へ体重をかけると、体のバランスが崩れて腰や骨盤に負担がかかります。両足で均等に体を支えることで、安定した姿勢を保つことができます。
正しい姿勢を意識しても、腰痛の出方には「寝ると痛いが立つと楽になる」などの特徴的なケースがあります。こうした症状には原因があり、対処法を知ることが予防や改善につながります。
以下の記事では、その原因とすぐに取り入れられる対策を詳しく解説しています。
>>「腰痛で寝ると痛いけど、立つと楽」な症状は対策できる!原因やすぐにできる対策
体の冷えを防ぐ
体が冷えると血行不良が起こり、しびれやだるさを悪化させる原因になります。体の冷えを防ぐには、以下の工夫が大切です。
- 服装の工夫
- お風呂の入り方
夏でも冷房が効いた部屋では、足元が冷えることがあります。靴下やひざ掛けを上手に使い、特に足首を冷やさないようにしましょう。シャワーだけで済ませず、ぬるめのお湯にゆっくり浸かるのがおすすめです。全身の血の巡りが良くなり、硬くなった筋肉もほぐれやすくなります。お湯の温度は、38〜40度くらいが目安です。
あくまで症状を和らげるための補助的な手段です。続けても症状が良くならない、またはひどくなる場合は、必ず整形外科などの医療機関にご相談ください。
医療機関で行う治療法
医療機関で行う治療法は、以下のとおりです。
- MRIや超音波(エコー)などによる原因の特定
- 保存療法(薬物療法・理学療法・ブロック注射)
- 手術療法
- 再発予防に向けたリハビリテーション
MRIや超音波(エコー)などによる原因の特定
原因を正確に突き止めることが、正しい治療に不可欠です。医療機関では、以下のような専門的な検査を組み合わせて、原因の特定を行います。
| 検査の種類 | 主にわかること | 解説 |
| MRI検査 | 神経の圧迫や椎間板の状態、筋肉や靭帯(じんたい)の損傷など | ・磁石の力で体の中を輪切りにして見る検査 ・レントゲンでは見えない神経や筋肉を詳しく映し出し、神経がどこで押さえつけられているかを確認 |
| 超音波(エコー)検査 | 血管の詰まりや血流の状態、血栓の有無、筋肉や腱(けん)の状態 | ・体に超音波をあて、中の様子をリアルタイムで見る検査 ・血管の中を流れる血液の様子を見るのが得意 ・「エコノミークラス症候群」の診断 |
| レントゲン検査 | 骨の変形や骨折の有無、骨と骨のすき間 | ・体の骨の写真を撮る、基本的な検査 ・背骨が変形して、神経の通り道を邪魔していないかなどを確認 |
超音波(エコー)検査は、血管のトラブルを見つける場合に期待が持てます。リアルタイムで血の流れがわかるため、命に関わる血栓がないか、すぐに確認できます。筋肉が弱っていないか、左右差はないかなどを客観的に評価できます。
検査で原因を把握することは、症状の背景にある病気を見逃さないために重要です。椎間板の異常が関与するケースでは、生活習慣や体質などがリスクを高める要因となることがあります。
以下の記事では、椎間板ヘルニアになりやすい人の特徴や予防のポイントを解説しています。
>>椎間板ヘルニアになりやすい人の特徴とは?リスクを高める要因と予防法を解説
保存療法(薬物療法・理学療法・ブロック注射)
検査で原因がわかったら、多くの場合、手術をしない「保存療法」から始めます。主な保存療法は、以下の3つです。
- 薬物療法
- 理学療法
- ブロック注射
薬物療法では、症状を和らげ体の回復を助ける以下の薬を使います。
- 痛み止め(非ステロイド性抗炎症薬):炎症を抑えて、痛みを和らげる
- 血流改善薬:血液の通り道である血管を広げ、足のすみずみまで血を届ける
- 神経障害性疼痛治療薬:傷ついた神経が原因で起こる痛みを抑える
- ビタミン剤(ビタミンB12など):神経の働きを助け、ダメージを受けた神経の回復をサポートする
理学療法では、国家資格を持つ理学療法士が、運動などを通じて体の機能回復を目指します。電気をあてたり温めたりして、筋肉の緊張をほぐすことを「物理療法」と呼びます。「運動療法」は、ストレッチで筋肉を柔らかくし、筋力トレーニングをすることを指します。
ブロック注射は、痛みを引き起こしている神経の近くに、直接薬を注射する治療法です。痛みの信号をブロックするため、強い痛みを素早く和らげる効果が期待できます。痛みが軽くなることで、筋肉の緊張がとれて血行が良くなります。「痛み→緊張→血行不良→さらに痛む」という悪循環を断ち切ります。
手術療法
保存療法を3か月ほど続けても症状が良くならない場合などには、手術を検討します。足の麻痺が進んでいて、日常生活に大きな支障がある場合も同様です。手術は、あくまで症状を改善するための選択肢の一つです。手術を検討するケースは、以下のとおりです。
- 薬やリハビリテーションを続けても、つらい痛みが続く
- 足に力が入らず、スリッパが脱げる、つまずきやすくなる
- 尿や便のコントロールが難しくなる
- しびれや麻痺が悪化している
手術には、神経の圧迫を取り除く手術や、詰まった血管の流れを良くする手術などがあります。手術が必要と判断した場合は、なぜ必要なのか、どんな方法があるのかを医師から説明がありますので、ご安心ください。
再発予防に向けたリハビリテーション
再発を防ぐために、リハビリテーションは重要です。理学療法士の指導のもと、一人ひとりの状態に合わせた運動を行います。筋肉をゆっくり伸ばす「静的ストレッチ」は、効果を期待できます。
最近の研究では、静的ストレッチの継続は、筋肉が柔らかくなるだけでなく、筋力の向上や筋肥大の可能性も報告されています。痛みで筋トレができない方にも、有効性が示唆されるリハビリテーションです。リハビリテーションで目指すことは、以下の3つです。
- 筋力と柔軟性の向上
- 正しい体の使い方の習得
- セルフケアの習慣化
専門家の指導で、正しいストレッチや筋力トレーニングを行い、立ち方や歩方の癖を見直し、体に負担の少ない動作を習得できます。ご自宅で続けられる運動を覚え、良い状態をキープしましょう。
まとめ
片足のしびれの原因は筋肉の疲れだけでなく、神経や血管のトラブルが隠れていることもあります。ご紹介したストレッチなどのセルフケアはおすすめですが、以下の危険なサインが見られる場合は、放置しないでください。
- 激しい痛み
- 急なむくみ
- 麻痺
自己判断してしまうと、重大な病気のサインを見逃してしまうかもしれません。つらい症状や不安が続くようでしたら、一人で抱え込まず、まずは整形外科などの専門医へ気軽に相談してみましょう。原因を正しく知ることが、不快な症状から解放されるための大切な第一歩になります。
当院(大室整形外科 脊椎・関節クリニック)は、脊椎センター・人工関節センターの2つを軸にしたクリニックです。足のしびれや腰、関節の痛み、リハビリなどでお悩みの方へ、専門医が丁寧に相談に応じます。JR姫路駅からは無料送迎バスを利用できますので、お気軽にご来院ください。
>>診察のご案内について
参考文献
Konstantin Warneke, Michael Keiner, Tim Wohlann, Lars H Lohmann, Tina Schmitt, Martin Hillebrecht, Anna Brinkmann, Andreas Hein, Klaus Wirth, Stephan Schiemann.Influence of Long-Lasting Static Stretching Intervention on Functional and Morphological Parameters in the Plantar Flexors: A Randomized Controlled Trial.J Strength Cond Res,2023,37,10,p.1993-2001