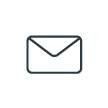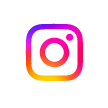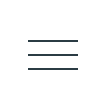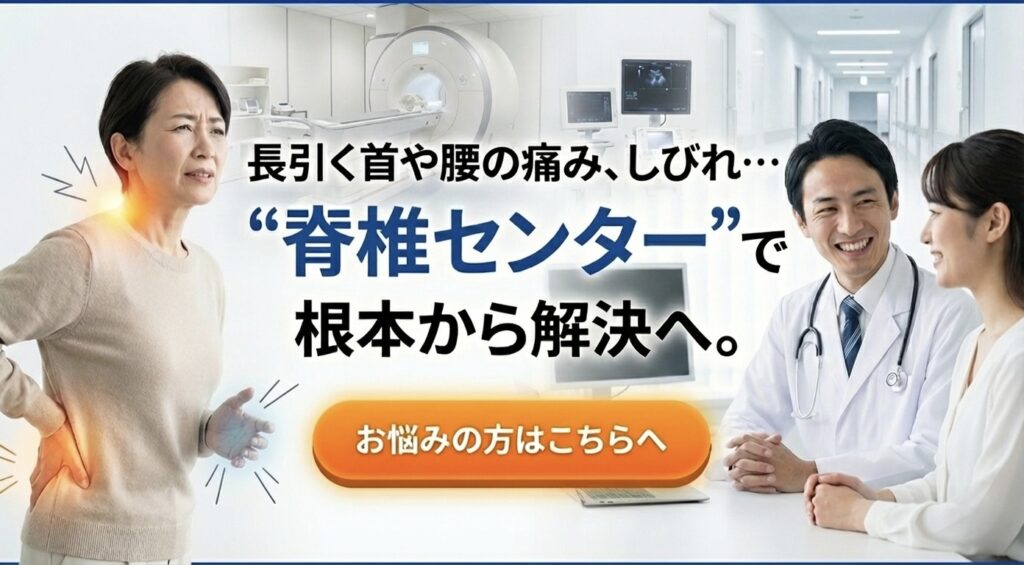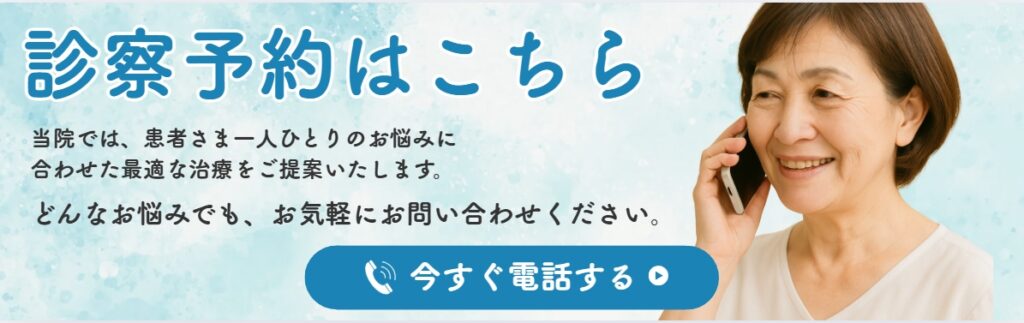頸椎症性脊髄症とは?痛くなる原因や症状、治療法を解説
「最近、手の動きがぎこちない」「何もない所でつまずきやすい」など、体の変化に戸惑いや不安を感じていませんか?首の骨の変形によって脊髄が圧迫される「頸椎症性脊髄症(けいついしょうせいせきずいしょう)」の可能性があります。
主な原因は加齢ですが、日本人は欧米の方と比べて神経の通り道が狭い傾向にあります。多くの人にとって他人事ではない病気です。本記事では、頸椎症性脊髄症の原因や見過ごしやすい代表的な症状、手術を含む治療法を解説します。早期発見や適切な治療につながるよう、ご自身の状態を正しく理解しましょう。
当院では、頸椎症性脊髄症をはじめとした整形外科疾患に対し、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。不安な症状がある方も安心してご相談いただけるよう、以下の記事で診察の流れや受付方法を詳しくまとめています。
>>診察のご案内について

記事監修:川口 慎治
大室整形外科 脊椎・関節クリニック 医師
経歴:
徳島大学医学部卒業後、洛和会音羽病院に勤務
京都大学医学部整形外科学教室入局
学研都市病院脊椎脊髄センター勤務
2023年より 大室整形外科 脊椎・関節クリニック勤務
専門分野:脊椎・脊髄外科
資格:
日本専門医機構認定 整形外科専門医
日本整形外科学会認定 脊椎脊髄病医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科指導医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科専門医
頸椎症性脊髄症とは首の骨の変形で神経が圧迫される病気
頸椎症性脊髄症は、首の骨である「頸椎」が変形し、神経の束である「脊髄」を圧迫する病気です。背骨には、脳からの指令を全身に伝える脊髄が通っています。脊髄が圧迫されると、脳からの指令が手足に伝わらなくなり、さまざまな症状が現れます。
椎間板(ついかんばん)は骨と骨の間にあり、衝撃を吸収し、背骨の動きを支え、体を安定させる組織です。年齢とともに水分を失い、弾力がなくなり、薄くなっていきます。骨のふちがトゲのように変形する骨棘(こつきょく)が形成されると、神経の通り道を狭めてしまいます。
日本人は欧米の方と比べて、神経の通り道が狭い傾向にあると言われています。日本人は、加齢による少しの変化でも脊髄が圧迫されやすく、注意が必要です。手足のしびれや歩きにくさを感じたら、放置せず専門医に相談しましょう。
首の神経を圧迫する病気には頸椎症性脊髄症のほかに、椎間板が突出することで症状を起こす「頚椎椎間板ヘルニア」もあります。どちらも首や肩の痛み、手足のしびれを伴うことがありますが、原因や治療法は異なります。以下の記事では、頸椎椎間板ヘルニアの症状・原因・治療法を解説しています。
>>【首や肩の痛みは要注意】頸椎椎間板ヘルニアの症状・原因・治療法を解説
頸椎症性脊髄症の原因
頸椎症性脊髄症の原因について、以下を解説します。
- 加齢による椎間板や骨の変性
- 椎間関節や靱帯の肥厚による脊柱管の狭窄
- 外傷や姿勢の悪さなど生活習慣による影響
加齢による椎間板や骨の変性
頸椎症性脊髄症の原因は、年齢を重ねることによる頸椎の変化です。症状出現までの変化は、以下のとおりです。
- 年齢とともに椎間板の水分が失われ、弾力が低下する
- 椎間板の弾力が低下し、首の骨が不安定になる
- 不安定な骨を安定させようと、骨棘を形成して補強しようとする
- 骨棘や変形した椎間板が、神経の通り道である脊柱管を狭くする
- 脊柱管の中を通る脊髄が圧迫され、手足のしびれなどの症状が出現する
長期にわたる首への負担が、頸椎症性脊髄症の根本的な原因となります。
椎間関節や靱帯の肥厚による脊柱管の狭窄
脊柱管の中を縦に走行している「後縦靱帯(こうじゅうじんたい)」や「黄色靱帯」の肥厚(ひこう)は、脊柱管が内側から狭められる原因です。加齢による変化は、椎間板や骨だけでなく、骨と骨をつなぎ止めている靱帯にも影響を及ぼすためです。
首の骨が不安定になると、靱帯を分厚く、硬くし体を支えようと補います。肥厚と呼ばれる状態です。骨棘と靱帯の肥厚が合わさると、脊髄は前後から挟まれるように圧迫されます。日本人は脊柱管が狭い傾向にあるため、加齢による少しの変化でも症状が出やすいと考えられています。
研究では、生まれつき脊柱管が狭い方はそうでない方と比較し、術後同等の生活の質が得られると報告があります。生まれつき脊柱管が狭い場合でも、適切な治療と早期介入により、改善は期待されるとされます。
外傷や姿勢の悪さなど生活習慣による影響
日々の生活習慣が加わることで、頸椎の変性が加速し、症状の引き金となることがあります。首に負担をかける生活習慣は、以下のとおりです。
- スマートフォンやパソコン作業で、長時間うつむいている
- デスクワークなどで猫背の姿勢を続けている
- 高すぎる枕を使っている、またはうつぶせで寝る癖がある
- 重い荷物を日常的に持つ仕事をしている
- 洗濯物を干すなど、長時間上を向く作業が多い
- ダンスや格闘技など、首を激しく動かす運動をしている
うつむいた姿勢では、頭の重さが首に直接かかり、負担は通常の何倍にもなります。過去の外傷で、転倒により頭や首を強く打ったことがある、交通事故でむちうちになった経験がある方も注意が必要です。日々の小さな負担の蓄積が、椎間板や骨の変性を早めてしまう可能性があります。
日頃から正しい姿勢を意識し、首への負担を減らすことが症状の悪化を防ぐうえで大切です。
仕事を続けながら治療を行う場合、休むべきタイミングや復帰の目安を理解しておくことが重要です。以下の記事では、頸椎椎間板ヘルニアで仕事を休む必要性や、手術後の休養期間・復職のタイミングを詳しく解説しています。
>>頸椎椎間板ヘルニアで仕事は休める?手術後の休む期間や職場復帰のタイミングを解説
頸椎症性脊髄症の代表的な症状
頸椎症性脊髄症の代表的な症状について、以下を解説します。
- 手の細かい作業が難しい(巧緻運動障害)
- 歩きにくい・つまずきやすい(歩行障害)
- 頻尿や残尿感がある(膀胱直腸障害)
手の細かい作業が難しい(巧緻運動障害)
初期症状は、指先の細かい作業が難しくなる「巧緻(こうち)運動障害」です。脊髄が圧迫されることで、脳から手や指への指令がスムーズに伝わらないことが原因で起こります。具体的な症状は、以下のとおりです。
- シャツのボタンをかけたり、外したりするのに時間がかかる
- 箸がうまく使えず、食べ物をポロポロと落としてしまう
- 字が震えたり、小さくなったり、以前のように字を書けない
- 財布から小銭をスムーズに取り出すことができない
- ペットボトルのキャップや瓶のフタを開けるのに苦労する
診断にはMRIなどの画像検査がありますが、画像の所見と症状の重さが必ずしも一致しない点には注意が必要です。研究では、MRIの画像が手術するかの判断材料になっており、MRIの結果だけで手術を決めるのは慎重にするべきと報告されています。画像検査の結果だけでなく、ご自身が自覚している症状が大切です。
歩きにくい・つまずきやすい(歩行障害)
歩行障害は、主に「運動麻痺」と「深部感覚の障害」が原因で起こります。手の症状の他に、少し遅れて足の症状が現れることも特徴です。注意が必要な症状は、以下のとおりです。
- 歩行中に足がもつれるような感覚があり、平らな道でつまずきやすい
- 歩くスピードが以前より遅くなったと感じる
- 階段を下りるのが怖く、手すりがないと不安に感じる
- 足の裏に一枚紙が貼りついているような鈍い感覚がある
- スリッパやサンダルが、意図せず脱げてしまうことがある
歩きにくさは、転倒による骨折などのけがにつながります。症状が進行すると、歩行時に杖などが必要になる場合もあります。歩き方の変化は、ご自身よりもご家族など周りの方が先に気づくことが多いです。
頻尿や残尿感がある(膀胱直腸障害)
頸椎症性脊髄症が進行すると、排尿や排便をコントロールしている神経にも影響が及びます。排泄に障害が起きることを「膀胱(ぼうこう)直腸障害」と呼びます。以下の症状には、注意が必要です。
- トイレに行く回数が増えた
- 排尿後も尿が残っている感じがする
- 急に強い尿意を感じ、我慢するのが難しい
- 尿の勢いが弱くなったり、尿が出にくくなったりする
- 以前より便秘がちになった
症状は、病状がある程度進行してから現れることが多いのが特徴です。加齢による変化や前立腺の病気(男性の場合)など、他の原因でも起こり得ます。手のしびれや歩行障害とあわせ、排泄のトラブルが出てきた場合は、頸椎症性脊髄症の可能性も考える必要があります。
頸椎症性脊髄症の治療法
治療法には、以下の選択肢があります。
- 手術をしない保存療法
- 神経の圧迫を取り除く手術療法
治療法は、症状の重さや進行具合、患者さんご自身の生活スタイルなどを総合的に考え、専門医と一緒に決めます。具体的な治療の流れについて、以下を解説します。
- まずは整形外科へ|MRIやレントゲンで精密検査
- 保存療法(薬・装具・リハビリ)
- 手術療法(前方除圧固定術・椎弓形成術)
- 手術が必要になるタイミングと判断基準
まずは整形外科へ|MRIやレントゲンで精密検査
症状に気づいたら整形外科を受診し、専門医による正確な診断を受けましょう。診断までに、問診・診察、画像検査があります。問診・診察では、症状がいつからあるか、日常生活で困っていることなどを伝えましょう。手足の感覚や力の入り具合、腱反射の検査で神経の状態を丁寧に評価します。
レントゲン検査では、骨棘の有無や首の骨が不安定になっていないか、生まれつき神経の通り道が狭いかどうかなどを調べます。MRI検査は、神経の状態を見る診断において重要な検査です。脊髄の圧迫の程度や変性の有無を確認します。
CT検査では、骨の形を立体的に見ることができる検査です。「後縦靭帯骨化症」の病気がないかを確認したり、手術計画を立てたりする際に役立つとされています。検査結果を総合的に判断し、症状の原因を突き止めます。
保存療法(薬・装具・リハビリテーション)
保存療法には、以下のとおりです。
- 薬物療法
- 装具療法
- リハビリテーション
薬物療法で使用される薬と期待される効果は、以下の3つがあります。
- 消炎鎮痛薬:痛みや炎症を抑える
- 神経障害性疼痛治療薬:しびれや痛みを和らげる
- 筋緊張弛緩剤:筋緊張をほぐし血行を改善、こりを和らげる
装具療法は、頸椎カラーを首に装着します。首の動きを制限することで首を安静な状態に保ち、脊髄への余計な負担を減らす効果が期待されます。使用場面は、パソコン作業など長時間うつむき姿勢になる場面です。
リハビリテーションは、理学療法士が患者さんの状態に合わせ計画を立てます。主なリハビリテーションは物理療法と運動療法です。物理療法は、首を温めて血行を良くする温熱療法、優しく引っ張る牽引療法をすることで筋肉の緊張を和らげ、痛みを軽減させます。運動療法は、首に負担がかからない範囲でストレッチや筋力トレーニングを行います。
セルフケアとしてできる工夫や注意点を取り入れることで、治療効果をより高めることができます。以下の記事では、頸椎椎間板ヘルニアの痛みを和らげる方法や日常での対処法について解説しています。
>>頸椎椎間板ヘルニアの痛みを和らげる方法!効果が期待できる対処法と注意点
手術療法(前方除圧固定術・椎弓形成術)
手術の目的は、神経の圧迫を取り除き、神経の通り道を広げる(除圧する)ことです。保存療法を続けても症状が改善しない場合や歩行障害などが進行し、日常生活に支障が出ている場合は、手術療法を検討します。代表的な手術は、表のとおりです。
| 手術方法 | アプローチ方向 | 特徴 |
| 前方除圧固定術 | 首の前方 | ・圧迫の原因である椎間板や骨棘を直接取り除く ・取り除いたスペースに、自家骨や人工骨を入れ、固定する ・圧迫されている範囲が1〜2か所と狭い場合に適応される |
| 椎弓形成術 | 首の後方 | ・背骨の一部(椎弓)を扉のように開き、金属のプレートで固定し脊柱管を広げる ・広範囲にわたって圧迫がある場合や神経の通り道がもともと狭い方に適応される |
どちらの方法を選択するかは、圧迫されている場所や範囲、首の骨の並びなどによって決まります。
手術が必要になるタイミングと判断基準
手術を検討するタイミングに、以下の症状があります。
- 保存療法を続けても、手のしびれや痛みが悪化している
- 階段を下りるのが怖く、手すりがないと不安を感じる
- 平らな道でも、足がもつれてつまずきやすくなった
- 以前よりお箸がうまく使えず、食べ物を落としてしまう
- シャツのボタンをかけたり、外したりするのに時間がかかる
- ペットボトルのキャップが開けにくくなった
- トイレに行く回数が増えた、または尿が出にくくなった
手術のタイミングは逃さないことが重要です。一度ダメージを受けてしまった神経は、圧迫を取り除いても完全には回復しないためです。研究では、手術後の回復具合は、手術前の症状の重さやMRIで見た脊髄のダメージの程度に大きく影響されることが報告されています。
症状が進行する前に専門医に相談し、適切なタイミングで治療方針を決めることが、より良い回復へとつながる可能性があります。
姫路市で専門治療なら大室整形外科へ|保存療法から手術まで対応
姫路市や周辺にお住まいで、手のしびれや歩きにくさにお悩みでしたら、脊椎センターを持つ当院へご相談ください。患者さん一人ひとりに合わせ、専門医が丁寧に相談に応じます。治療の基本は、体への負担が少ない保存療法です。症状が進行している場合は、手術も重要な選択肢です。当院では、専門的な知見にもとづき、以下の治療を提供します。
- 精密な検査にもとづいた診断:MRIなどの検査で、神経の圧迫の程度を正確に評価
- 多様な選択肢での治療アプローチ:新しい知見を取り入れ、最善の選択肢を検討
- 豊富な実績にもとづく手術治療:適切な手術で、症状の改善を追求
しびれや歩行障害は、生活の質を大きく下げてしまいます。まずは一度、当院(大室整形外科 脊椎・関節クリニック)の専門医へご相談ください。JR姫路駅からは無料送迎バスを利用できますので、お気軽にご来院ください。
>>診察のご案内
まとめ
頸椎症性脊髄症は、加齢による首の骨の変化が原因で起こり、放置すると症状が進行してしまう可能性があります。日々の生活習慣が加わることで、頸椎の変性が加速し、症状の引き金となることもあります。
治療で大切なのは「適切なタイミングを逃さないこと」です。一度ダメージを受けた神経は、圧迫を取り除いても完全には回復しない可能性があるためです。治療法は、保存療法から開始し、症状が改善しない場合や症状の内容によっては手術療法が選択されます。
「お箸が使いづらい」「階段を下りるのが怖い」など、症状に心当たりがあれば、当院の脊椎センターの専門医へ相談しましょう。早期の診断と治療が、より良い生活の質を守るために大切です。詳しいアクセス方法は、以下のページをご覧ください。
>>大室整形外科へのアクセスはこちら
参考文献
- Atli K, Chakravarthy V, Khan AI, Moore D, Steinmetz MP, Mroz TE.Surgical Outcomes in Patients with Congenital Cervical Spinal Stenosis.World Neurosurg,2020,141,,p.e645-e650
- Hilton B, Tempest-Mitchell J, Davies BM, Francis J, Mannion RJ, Trivedi R, Timofeev I, Crawford JR, Hay D, Laing RJ, Hutchinson PJ, Kotter MRN.Cord compression defined by MRI is the driving factor behind the decision to operate in Degenerative Cervical Myelopathy despite poor correlation with disease severity.PLoS One,2019,14,12,p.e0226020
- Lindsay A Tetreault, Alina Karpova, Michael G Fehlings.Predictors of outcome in patients with degenerative cervical spondylotic myelopathy undergoing surgical treatment: results of a systematic review.Eur Spine J,2015,24,Suppl 2,p.236-51