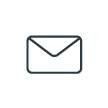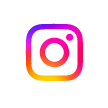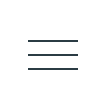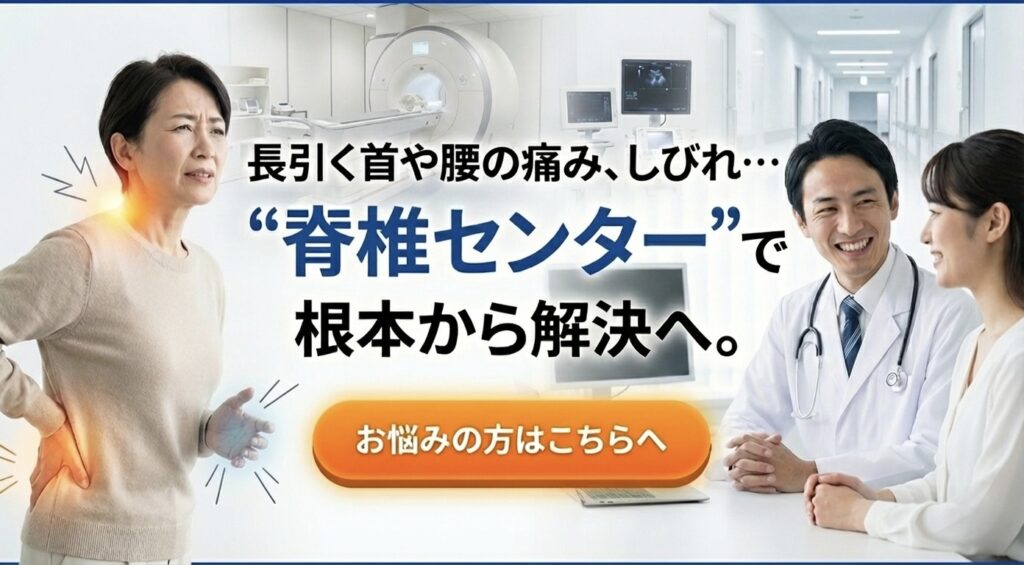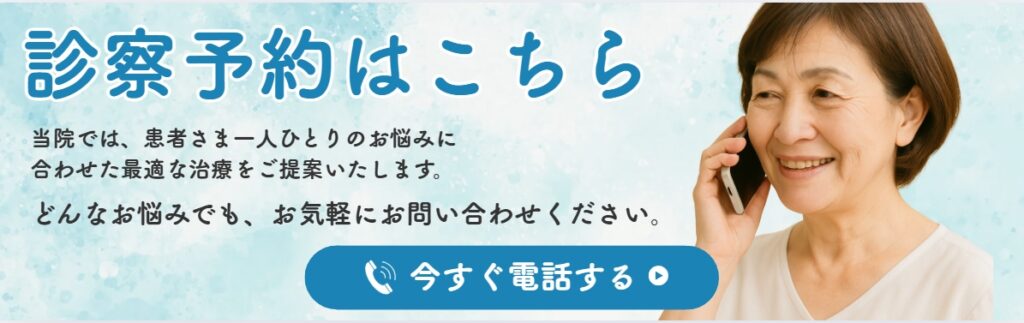腰椎すべり症の原因と特徴!年代別リスクと治療法を解説
腰がだるかったり、歩くと足がしびれたりしませんか?腰のだるさなどの症状は、腰の骨がずれる「腰椎すべり症」である可能性があります。単なる腰痛と軽く考えていると、気づかないうちに症状が進行してしまうこともある、注意が必要な病気です。
腰椎すべり症の原因は、主に「加齢」と「若い頃のスポーツ」の2つに分けられます。年代や性別によってリスクが大きく異なるのが特徴です。本記事では、腰椎すべり症の年代別の原因や脊柱管狭窄症との見分け方などを解説します。ご自身の症状と照らし合わせ、適切な対策への第一歩を踏み出しましょう。
当院では、腰椎すべり症をはじめとした整形外科疾患に対し、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。不安な症状がある方も安心してご相談いただけるよう、以下の記事で診察の流れや受付方法を詳しくまとめています。
>>診察のご案内について

記事監修:川口 慎治
大室整形外科 脊椎・関節クリニック 医師
経歴:
徳島大学医学部卒業後、洛和会音羽病院に勤務
京都大学医学部整形外科学教室入局
学研都市病院脊椎脊髄センター勤務
2023年より 大室整形外科 脊椎・関節クリニック勤務
専門分野:脊椎・脊髄外科
資格:
日本専門医機構認定 整形外科専門医
日本整形外科学会認定 脊椎脊髄病医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科指導医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科専門医
腰椎すべり症の2大原因
腰椎すべり症の2大原因を、以下の項目に沿って解説します。
- 加齢が引き起こす変性すべり症
- スポーツでの疲労骨折が原因の分離すべり症
加齢が引き起こす変性すべり症
変性すべり症は、主に加齢が原因で起こるすべり症です。背骨の間でクッションの役割を担う「椎間板」や骨同士をつなぐ「靭帯」が長年の負担で傷むことが原因です。本来、腰椎をがっちりと支えている組織が弱まることで、腰椎の安定性が失われ、骨が前後にずれてしまいます。特に腰の上から4番目の「第4腰椎」で起こりやすいことが特徴です。
加齢が原因のタイプは、40代以降の女性に多く見られます。閉経による女性ホルモンの減少が、骨の質を低下させることも、発症の一因として関係していると考えられています。加齢による体の変化は誰にでも起こりますが、生活習慣を見直すことでリスクを減らすことは可能です。
肥満や運動不足は腰痛を悪化させる原因です。バランスの良い食事や適度な運動を心がけましょう。研究では、変性すべり症による痛みや機能障害に対して、手術療法が有効であるとの報告もあります。まずは原因を正しく理解し、ご自身の状態に合った治療を選びましょう。
スポーツでの疲労骨折が原因の分離すべり症
分離すべり症は、若い頃のスポーツが原因で起こることがあります。「腰椎分離症」という、背骨の疲労骨折から進行するケースがほとんどです。特に、成長期にジャンプや腰をひねる動作を繰り返すと、背骨の後方部分(椎弓)に負担が集中し、ひびが入ることがあります(疲労骨折)。
野球やサッカー、バレーボール、柔道などの部活動に打ち込んだ経験のある方は、スポーツが原因のタイプのリスクが考えられます。10代で分離症を発症し、症状がないまま過ごし、30〜40代になってから腰痛や足のしびれが現れることも少なくありません。
脊柱管狭窄症や椎間板ヘルニアとの見分け方
腰の痛みや足のしびれは、腰椎すべり症だけの症状ではありません。似た症状が出る病気に「脊柱管狭窄症」や「椎間板ヘルニア」があります。どの病気が原因かわからず、不安に感じる方も少なくありません。神経が圧迫される点は同じですが、症状の出方に違いがあります。
腰椎すべり症と脊柱管狭窄症は、症状がよく似ています。どちらも腰を反らすと神経の通り道が狭まり、痛みやしびれが悪化します。歩くと足がしびれる「間欠性跛行」も、2つの病気に共通する症状です。
椎間板ヘルニアは、前かがみになると痛みが強くなるのが特徴です。飛び出したクッションが、さらに神経を圧迫するためです。せきやくしゃみで、足に激痛が響くこともあります。病気ごとの特徴は目安であり、すべり症が原因で脊柱管が狭くなるなど、複数の病気が隠れていることもあります。
足の力が急に入らなくなったり、尿や便が出にくくなったりした場合は、すぐに専門医の診察が必要なサインです。ご自身の判断で様子を見るのではなく、まずは整形外科にご相談ください。レントゲンやMRI検査で原因を正確に突き止め、適切な治療を始めましょう。
以下の記事では、腰椎椎間板ヘルニアにおける症状のレベル別の違いや、それぞれに適した治療法について詳しく解説しています。症状の進行度を知ることで、より適切な対処につながります。
>>腰椎椎間板ヘルニアの症状レベル別の特徴!治療法も解説
腰椎すべり症の主な症状
腰椎すべり症の主な症状は以下のとおりです。
- 間欠性跛行(歩くと足がしびれて休みが必要)
- 坐骨神経痛(お尻や太ももの痛み・しびれ)
間欠性跛行(歩くと足がしびれて休みが必要)
腰椎すべり症を代表する症状の一つが「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」です。休み休みでないと、続けて歩けない状態を指します。歩き始めは平気でも、しばらくすると足が痛くなったり、しびれたりして、歩き続けるのが困難になります。少し休むと症状が和らぎ、また歩けるようになるのが大きな特徴です。
歩くときは、自然と背筋が伸びて腰が少し反った姿勢になります。腰が反った姿勢が、腰の神経の通り道をさらに圧迫するため、足に痛みやしびれが出てくるのです。反対に、前かがみになると神経の圧迫がゆるみ、症状が楽になります。間欠性跛行の症状は、生活の質を大きく下げる原因です。「年のせい」と諦めずに、専門医にご相談ください。
坐骨神経痛(お尻や太ももの痛み・しびれ)
間欠性跛行と並んで多く見られるのが、お尻から足にかけて広がる痛みやしびれです。坐骨神経痛(ざこつしんけいつう)と呼ばれます。坐骨神経は、腰からお尻を通り、足先まで伸びる太い神経です。腰椎すべり症によって神経の根元が圧迫されると、神経が伸びている範囲に沿って、以下の不快な症状が現れます。
- 電気が走るような鋭い痛み
- 焼けるような痛み
- 正座の後の感覚
- 足の皮膚の感覚が鈍い
- 足に力が入りにくい
症状は片足だけに出ることも、両足に出ることもあります。長時間立っている、腰を反らすといった動作で強くなるのが特徴です。放置すると筋力の低下が進むこともあるため、注意が必要です。
年代別の腰椎すべり症になりやすい人の特徴
年代別の腰椎すべり症になりやすい人の特徴は以下のとおりです。
- スポーツで腰に過度な負担をかけた経験がある10〜20代
- 加齢や閉経による骨質の低下しやすい40代以降の女性
スポーツで腰に過度な負担をかけた経験がある10〜20代
10代や20代の若い世代に起こる腰痛は「分離すべり症」の可能性があります。骨が成長しきっていない時期に、腰に強い負担がかかると「腰椎分離症」という背骨の一部の疲労骨折を起こすことがあります。
腰椎分離症になった方は、将来的に骨がずれる「分離すべり症」へ移行する可能性があります。若い方のすべり症で手術を考える場合は、特に注意が必要です。手術の方法によって、将来再び手術が必要になる確率が、大きく変わることが研究でわかっています。
ある研究では、前方からのみ骨を固定する手術(ASF)だと、5年以内に再手術が必要になったほうが31.8%にのぼりました。一方、前方と後方の両方から固定する手術(A+PSF)では、再手術率は7.0%まで抑えられていました。
将来の生活を見据え、納得できる治療を選ぶことが大切です。専門医と相談し、ご自身に合った治療法を見つけましょう。
以下の記事では、若い世代でも発症する椎間板ヘルニアの背景や、原因となる日常習慣・予防法について詳しく解説しています。20代でも他人事ではない理由がわかります。
>>若い人の椎間板ヘルニアの原因とは?20代でもなる理由と予防法
加齢や閉経による骨質の低下しやすい40代以降の女性
40代を過ぎてからの腰痛や足のしびれは「変性すべり症」の可能性があります。長年の負担と、加齢による体の変化が主な原因です。特に中年以降の女性に多く見られるのが特徴です。女性の場合、閉経にともなう女性ホルモンの減少が、リスクをさらに高めることが知られています。
女性ホルモン(エストロゲン)には、骨を壊す細胞の働きを抑え、骨を丈夫に保つ大切な役割があります。女性ホルモンが減ることで骨がもろくなる「骨粗しょう症」が進み、腰椎がずれやすい状態になってしまうのです。
腰椎すべり症の治療法5つ
腰椎すべり症の5つの治療法は以下のとおりです。
- コルセット
- 薬物療法
- リハビリテーション
- 強い痛みを抑えるブロック注射
- 手術療法(固定術)
コルセット
腰に強い痛みがある場合、まず試されるのがコルセットです。コルセットは、不安定になった腰を外から支える方法です。腰を固定し、負担を軽くする役割があります。ただし、コルセットは万能ではありません。
ずっと頼りすぎると、ご自身の体を支える腹筋や背筋が弱り、治りづらくなる可能性があります。コルセットを強く締め付けると、血行不良の原因になる場合もあります。痛みが強い時期に限定して使うなど、医師の指示を守ることが大切です。
以下の記事では、椎間板ヘルニアに対するコルセットの効果や、正しい使い方・選び方について詳しく解説しています。
>>椎間板ヘルニアにコルセットの効果はある?正しい装着法と選び方を徹底解説
薬物療法
薬物療法は、つらい痛みやしびれを和らげる治療です。症状を抑えることで、日常生活の質を取り戻したり、リハビリテーションに前向きに取り組めるようにしたりする大切な役割があります。症状に合わせて、複数の薬の使い分けや、組み合わせをします。薬物療法で使われる主な薬は以下のとおりです。
- 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs):痛みや炎症を抑えるお薬
- 筋弛緩薬(きんしかんやく):緊張してしまった筋肉をほぐすお薬
- 神経障害性疼痛治療薬:神経の圧迫による痛みを緩和させるお薬
医師が患者さんの状態を慎重に見極めて処方します。効果の出方や副作用は人それぞれです。ご自身の判断で量を調整したり、やめたりすることは避けてください。気になることがあれば、どんな小さなことでも相談しましょう。
リハビリテーション
リハビリテーションは、症状の根本改善と再発予防を目指す重要な治療です。専門の理学療法士が、一人ひとりの体の状態を詳しく評価し、その方に合った最適なプログラムを作成して、二人三脚で進めていきます。リハビリテーションの主な内容は以下のとおりです。
- 運動療法:下肢のストレッチや筋力トレーニングで背骨の安定性を高める
- 物理療法:温熱療法や電気治療で筋肉の緊張を和らげる
- 日常生活の指導:無意識で腰に負担をかけている癖を見直す
強い痛みを抑えるブロック注射
飲み薬やリハビリテーションを続けても痛みが取れない場合や、夜も眠れないほど強い痛みがある場合には、ブロック注射が用いられます。痛みの原因となっている神経のすぐ近くに、麻酔薬などを注入する方法です。
注射によって痛みが和らいでいる間にリハビリテーションを集中して行うことで、治療を進めやすくなることがあります。痛みにただ耐えるのではなく、積極的に症状をコントロールする方法です。
手術療法(固定術)
保存療法を数か月間続けても症状が良くならない場合などは、手術療法を検討します。手術方法としては固定術が一般的ですが、施設によっては内視鏡手術が選択されます。ある研究では、内視鏡を使った低侵襲手術が、痛みや機能障害の改善に最も優れていたと報告されています。傷口が小さく、入院期間の短縮や再手術率の低下も期待できます。一方で、他の手術法より合併症の確率が高いという側面もあります。
若い方の手術では、将来の再手術リスクを考えることが特に重要です。最近の研究で、手術方法によって再手術率が大きく違うことがわかりました。同じすべり症の手術でも、原因や年齢によって最適な方法は異なります。医師と相談しながら、ご自身に合った治療法を選びましょう。
まとめ
腰椎すべり症は、加齢による「変性すべり症」と、若い頃のスポーツが原因の「分離すべり症」に分けられ、それぞれ適した治療法が異なります。治療には、コルセットやリハビリテーションといった保存療法から、内視鏡を使った体への負担が少ない手術まで、さまざまな選択肢があります。
大切なのは「年のせい」や「古傷だから」と諦めずに、ご自身の体の状態を正確に把握することです。つらい症状の原因を突き止め、あなたに合った治療法を見つけるために、まずは一度、整形外科などの専門医へお気軽にご相談ください。
当院の受診をご希望の方は、まずはお電話にてご予約ください。詳しいアクセス方法は、以下のページをご覧ください。
>>大室整形外科へのアクセスはこちら
参考文献
- Paal K Nilssen, Nakul Narendran, Ryan A Finkel, Kenneth D Illingworth, David L Skaggs.Spondylolisthesis in Young Patients in a Large National Cohort: Reoperation Rate Depends on Surgical Approach.J Bone Joint Surg Am,2024
- Hao Jia, Zhuo Zhang, Jianpu Qin, Lipei Bao, Jun Ao, Hu Qian.Management for degenerative lumbar spondylolisthesis: a network meta-analysis and systematic review basing on randomized controlled trials.Int J Surg,2024,110,5,p.3050-3059