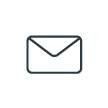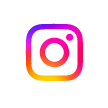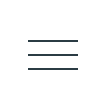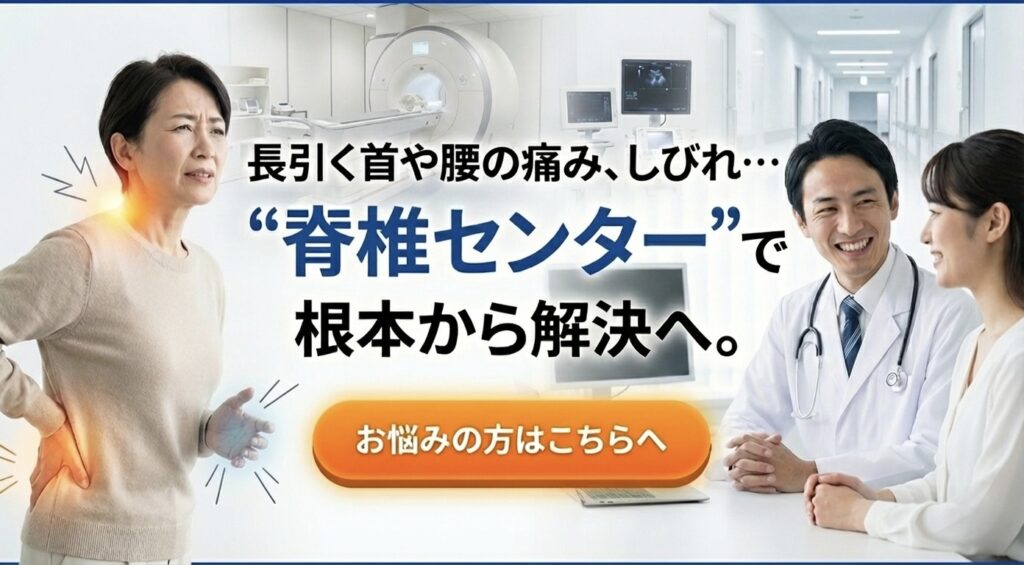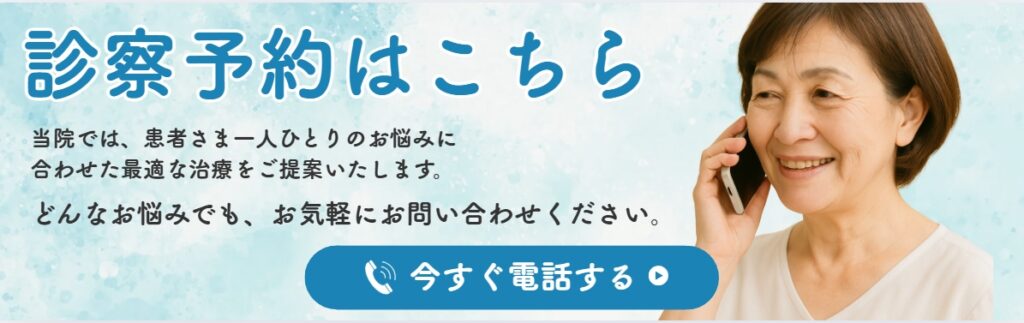首の付け根が痛い原因は?症状の特徴や効果が期待できる改善法を解説
「なんだか首の付け根がズキズキ痛む」「パソコン作業で首から肩が重い」と、つらい症状に悩んでいませんか?
首の付け根の痛みは、単なる筋肉疲労だけでなく、ストレートネックや神経の圧迫、さらには心臓や血管の病気が原因になっている場合もあります。放置すれば、しびれや頭痛、めまいといった深刻な症状につながることもあるのです。
この記事では、首の付け根が痛む原因をわかりやすく整理し、危険なサインの見分け方、自宅でできるセルフケア、医療機関で行われる治療法までを網羅的に解説します。「ただの疲れ」と軽く見ずに、正しい知識を身につけて、つらい痛みから解放される第一歩を踏み出しましょう。
当院では、頚椎椎間板ヘルニアをはじめとした整形外科疾患に対し、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。不安な症状がある方も安心してご相談いただけるよう、以下の記事で診察の流れや受付方法を詳しくまとめています。
>>診察のご案内について

記事監修:川口 慎治
大室整形外科 脊椎・関節クリニック 医師
経歴:
徳島大学医学部卒業後、洛和会音羽病院に勤務
京都大学医学部整形外科学教室入局
学研都市病院脊椎脊髄センター勤務
2023年より 大室整形外科 脊椎・関節クリニック勤務
専門分野:脊椎・脊髄外科
資格:
日本専門医機構認定 整形外科専門医
日本整形外科学会認定 脊椎脊髄病医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科指導医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科専門医
首の付け根が痛む原因と症状の特徴
首の付け根が痛む原因と症状の特徴について、以下の4つを解説します。
- ストレートネック(デスクワークやスマホ長時間利用)
- 筋肉の緊張(肩こり・ストレス)
- 神経圧迫による痛み(頚椎症・頚椎椎間板ヘルニア)
- 急性外傷(寝違え・むちうち)
ストレートネック(デスクワークやスマホ長時間利用)
ストレートネックとは、首の自然なカーブが失われて真っ直ぐになり、首の付け根に大きな負担がかかる状態です。現代のデスクワークやスマホ利用に深く関係しています。
私たちの頭はボーリング球ほどの重さ(約4〜6kg)があり、本来は首の骨(頚椎)のゆるやかなカーブがその重さを分散しています。うつむいた姿勢を長時間続けるとこのカーブが失われ、首がまっすぐになってしまいます。結果、頭の重さが一点に集中し、首や肩の筋肉が常に緊張して血行も悪くなります。
こうした状態が続くと、慢性的な首こりや痛み、頭痛の原因となります。ストレートネックになりやすい生活習慣は以下のとおりです。
- パソコンやスマホの利用:1日に3時間以上、うつむいて画面を見ている
- 作業中の姿勢:気づくと猫背になり、あごが前に突き出ている
- 普段の癖:いつも同じ側の肩にカバンをかけたり、脚を組んだりする
- 使っている枕:枕が高すぎる、または低すぎて首が安定しない
- 運動習慣:体を動かす習慣があまりなく、筋肉が凝り固まっている
日常生活で姿勢や習慣を意識することが、ストレートネックの予防・改善につながります。
以下の記事では、頚椎椎間板ヘルニアにおける痛みを和らげるための具体的な対処法や、日常生活で注意すべきポイントを紹介しています。首まわりの症状に悩んでいる方はぜひご覧ください。
>>頚椎椎間板ヘルニアの痛みを和らげる方法!効果が期待できる対処法と注意点
筋肉の緊張(肩こり・ストレス)
首の付け根の痛みは、多くの場合「肩こり」が悪化して起こります。首から肩、背中にかけて筋肉がつながっているため、肩の緊張が首の痛みにもつながるのです。
筋肉の緊張が起こる主な理由は次の2つです。
- 同じ姿勢や運動不足:血流が悪くなり疲労物質が溜まる
- 精神的ストレス:自律神経が乱れ血管が収縮し血行不良になる
このように、体の使い方と心の状態の両面が首や肩のこりに影響します。特にストレスや睡眠不足、不規則な生活は緊張を強める要因です。日常的にリラックスを意識し、生活習慣を整えることが大切です。
神経圧迫による痛み(頚椎症・頚椎椎間板ヘルニア)
首の付け根の痛みに加えて、腕や手にしびれや力の入りにくさがある場合は、首の神経が圧迫されている可能性があります。代表的な病気は次の2つです。
- 頚椎症:加齢や生活習慣で骨や椎間板が変形し、骨棘が神経を圧迫する
- 頚椎椎間板ヘルニア:椎間板の中身が飛び出し、神経を圧迫する
これらの病気では、首の付け根だけでなく肩甲骨まわり、腕、指先にまで痛みやしびれが広がるのが特徴です。「ボタンがかけにくい」「箸が使いにくい」といった細かい動作の障害も注意サインです。
首の痛みは、首だけの問題ではなく体全体のバランスとも関係しています。最近の研究では、首の治療に加えて腰も一緒に整えると、痛みや動きの改善がより大きいことが報告されています。
以下の記事では、首の神経が圧迫されることで起こる頚椎椎間板ヘルニアの原因や症状、治療法まで詳しく解説しています。肩や腕に広がる痛みの対処法を知りたい方におすすめです。
>>【首や肩の痛みは要注意】頚椎椎間板ヘルニアの症状・原因・治療法を解説
急性外傷(寝違え・むちうち)
突然の激痛で首が動かせなくなる場合、筋肉や靭帯を傷つける「急性外傷」が原因です。代表的なのは「寝違え」と「むちうち」です。それぞれの原因や症状、特徴を表にまとめています。
| 種類 | 原因 | 主な症状 | 特徴・注意点 |
| 寝違え(急性疼痛性頸部拘縮) | ・睡眠中の不自然な姿勢 ・合わない寝具 |
・首の付け根から肩にかけての強い痛み ・動かせない |
・筋肉の炎症や軽い肉離れ ・安静で数日〜1週間で改善 |
| むちうち(外傷性頚部症候群) | 交通事故やスポーツでの衝突 | 首の痛みのほか多様な症状 | 症状は遅れて出ることもあり、受診が必須 |
むちうちでは、首の痛みに加えて次のような症状が現れることがあります。
- 頭痛、めまい、吐き気
- 耳鳴り
- 腕や手のしびれ
- 全身のだるさ、集中力の低下
むちうちは事故直後に症状がなくても、数日経ってから出る場合があります。軽いと思って放置すると悪化や後遺症につながるため、必ず医療機関で正しい診断を受けてください。
危険な症状の見分け方(内臓や血管の病気)
首の付け根の痛みの多くは筋肉や骨の問題によるものですが、まれに内臓や血管の病気が隠れていることがあります。「いつものこりとは違う」と感じたら注意が必要です。以下のような症状が1つでも当てはまる場合は、命に関わる病気の可能性があるため、すぐに医療機関を受診してください。
| 症状の特徴 | 考えられる病気 |
| ・突然の激しい頭痛 ・急なめまい、ふらつき、物が二重に見える ・ろれつが回らない、言葉が出にくい |
脳の血管の病気(椎骨動脈解離など) |
| ・胸が締め付けられるような痛み ・左肩や腕、あごへ痛みが広がる ・息苦しさ、冷や汗を伴う |
心臓の病気(狭心症、心筋梗塞など) |
| ・急に手足に力が入らない ・箸が持てない ・字が書けない ・歩きにくい |
脳や脊髄の神経の病気 |
| ・38度以上の高熱 ・首が硬くあごを胸につけられない ・吐き気や嘔吐を繰り返す |
感染症(髄膜炎など) |
| ・首の付け根にしこりがある ・理由がないのに体重が減り続ける |
腫瘍 |
心臓の病気による首の痛みは「放散痛」と呼ばれ、心臓の異常が首や肩に間違って伝わる現象です。高熱と首の硬直を伴う場合は髄膜炎が疑われ、放置すると命に関わることもあります。
「いつもと違う」「様子がおかしい」と感じた直感は大切です。夜間や休日であっても自己判断せず、救急外来を受診し、必要なら迷わず救急車を呼んでください。
自宅でできる首の付け根の痛み対策
首の痛みの原因は、実は日常生活の中に隠れていることがほとんどです。そのため、ご自宅でのセルフケアは症状を和らげ、再発を防ぐために大切です。自宅でできる首の付け根の痛み対策として、以下の5つを解説します。
- 症状別の応急処置(温熱・冷却療法)
- 正しい姿勢
- ストレッチ
- 枕の選び方
- 睡眠姿勢
- 市販の湿布・鎮痛薬
症状別の応急処置(温熱・冷却療法)
痛みの種類に応じて「温める」か「冷やす」かを選ぶことが重要です。症状やおすすめの対処法はそれぞれ以下の表にまとめています。
| 症状の種類 | おすすめの対処法 | 処置の目的 |
| 慢性的な痛み(重だるさ、じわじわ痛む) | 温める(温熱療法) | 血行を良くして、筋肉の緊張をほぐす |
| 急性の痛み(ズキズキ痛む、熱感がある) | 冷やす(冷却療法) | 炎症を鎮めて、痛みを和らげる |
正しい姿勢
首の痛みを予防・改善するためには、日常生活における姿勢の見直しが不可欠です。頭は約4〜6kgと重く、首を30度傾けるだけで約18kgの負荷がかかるため、無意識の前傾姿勢が首に大きな負担を与えます。パソコン作業やスマートフォン使用時には、以下のポイントを意識して正しい姿勢を保ちましょう。
| チェック項目 | 正しい姿勢・調整ポイント | 注意点 |
| 画面の高さ | パソコン画面の上端が目線の高さ〜やや下になるように調整 | 画面が低すぎると頭が前に出て猫背に |
| 椅子の座り方 | お尻を背もたれにつけて深く腰かけ、骨盤を立てる意識で座る | 浅く座ると背中が丸まり首に負担がかかる |
| 足の位置 | 足裏全体が床につくように椅子の高さを調整 | 足が浮いていると体に余計な力が入る |
| 肘の角度 | 肘が90度前後になるように机と椅子の高さを調整 | 肩が上がると首・肩の緊張につながる |
スマートフォンを使う際は、下を向いて操作せず、スマホを目線の高さまで持ち上げて使いましょう。難しい場合は、30分に1回は休憩をとり、首や肩を回して緊張をほぐすことを心がけてください。
ストレッチ
首の付け根の痛みに効果が期待できるストレッチとして、以下の3つを表にまとめています。
| ストレッチ名 | 手順 | ポイント・注意点 |
| 首の横を伸ばすストレッチ | 1.楽な姿勢で座り、背筋を伸ばす 2.右手を頭の左側に置き、ゆっくり右に倒す 3.左の首筋が伸びるのを感じながら20秒キープ 4.ゆっくり戻し、反対側も同様に行う |
・反動をつけず、ゆっくり倒す ・呼吸を止めないよう意識 |
| 胸を開くストレッチ(猫背改善) | 1.椅子の後ろで両手を組む 2.息を吸いながら胸を張り、組んだ手を斜め下に引き下げる 3.肩甲骨を中央に寄せながら20秒キープ |
・胸を開くイメージで ・肩がすくまないよう注意 |
| 肩甲骨を回すストレッチ | 1.両肘を曲げて指先を肩につける 2.肘で大きな円を描くように、前回し・後ろ回しを各10回行う |
・肩甲骨から大きく動かすとより効果が期待できる ・首や肩に力を入れすぎない |
ストレッチを行ううえで、以下のルールを守りましょう。
- 痛みを感じない、心地よい範囲で行う
- 反動をつけず、ゆっくりと筋肉を伸ばす
- 呼吸を止めず、自然な呼吸を意識する
無理に行うと、かえって筋肉を傷めてしまうので注意してください。
枕の選び方
枕は「高さ・硬さ・大きさ」の3点を基準に選ぶことが大切です。高さは、仰向けでは首とマットレスの隙間を自然に埋め、首のカーブを保てるものが理想で、額が顎より少し高くなる程度が目安です。横向きでは、首から背骨までがまっすぐになる高さが適切で、肩幅を考慮して仰向け用よりやや高めの枕が必要です。
硬さは、柔らかすぎて沈み込むものや、硬すぎて首が浮いてしまうものは避けましょう。頭をしっかり支えながら寝返りがしやすい、適度な反発力のある枕が望ましいです。
大きさについては、寝返りをしても頭が枕から落ちないよう、十分な幅と奥行きのあるものを選びましょう。
睡眠姿勢
1日の約3分の1を占める睡眠時間は、体を回復させる大切な時間です。首に負担の少ない睡眠姿勢のポイントを以下にまとめています。枕選びのチェックリストは以下のとおりです。
| 寝姿勢 | 特徴とポイント |
| 仰向け | ・最も首にやさしい姿勢 ・膝下にクッションや丸めたタオルを入れると腰への負担も軽減される |
| 横向き | ・枕の高さが重要 ・体の軸を保つために抱き枕を使うと安定感が増し、肩・腰の負担を軽減できる |
| うつ伏せ | ・首を大きくひねる姿勢となり、首や肩に強い負担がかかるためできるだけ避ける |
市販の湿布・鎮痛薬
市販薬は一時的に痛みを和らげる対症療法であり、根本的な治療にはなりません。正しい使い方を理解し、症状が改善しない場合は自己判断を避けて医療機関を受診しましょう。
| 種類 | 特徴・効果 | 注意点 |
| 冷湿布 | ・清涼感がある ・急性の痛み(寝違え、捻挫など)や熱感、炎症のある部位に適している |
特になし(急性症状には基本的に適応) |
| 温湿布 | ・じんわり温かい ・慢性的なこりや血行不良による痛みに効果が期待できる ・筋肉をほぐしてリラックス効果が期待できる |
炎症がある部位には使用を避ける(悪化する可能性あり) |
| 痛み止め成分入り湿布 | ・NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)配合 ・炎症や痛みの原因物質の生成を抑える効果がある |
成分によって皮膚がかぶれることがあるため、長時間の使用は控えること |
| 飲み薬(鎮痛薬) | ・痛みが強い場合に日常生活への支障を軽減する目的で使用される ・多くはNSAIDsを含む |
・胃腸に負担があるため空腹時は避ける ・添付文書を必ず確認する ・1〜2週間で改善しなければ医療機関を受診する |
市販薬は、一時的な痛みの緩和につながる可能性があります。しかし、根本治療ではないため、1〜2週間ほど使用しても症状が長引く場合は必ず整形外科などを受診してください。
病院で行う治療法
当院、大室整形外科の治療の基本は、手術をしない方法です。これを「保存療法」と呼び、体への負担が少ないのが特徴です。ほとんどの場合、この保存療法で症状は良くなっていきます。一般的に、病院で行う治療法は以下の3つです。
- 保存療法(薬物・リハビリテーション・物理療法)
- ブロック注射
- 手術
保存療法(薬物・リハビリテーション・物理療法)
保存療法とは、手術を行わずに痛みを和らげ、体の機能を回復させる治療法です。首の付け根の痛みに対しても、まずはこの方法から始めるのが一般的で、体への負担が少ないのが特徴です。
薬物療法では、炎症や痛みを抑えるNSAIDsや、筋肉の緊張を和らげる筋弛緩薬を使用し、湿布や塗り薬も患部に直接作用します。リハビリテーションは、理学療法士がストレッチや筋力強化、姿勢改善を指導し、温熱・電気・牽引などの物理療法も併用します。
腰のリハビリを並行して行うことで痛みが改善するケースもあり、全身のバランスを整える視点が重要です。
ブロック注射
飲み薬やリハビリテーションを続けても、なかなか痛みが引かない場合に対して行う治療法で、神経や筋肉に直接薬を注射し、痛みの伝達を遮断します。即効性があり、つらい痛みの悪循環を断ち切ることが期待されます。
期待される効果は主に以下の3つです。
- 神経に直接作用し、飲み薬より早く痛みを軽減する
- 筋肉の緊張がゆるみ、血流が改善する
- 痛みが和らぐことで、リハビリに取り組みやすくなる
主な方法には、筋肉のしこりに打つ「トリガーポイント注射」と、神経の近くに打つ「神経ブロック注射」があり、症状や原因に応じて医師が最適な方法を選びます。
手術
保存療法やブロック注射で改善が見られず、しびれや麻痺が進行する場合は、神経の圧迫を取り除くための手術が検討されます。手術は大きな決断だからこそ、患者さんの生活や希望を踏まえて慎重に判断されます。手術を検討する具体的なサインとして、以下が挙げられます。
- 腕や足に力が入らず、歩きにくさを感じる
- お箸がうまく使えない、シャツのボタンが留めにくい
- 字がうまく書けないなど、指先の細かい作業が難しい
- 痛みが激しく、仕事や家事など日常生活を送ることができない
- 保存療法を3か月以上続けても、ほとんど効果が見られない
手術は、麻痺の進行を食い止め、痛みのない生活を取り戻すための重要な治療法です。医師から手術のメリットだけでなく、リスクについても説明を受けましょう。
以下の記事では、頚椎椎間板ヘルニアで仕事を休む必要があるかどうか、手術後の休養期間や復職の目安などを詳しく解説しています。治療と仕事の両立に不安がある方は、ぜひご参考ください。
>>頚椎椎間板ヘルニアで仕事は休める?手術後の休む期間や職場復帰のタイミングを解説
まとめ
多くの痛みは、デスクワークやスマホの長時間利用による姿勢の乱れなど、日々の生活習慣に原因が隠れています。まずは正しい姿勢を意識したり、簡単なストレッチを取り入れたりすることから始めましょう。
痛みが長引く場合や、腕や手のしびれといった「いつもと違う」症状を感じたときは、自己判断で放置しないでください。それは体からの大切なサインかもしれません。
つらい痛みを我慢せず、早めに整形外科などの専門家に相談して、原因に合った適切なケアを受け、快適な毎日を取り戻しましょう。
当院の受診をご希望の方は、まずはお電話にてご予約ください。詳しいアクセス方法は、当院の公式サイトをご覧ください。
>>大室整形外科へのアクセスはこちら
参考文献
Ozdincler A, Aktas D, Reyhanioglu DA, Ozturk B. The effect of neck mobilization Vs. combined neck and lumbar mobilization on pain and range of motion in people with cervical disc herniation: A randomized controlled study. J Bodyw Mov Ther, 2025, 43, p.188-195.