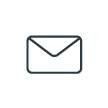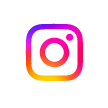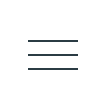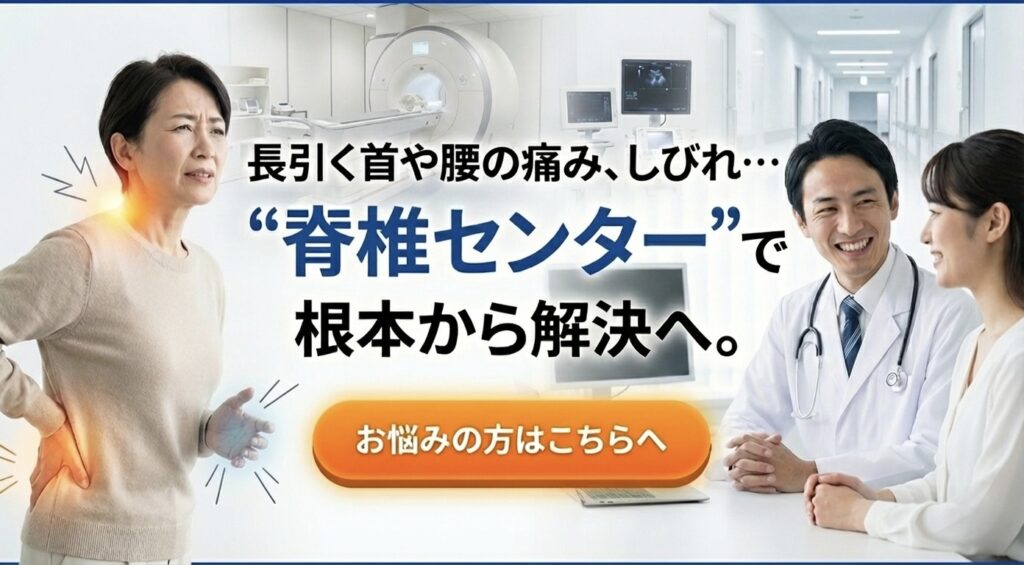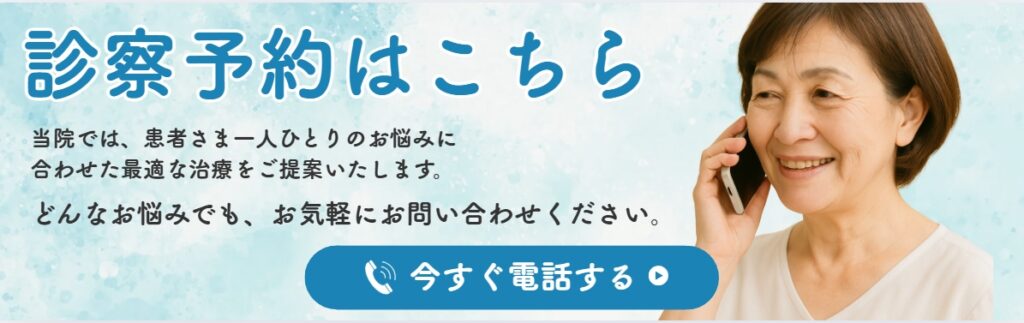首筋が痛いときの原因と対処法!放置すると危険な症状も解説
「朝起きたら首が痛くて動かせない」「デスクワークの後、首筋が重い」、そんな経験はありませんか?
首の痛みは単なる筋肉のこりだけでなく、骨や神経の病気、さらには心筋梗塞など重大な病気のサインであることもあります。首は約5kgの頭を支え続けており、日常生活の中で想像以上の負担を受けています。
この記事では、首の痛みを引き起こす原因や放置すると危険な症状、温めるべきか冷やすべきかの判断基準、再発を防ぐセルフケアまで解説します。正しい知識を身につけることで、つらい痛みを和らげ、安心して日常を過ごすためのヒントが得られます。
当院では、頚椎椎間板ヘルニアをはじめとした整形外科疾患に対し、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。不安な症状がある方も安心してご相談いただけるよう、以下の記事で診察の流れや受付方法を詳しくまとめています。
>>診察のご案内について

記事監修:川口 慎治
大室整形外科 脊椎・関節クリニック 医師
経歴:
徳島大学医学部卒業後、洛和会音羽病院に勤務
京都大学医学部整形外科学教室入局
学研都市病院脊椎脊髄センター勤務
2023年より 大室整形外科 脊椎・関節クリニック勤務
専門分野:脊椎・脊髄外科
資格:
日本専門医機構認定 整形外科専門医
日本整形外科学会認定 脊椎脊髄病医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科指導医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科専門医
首筋の痛みを引き起こす主な原因
首筋の痛みを引き起こす主な原因は、以下のとおりです。
- 日常生活での筋肉緊張(デスクワーク・スマホ首・猫背)
- 睡眠時のトラブル(寝違え・枕の高さや硬さ)
- 頚椎椎間板ヘルニアや変形性頚椎症
- 外傷やスポーツによる首のケガ(むちうち)
- ストレスや自律神経の乱れ
- 心筋梗塞・髄膜炎など
日常生活での筋肉緊張(デスクワーク・スマホ首・猫背)
首は約5kgある頭を支えており、正しい姿勢では首の骨(頚椎)が自然なカーブを描き、重さを効率的に分散しています。しかし、日常生活の悪い姿勢がこのバランスを崩し、筋肉の過緊張や血行不良を引き起こします。主な原因と影響は以下のとおりです。
| 姿勢・習慣 | 首への影響 | 結果 |
| デスクワーク・PC作業 | 前かがみ姿勢で頭が体の中心より前に出る | 首〜肩〜背中に大きな負担 |
| スマホ首(ストレートネック) | 下を向く角度が深いほど首への負担増大 | 頚椎のカーブが消失し、慢性のコリや痛みにつながる |
| 猫背 | 背中が丸まり頭が前に出やすい | 首・肩の筋肉に余計な負担がかかり、慢性痛につながる |
これらの筋肉の緊張やコリは、慢性化しやすいのが特徴です。放置すると、頭痛や吐き気、めまいなどを伴うこともあります。
睡眠時のトラブル(寝違え・枕の高さや硬さ)
朝起きたときに首を動かせなくなる「寝違え」は、医学的に急性疼痛性頸部拘縮と呼ばれます。睡眠中の不自然な姿勢や合わない枕が原因で、首の筋肉や靭帯に負担がかかり炎症を起こすものです。枕の高さや硬さが合わないと、以下のようなトラブルにつながります。
- 高すぎる枕:首が前に曲がり筋肉が伸ばされ続け、首の緊張やいびきにつながる
- 低すぎる枕:首が縮こまり血流が悪化することで、首のこりや違和感につながる
- 硬すぎる/柔らかすぎる枕:頭を支えられず不安定になり、慢性痛につながる
理想の枕は、仰向け時に自然なS字カーブを保てる高さ、横向き時に首と背骨がまっすぐになる高さが目安です。硬さは適度に反発があり、頭が沈みすぎないものが望ましいです。
頚椎椎間板ヘルニアや変形性頚椎症
首の痛みに加えて腕や手のしびれ・痛みがある場合、筋肉の問題ではなく神経や骨の病気が原因の可能性があります。代表的なものが「頚椎椎間板ヘルニア」と「変形性頚椎症」です。それぞれの特徴と症状を以下の表にまとめています。
| 疾患名 | 特徴 | 主な症状 |
| 頚椎椎間板ヘルニア | ・椎間板が飛び出して神経を圧迫する病気 ・30~50代の比較的若い世代にも起こりやすい |
・首~腕・指先の痛みやしびれ ・腕や手の筋力低下 ・ボタンがかけにくいなど細かい作業が困難 |
| 変形性頚椎症 | 加齢や長年の姿勢不良により椎間板がすり減り、骨がトゲ状に変形(骨棘)して神経を圧迫 | ・首や肩のこり、首を動かすと痛む ・腕や手のしびれや筋力低下 ・症状がゆっくり進行することが多い |
これらの症状がある場合、自己判断でマッサージを行うと神経圧迫を悪化させる恐れがあります。必ず整形外科を受診し、レントゲンやMRIで正確な診断を受けることが大切です。
最近の研究では、首の痛みは局所の問題だけでなく全身のバランスとも深く関係していることが示されています。実際に、首と腰を同時に治療したほうが、痛みや機能障害の改善が有意に大きいと報告されています。
以下の記事では、頚椎椎間板ヘルニアにおける痛みを和らげるための具体的な対処法や、日常生活で注意すべきポイントを紹介しています。首まわりの症状に悩んでいる方はぜひご覧ください。
>>頚椎椎間板ヘルニアの痛みを和らげる方法!効果が期待できる対処法と注意点
外傷やスポーツによる首のケガ(むちうち)
交通事故やラグビー・柔道などのコンタクトスポーツでは、強い衝撃で首を痛めることがあります。その代表例が「むちうち(頚椎捻挫)」です。首が鞭のように大きくしなり、筋肉や靭帯、神経が損傷することで起こります。
むちうちで起こりうる症状として、以下が挙げられます。
- 首・肩・背中の痛みやこり
- 頭痛、めまい、吐き気
- 耳鳴り
- 腕や手のしびれ
- 全身のだるさ、疲労感
むちうちで注意すべき点は、ケガの直後には症状がなくても、数時間〜数日経ってから痛みや不調が現れることです。放置すると、症状が長引いたり、後遺症として残ったりする可能性もあります。症状が軽くても、一度は整形外科などの医療機関で診察を受けましょう。
ストレスや自律神経の乱れ
ケガや骨の異常がなくても首が痛む場合、背景に精神的ストレスや自律神経の乱れが関わっていることがあります。ストレスによる首の痛みの悪循環は、以下の流れで発生します。
- ストレスを感じる
- 交感神経が優位になって血管が収縮し、筋肉がこわばる
- 首や肩の血行が悪くなる
- 筋肉に疲労物質が溜まり、痛みやこりとして感じる
- 痛みがさらなるストレスとなり、筋肉の緊張が悪化する
悪循環に陥ることで、めまいや頭痛、吐き気、不眠といった、首の痛み以外の不調を引き起こすこともあります。症状が続く場合は、我慢せずに専門医へ相談することが大切です。
心筋梗塞・髄膜炎など
首筋の痛みは単なる肩こりや筋肉の緊張ではなく、命に関わる重大な病気のサインである場合があります。特に以下のような症状を伴うときは、放置せずすぐに医療機関を受診してください。
| 疑われる病気 | 特に注意すべき症状 |
| 心筋梗塞・狭心症 | ・胸の締め付け感や圧迫感 ・左首筋や肩、腕、あごへの痛みの広がり(放散痛) ・息苦しさ、冷や汗、吐き気 |
| 髄膜炎 | ・突然の激しい頭痛 ・首が硬直して前に曲げられない ・高熱、嘔吐 |
| 椎骨動脈解離 | ・後頭部から首にかけての突然の激痛 ・「バットで殴られたような」経験のない頭痛 ・めまい、ふらつき、ろれつ障害 |
上記の病気による首の痛みは、一般的な肩こりとは明らかに異なります。「いつもと違う」と感じたときは危険信号です。ためらわずに救急車を呼ぶか、速やかに受診しましょう。
放置すると危険な首筋の痛みのサイン
放置すると危険な首筋の痛みのサインは以下のとおりです。
- 腕や手のしびれ・筋力低下
- めまい・吐き気・激しい頭痛
- 胸痛・息苦しさ(心臓病の可能性)
腕や手のしびれ・筋力低下
首の痛みに加えて腕や手にしびれや力が入らない感覚がある場合、首の神経が圧迫されている危険なサインです。放置すると麻痺が進行し、回復が難しくなることもあります。考えられる主な病気は以下の2つです。
- 頚椎椎間板ヘルニア:椎間板が飛び出し、神経を圧迫する
- 変形性頚椎症:加齢などで骨が変形し、神経の通り道を狭める
神経圧迫の危険度セルフチェックとして、以下の項目に当てはまる場合は要注意です。
- 腕から指先にかけて、電気が走るような痛みやしびれがある
- 箸がうまく使えない、字が震えて書きにくい
- シャツのボタンを留めるなど、細かい指先の動きが難しい
- 腕の力が弱くなり、持っている物を頻繁に落とす
- 歩くと足がもつれる感じがする、階段の上り下りが怖い
これらの症状は神経障害が進行しているサインです。自己判断でマッサージなどをせず、できるだけ早く整形外科、特に脊椎専門の医療機関を受診してください。
めまい・吐き気・激しい頭痛
首筋の痛みに加えてめまい・吐き気・激しい頭痛がある場合、脳や血管の異常を知らせる緊急サインかもしれません。単なる首こりが原因の「頚性めまい」とは異なり、命に関わる病気の可能性を考える必要があります。考えられる危険な病気は以下のとおりです。
| 疑われる病気 | 主な特徴 |
| 椎骨動脈解離 | ・脳へ血液を送る椎骨動脈が裂ける病気 ・後頭部〜首筋にかけて「バットで殴られたような」突然の激痛が起こる ・脳梗塞やくも膜下出血を引き起こす危険あり |
| 髄膜炎 | ・脳を覆う膜に感染が起こる病気 ・激しい頭痛と高熱、嘔吐を伴い、首が硬直して前に曲げられなくなる。 |
ただちに救急受診を考えるべき症状は以下のとおりです。
- 突然始まった、立っていられないほどの激しい頭痛
- 首の痛みと同時に、高熱や嘔吐がある
- めまいやふらつきがひどく、まっすぐ歩けない
- ろれつが回らない、物が二重に見える、顔の片方がゆがむ
これらは一刻を争う危険な症状です。「少し様子を見る」という選択は絶対にせず、すぐに救急車を呼ぶか、脳神経外科などの救急外来を受診してください。
胸痛・息苦しさ(心臓病の可能性)
首の痛みに胸痛や息苦しさを伴う場合は、心臓病のサインである可能性があります。これは「放散痛」と呼ばれ、心臓の異常が首や肩の痛みとして現れる現象です。特に痛みが左の首から肩や腕に広がり、胸の圧迫感や息苦しさを伴う場合は注意が必要です。
こうした症状は整形外科ではなく循環器内科や救急外来の対応が必要になるため、ためらわずに医療機関を受診してください。
自宅での応急処置:温める・冷やすの判断基準
首の痛みは、発症からの経過と痛みのタイプによって適切な対処法が変わります。誤った対応は悪化につながるため注意が必要です。
痛みが出てすぐ(1〜2日程度)は「冷やす」のが基本です。首の筋肉や靭帯に炎症が起きているため、冷却で炎症の広がりを抑えます。冷やすべき典型的なケースは次のとおりです。
- 寝違えて強い痛みがある
- ズキズキ脈打つように痛む
- 腫れや熱感がある
- スポーツ直後の痛み
一方、痛みが3日以上続く場合は「温める」ことが有効です。血行を促し筋肉のこりをほぐすことで、痛みが和らぎます。温めると良いケースは次のとおりです。
- デスクワークによる慢性的なこり
- 鈍い痛みが長引いている
- 首や肩が冷えて血行不良を感じる
まとめると、痛みのタイプに応じた対処は以下のとおりです。
| 痛みのタイプ | 対処法 | 目的 |
| 急な激痛・熱感(発症〜2日程度) | 冷やす | 炎症を抑える |
| 長引く鈍痛・こり(3日以降) | 温める | 血行を良くする |
判断に迷う場合や、しびれなど他の症状を伴うときは、自己判断せず整形外科を受診してください。
再発予防のセルフケア
再発予防のセルフケアとして、以下の4つを解説します。
- ストレッチ
- 姿勢改善
- 枕選び・睡眠姿勢
- 市販薬・湿布の活用
ストレッチ
首や肩の筋肉は、同じ姿勢が続くと硬くなり、血流が悪化して痛みやコリの原因になります。ストレッチは筋肉をゆるめ、柔軟性と血流を保つために効果が期待できます。ただし、強い痛みや腕のしびれがある時に無理に行うのは危険です。「痛気持ちいい」と感じる範囲で、リラックスして行うことを心がけましょう。
首の後ろを伸ばすストレッチは以下の手順で行います。
- 椅子に深く座り、背筋をまっすぐにする
- 両手を頭の後ろで組み、腕の重みを使ってゆっくりと頭を前に倒す
- 無理に引っ張らず、首の後ろがじっくり伸びるのを感じながら20秒キープする
首の横を伸ばすストレッチは以下の手順で行います。
- 右手で頭の左側を持ち、ゆっくりと真横に倒す
- 左肩が上がらないよう、左手で椅子の座面を持つ
- 左の首筋が心地よく伸びるのを感じながら20秒キープする
- 反対側も同様に行う
胸を開き、肩甲骨を寄せるストレッチは以下の手順です。
- 体の後ろで両手を組む
- 左右の肩甲骨を背骨に引き寄せるイメージで、胸をぐーっと張る
- 猫背で縮こまった胸の筋肉が伸びるのを感じる
上記のストレッチは、デスクワークの合間に特におすすめです。デスクワークやスマホの操作中は、1時間に1回は休憩を挟むのが理想です。タイマーをセットするなどして、意識的に体を動かす習慣をつけましょう。
以下の記事では、頚椎椎間板ヘルニアを発症した場合に仕事を休むべきかどうか、また手術後の休養期間や職場復帰のタイミングを詳しく解説しています。
>>頚椎椎間板ヘルニアで仕事は休める?手術後の休む期間や職場復帰のタイミングを解説
姿勢改善
日常の何気ない姿勢が、首への負担を大きくしています。特に猫背やうつむき姿勢は、約5kgある頭を首だけで支えることになり、慢性的な痛みにつながります。正しい姿勢を意識することが、首の健康を守る基本です。正しい姿勢のセルフチェックポイントを以下の表にまとめています。
| シーン | チェックポイント |
| 座っているとき | ・椅子に深く腰掛け、お尻の骨(坐骨)で座る意識を持つ ・パソコンのモニターは、目線がわずかに下がる高さに調整する ・あごを軽く引き、耳の穴が肩の真上に来るように意識する ・足の裏全体が、しっかりと床についているか確認する |
| 立っているとき | ・壁を背にして立ち、後頭部・肩甲骨・お尻・かかとが壁につくか確認する ・耳、肩、腰、ひざ、くるぶしが一直線になるように立つ |
| スマホを見るとき | ・首を傾けず、スマホを顔の高さに持ち上げる ・うつむく角度をできるだけ小さくする |
最初は窮屈に感じても、体にとって自然で負担の少ない姿勢です。
以下の記事では、首の神経が圧迫されることで起こる頸椎椎間板ヘルニアの原因や症状、治療法まで詳しく解説しています。肩や腕に広がる痛みの対処法を知りたい方におすすめです。
>>【首や肩の痛みは要注意】頸椎椎間板ヘルニアの症状・原因・治療法を解説
枕選び・睡眠姿勢
体に合わない枕は、睡眠中に首の骨(頚椎)を不自然に歪ませ、朝の痛みや寝違えの原因となります。人生の3分の1を占める睡眠時間だからこそ、首を守る正しい枕選びが重要です。首を守る枕選びの3つのポイントを以下の表にまとめています。
| 項目 | ポイント |
| 高さ | ・仰向け:首とマットレスの隙間を埋め、顔が軽く下を向く(約5度)が理想 ・横向き:肩の厚みに合わせ、首から背骨までが一直線になる高さ |
| 硬さ | ・柔らかすぎると頭が沈み寝返りが打ちにくい ・硬すぎると首が浮いて負担になる →適度な反発力で首と頭を支えるものが最適 |
| 素材・形状 | ・十分な横幅で寝返りしても頭が落ちない ・通気性が良く、首の自然なカーブにフィットする設計がおすすめ |
うつ伏せ寝は首を大きくひねった状態が続くため負担が大きくなります。仰向けか横向きで眠る習慣を心がけましょう。
市販薬・湿布の活用
急な首の痛みでつらいとき、市販薬や湿布は一時的に症状を和らげる方法です。ただし、根本治療ではなく「対症療法」であることを理解しておきましょう。飲み薬(ロキソプロフェンやイブプロフェンなど)は炎症を抑えますが、胃に負担をかけるため食後に服用しましょう。
湿布には炎症を冷やす「冷湿布」と、血流を促し筋肉をほぐす「温湿布」があり、症状の経過に応じて使い分けます。使用にあたっては必ず用法・用量を守り、皮膚に異常が出たら中止してください。2週間以上使っても改善しない、または悪化する場合は、自己判断を避け速やかに整形外科を受診することが大切です。
当院の受診をご希望の方は、まずはお電話にてご予約ください。詳しいアクセス方法は、当院の公式サイトをご覧ください。
>>大室整形外科へのアクセスはこちら
まとめ
単なるコリと軽く考えがちな首の痛みですが、日常生活の癖だけでなく、神経の病気や命に関わる重大な病気が隠れている可能性もあります。まずは、姿勢の改善やストレッチといったセルフケアを日々の生活に取り入れ、痛みを予防することが大切です。
痛みが長引いたり、腕のしびれや激しい頭痛など「いつもと違う」危険なサインを感じたりした場合は、決して自己判断で放置しないでください。少しでも不安があれば、我慢せずに専門の医療機関へ相談しましょう。専門家による適切な診断と治療が、つらい痛みから解放される一番の近道です。
一人で抱え込まず、まずは専門の医師にあなたの不安や希望を遠慮なく相談しましょう。当院の受診をご希望の方は、まずはお電話にてご予約ください。
参考文献
Ozdincler A, Aktas D, Reyhanioglu DA, Ozturk B. The effect of neck mobilization Vs. combined neck and lumbar mobilization on pain and range of motion in people with cervical disc herniation: A randomized controlled study. J Bodyw Mov Ther, 2025, 43, p.188-195.