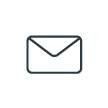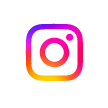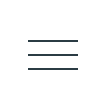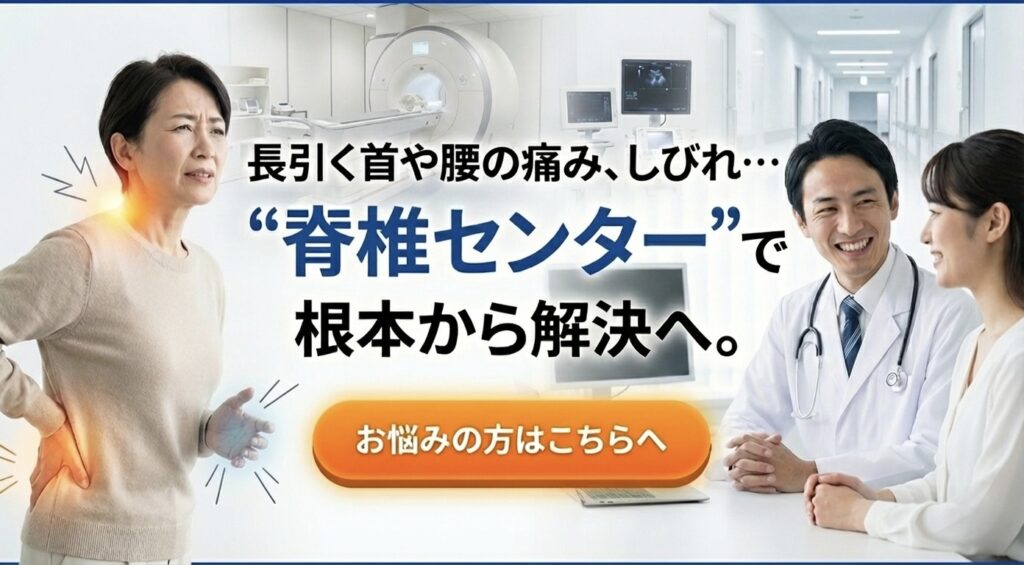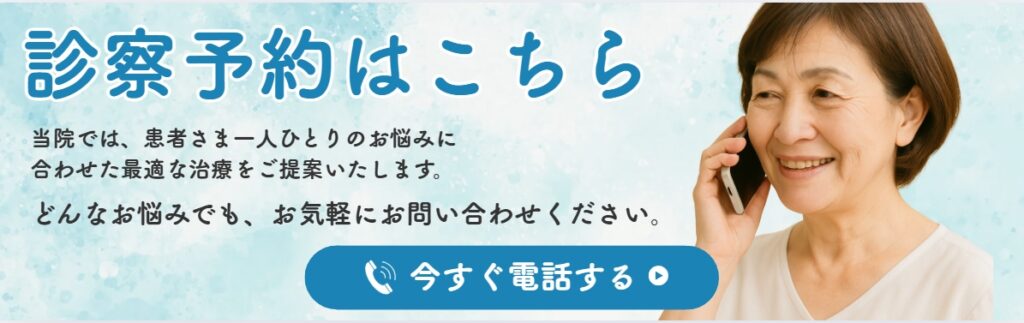腰部脊柱管狭窄症の症状とは?痛くなる原因やしびれの特徴、治療法まで解説
「5分歩くと足が痛くてしびれる、少し前かがみで休むとまた歩ける」、それは「腰部脊柱管狭窄症」のサインの可能性があります。単なる腰痛や年のせいだと諦めている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、腰部脊柱管狭窄症の症状や原因、診断の流れを解説します。薬やリハビリテーション、体への負担が少ない手術まで、治療の選択肢もご紹介します。放置すれば歩行困難につながる可能性もあるため、症状への正しい理解が大切です。この記事を読み、つらい痛みやしびれを乗り越えるための知識を手に入れてください。
当院では、腰部脊柱管狭窄症をはじめとした整形外科疾患に対し、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。不安な症状がある方も安心してご相談いただけるよう、以下の記事で診察の流れや受付方法を詳しくまとめています。
>>診察のご案内について

記事監修:川口 慎治
大室整形外科 脊椎・関節クリニック 医師
経歴:
徳島大学医学部卒業後、洛和会音羽病院に勤務
京都大学医学部整形外科学教室入局
学研都市病院脊椎脊髄センター勤務
2023年より 大室整形外科 脊椎・関節クリニック勤務
専門分野:脊椎・脊髄外科
資格:
日本専門医機構認定 整形外科専門医
日本整形外科学会認定 脊椎脊髄病医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科指導医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科専門医
腰部脊柱管狭窄症の主な症状5つ
腰部脊柱管狭窄症の主な症状は、以下のとおりです。
- 足の痛みとしびれ(間欠性跛行)
- 坐骨神経痛
- 筋力低下
- 背筋を伸ばしたときに強くなる腰の痛み
- 重症化のサイン:排尿・排便の異常(馬尾症候群)
足の痛みとしびれ(間欠性跛行)
「歩き始めは平気なのに、数分歩くと足がしびれて前に進めない」、これは腰部脊柱管狭窄症に特徴的な症状です。間欠性跛行(かんけつせいはこう)と呼ばれます。主な症状の特徴は以下のとおりです。
- 歩き続けると太もも〜足先に痛みやしびれが出る
- 足に力が入らなくなり、脱力感を伴うことがある
- 前かがみになると症状がやわらぎ、再び歩けるようになる
- 坂道を下ると悪化しやすい
間欠性跛行は神経への血流不足による症状です。症状の出方に波があるため、進行していても気づきにくい場合があります。放置せず、症状が続くようであれば専門医に相談することをおすすめします。
坐骨神経痛
お尻から太ももの裏、ふくらはぎ、足先にかけて、痛みやしびれが出る症状を「坐骨神経痛」と呼びます。腰部脊柱管狭窄症では、神経が圧迫されることによりこの症状が引き起こされることがあります。坐骨神経痛の症状は、以下のとおりです。
- 痛み:電気が走るような鋭い痛み、焼けつくような痛み
- 感覚の異常:感覚が鈍くなる、皮膚が厚く感じる、足が冷たい・ほてるように感じる
- 力の入りにくさ:足がもつれる、力が入りづらくなる感覚
安静時は症状がなくても、立ったり歩いたりすると、お尻や足の症状が強くなる傾向があります。腰の痛みはそれほど強くないのに、お尻や足の症状ばかりが目立つというケースもあります。足の症状は生活の質を大きく下げるため、我慢は禁物です。
筋力低下
「最近つまずきやすい」「スリッパが勝手に脱げる」という変化は、腰部脊柱管狭窄症の進行で起こる筋力低下のサインかもしれません。神経の圧迫が長く続くと、脳から足の筋肉への命令が、うまく伝わらなくなり、足に力が入りにくくなる運動障害が生じます。よく見られる筋力低下のサインは以下のとおりです。
| 症状 | 原因・特徴 |
| つまずきやすくなる | 足首を持ち上げる筋肉が弱くなり、すり足気味の歩き方になる |
| 階段の上り下りが怖くなる | 太ももやふくらはぎの筋力が低下し、体を支えにくくなる |
| スリッパや靴が脱げやすい | 足の指を動かす筋肉が弱くなり、踏ん張りがきかなくなる可能性がある |
| しゃがんだ姿勢から立ち上がれない | 下半身全体の筋力が低下し、立ち上がる動作が難しくなる |
筋力の低下は、転倒による骨折のリスクや、日常の行動範囲を狭める大きな要因になります。ご自身の動きに「いつもと違う」と感じたら、体が発する重要なサインです。気になる症状があれば、早めに専門医へ相談することが大切です。
背筋を伸ばしたときに強くなる腰の痛み
腰部脊柱管狭窄症では、足のしびれや痛みに加えて、姿勢によって変化する腰痛が現れることがあります。痛みが強くなる傾向がある姿勢・動作は、以下の場合です。
- 背筋を伸ばして立つとき
- 歩行時に姿勢がまっすぐなとき
- 腰を反らせるような動き
上記の姿勢では、神経の通り道(脊柱管)が狭くなり、神経の圧迫が強まるため痛みが増します。以下のような痛みが和らぎやすい姿勢・動作もあります。
- 椅子に座っているとき
- 腰をかがめた前かがみの姿勢をとったとき
- 自転車をこいでいるとき
「安静時は楽なのに、立ち仕事や歩行中に腰が痛む」という方は、注意が必要です。姿勢によって痛みの強さが変わる場合は、腰部脊柱管狭窄症の可能性があります。気になる症状がある方は、早めの受診をおすすめします。
重症化のサイン:排尿・排便の異常(馬尾症候群)
腰部脊柱管狭窄症が進行し、脊柱管内の神経の束(馬尾神経)が強く圧迫されると、「馬尾(ばび)症候群」という状態になることがあります。緊急手術が必要になることもある重篤な状態です。注意すべき症状の一覧を表にまとめています。
| 症状の分類 | 具体的な異常 |
| 排尿の異常 | ・尿意がわかりにくい、または出にくい(排尿困難) ・頻繁にトイレに行きたくなる(頻尿) ・排尿後に残っている感じがする(残尿感) ・自分の意思に関係なく尿がもれる(尿失禁) |
| 排便の異常 | ・急に便秘がひどくなった ・便が漏れてしまうことがある(便失禁) |
| 会陰部の異常 | お尻や股間(会陰部)の感覚が鈍い、しびれる |
上記の症状に当てはまる場合、神経機能の障害が進行しているサインです。放置すると、神経が回復しにくくなり、排尿・排便障害が後遺症として残る可能性があります。迷わず、専門医を受診してください。
腰部脊柱管狭窄症の原因
腰部脊柱管狭窄症の原因は、主に以下の2つです。
- 加齢による背骨の変形
- 神経圧迫
加齢による背骨の変形
背骨は、体を支える大黒柱のような存在で、骨・軟骨・靭帯などが精密に組み合わさって構成されています。しかし、年齢とともにその構造が変化し、神経の通り道である脊柱管が狭くなることがあります。脊柱管を狭くする主な変化は以下のとおりです。
- 椎間板の膨らみ:クッションの役割をもつ椎間板が硬くなり、後方に飛び出す
- 黄色靭帯の肥厚:背骨をつなぐ靭帯が分厚く硬くなり、内側から脊柱管を狭める
- 椎間関節の変形・骨棘の形成:背骨の関節がすり減り、トゲのような骨(骨棘)ができて神経を圧迫する
上記の変化は、単独で起こるのではなく、複数が同時に・複合的に進行することが一般的です。まれに先天的に脊柱管が狭い方もいますが、ほとんどは加齢による変化の積み重ねによって発症します。
神経圧迫
加齢などによって背骨が変形し、神経の通り道(脊柱管)が狭くなると、神経の束が圧迫されます。この「神経圧迫」こそが、足の痛みやしびれの主な原因です。神経が圧迫されると、以下の表のような神経圧迫による影響が生じます。
| 現象 | 説明 |
| 神経の栄養不足(血流障害) | 1.圧迫により血管もつぶされ、神経への血流が滞る 2.栄養が不足する 3.痛み・しびれが生じる |
| 姿勢による圧迫の変化 | 姿勢によって脊柱管の広さが変わり、圧迫の強さが変化する |
また、姿勢による圧迫の変化については、以下の表にまとめています。
| 姿勢 | 神経への影響 | 症状の傾向 |
| 立つ・歩く | 背筋が伸びることで脊柱管が狭くなり、圧迫が強まる | 症状が悪化しやすい |
| 座る・前かがみ | 脊柱管が少し広がり、圧迫がゆるむ | 症状が楽になることが多い |
さらに、背骨が前後にずれる「腰椎すべり症」や、椎間板が飛び出す「腰椎椎間板ヘルニア」が合併している場合もあります。神経圧迫による症状は、姿勢によって変化するのが特徴です。普段の姿勢や動作に注意しながら、気になる症状があれば早めに受診しましょう。
以下の記事では、椎間板ヘルニアの基本的な原因や症状、整形外科で行われる治療法の流れについて、ポイントをわかりやすく解説しています。
>>椎間板ヘルニアとは?原因・症状・治療法を解説
腰部脊柱管狭窄症の診断の流れ
診断では、いつから・どのような症状があるかを問診で詳しく伺います。続いて、実際の動作や痛みの出方を観察し、病状を把握します。必要に応じて以下の検査を行い、他の病気との見分けも行います。
- 画像検査(レントゲン・MRIなど)
- 他の疾患との鑑別(椎間板ヘルニア、すべり症など)
これらを総合的に判断し、診断を確定します。
画像検査(レントゲン・MRI)
腰部脊柱管狭窄症が疑われる場合、問診や診察だけでなく、背骨や神経の状態を直接「目で確認する」ために画像検査を行います。画像検査によって、症状の原因や重症度をより正確に把握でき、治療方針の決定にも役立ちます。
レントゲンは主に骨の状態を確認するための基本的な検査で、背骨全体のバランスや加齢による骨の変化を把握するのに適しています。MRIは神経や椎間板、靭帯といった軟部組織の状態がわかる、腰部脊柱管狭窄症の診断や手術の判断に欠かせない検査です。
症状の原因を正確に知ることは、適切な治療につながります。検査に不安がある方も、事前に医師に相談しながら進めていくことが大切です。
他の病気との鑑別(椎間板ヘルニア、すべり症など)
足のしびれや痛みは、必ずしも腰部脊柱管狭窄症だけが原因とは限りません。似た症状をもつ他の病気との見分け(鑑別)が、正しい治療につながります。
以下に、主な疾患との違いをまとめました。
| 病名 | 主な原因 | 症状が悪化する姿勢 | 症状が楽になる行動 |
| 腰部脊柱管狭窄症 | 神経の通り道が狭くなる | 背筋を伸ばして歩く、立つ | 前かがみになる、座る |
| 腰椎椎間板ヘルニア | 飛び出た椎間板が神経を圧迫する | 前かがみ、座り続ける | 横になるなど楽な姿勢をとる |
| 閉塞性動脈硬化症 | 足の血管が詰まり血流が悪くなる | 歩く、運動する | 姿勢に関係なく立ち止まる |
腰椎椎間板ヘルニアは、前かがみで悪化するのが特徴で、主に椎間板が神経を圧迫することが原因です。
閉塞性動脈硬化症は、足の血管が詰まり血流が不足することで痛みが出る病気です。脊柱管狭窄症とは異なり、姿勢に関係なく立ち止まるだけで症状が和らぎます。
似た症状でも原因は異なりますので、自己判断せず、早めに専門医の診察を受けることが重要です。
以下の記事では、腰椎すべり症の主な原因や、年代によって異なるリスク、治療法の選択肢をわかりやすく解説しています。
>>腰椎すべり症の原因と特徴!年代別リスクと治療法を解説
腰部脊柱管狭窄症の症状を改善する治療法
腰部脊柱管狭窄症の治療法として、改善が期待できるのは以下の3つです。
- 保存療法(薬・ブロック注射など)
- 運動療法
- 低侵襲手術(保存療法で改善しない場合)
保存療法(薬・ブロック注射など)
腰部脊柱管狭窄症の治療は、まず手術以外の保存療法から始めるのが基本です。保存療法は、体への負担を抑えながら痛みやしびれを和らげることを目的とし、複数の方法を組み合わせて行います。中でも薬物療法は中心的な手段で、炎症や痛みを抑え、血流を改善して神経の回復を助ける働きがあります。
以下に、薬の種類を含む主な保存療法の内容をまとめました。
| 方法 | 目的・効果 | 補足事項 |
| 痛み止め(消炎鎮痛薬) | 炎症を抑えて痛みを緩和 | 一般的な痛み止め(例:NSAIDs) |
| しびれの薬(神経障害性疼痛薬) | 神経の興奮を抑えて、しびれや鋭い痛みを軽減 | 神経が敏感になっている場合に使用 |
| 血流改善薬(プロスタグランジン製剤) | 神経周辺の血流を促進し、圧迫による循環不良を改善 | 神経の栄養不足に対応 |
| ビタミンB12製剤 | 傷ついた神経の修復をサポート | 補助的に使用されることが多い |
| ブロック注射 | 痛みの原因となる神経周囲に薬を注射し、強い痛みを一時的に抑える | ・局所麻酔や抗炎症薬を使用 ・診断目的にも使われる |
| コルセット療法 | ・腰を安定させて痛みを軽減する ・動作時の不安を軽くする |
長期使用は筋力低下のリスクがあるため、医師の指示が必要 |
保存療法は、手術を避けたい方や、まずは日常生活を楽にしたい方に適した治療です。ただし、保存療法だけで症状の改善が得られない場合や、神経へのダメージが進んでいると判断された場合には、手術を検討する必要があります。不安な点があれば、医師に相談しながら、最適な治療法を一緒に考えていくことが大切です。
以下の記事では、腰部脊柱管狭窄症に対する手術の成功率やリスク、回復までの流れを詳しく解説しています。手術を検討する際の判断材料として、ぜひ参考にしてください。
>>腰部脊柱管狭窄症の手術成功率は?リスクや回復までの流れを解説
運動療法
薬物療法と並んで、腰部脊柱管狭窄症の治療を支えるもう一つの柱が運動療法です。痛みの軽減だけでなく、再発しにくい体づくりを目指す根本的なアプローチとして行われます。理学療法士が、一人ひとりの状態に合わせて適切な運動を指導します。
ストレッチは、硬くなった筋肉をほぐして血流を改善し、神経への負担を軽減することが目的です。主なポイントは以下のとおりです。
- 腰、臀部、太もも裏の筋肉をゆっくり伸ばす
- 筋肉の緊張をほぐし、血流を促進する
- 腰を軽く丸める姿勢で神経の通り道が広がりやすくなる
筋力トレーニングは、体幹を鍛えて背骨を安定させ、痛みが出にくい体に整えることが目的です。主なポイントは以下のとおりです。
- 腹筋・背筋などの体幹をバランス良く鍛える
- 背骨を支える筋力を高める
- 腰を強く反らす運動は避ける
- 自己流ではなく、必ず専門家の指導のもとで行う
無理のない運動を継続することが、長期的な機能維持や再発予防につながります。大切なのは、専門家の評価にもとづいて無理のない適切な運動を継続することです。
低侵襲手術(保存療法で改善しない場合)
保存療法を数か月続けても症状が改善しない場合や、以下の状態が見られる場合には手術を検討します。
- 足の筋力低下が進み、歩行が難しくなってきた
- 排尿・排便の異常(馬尾症状)が出てきた
- 痛みやしびれが日常生活に支障をきたしている
近年は体への負担を最小限に抑えた「低侵襲手術」が主流です。代表的な低侵襲手術の一つが、内視鏡下手術です。モニターで神経の状態を確認しながら、必要最小限の範囲で圧迫を取り除くことを目的としています。内視鏡下手術のメリットは以下のとおりです。
- 筋肉へのダメージが少ない
- 術後の痛みが軽く、回復が早い
- 入院期間が短くなる傾向がある
手術は、神経の圧迫を取り除く「除圧術」が基本です。背骨に不安定さがある場合は、除圧に加えて「固定術」を併用することがあります。どの手術法が適しているかは、MRIなどの検査結果をもとに、症状や骨の状態を総合的に判断して決定します。
日常生活での対策
治療と並行して、日々の暮らし方を少し見直すことが大切です。日常生活でできる対策は以下の2つです。
- 正しい姿勢で腰への負担を減らす
- 日常動作を工夫する
正しい姿勢で腰への負担を減らす
腰部脊柱管狭窄症の症状は、姿勢によって大きく変わります。背筋を反らすと、神経の通り道である脊柱管が狭くなり症状が悪化します。逆に、少し丸めると脊柱管が広がり、神経への圧迫が和らぎます。
立ち姿勢と座り姿勢、寝るときの姿勢のポイントを以下の表にまとめています。
| 場面 | やってはいけない姿勢(NG) | 心がけたい姿勢(OK) |
| 立つ | 胸を張って腰を反らす姿勢 | 少しお腹に力を入れ、軽く前かがみ |
| 座る | 浅く腰掛け、背中が丸まる姿勢 | 深く腰掛け、背もたれを使う |
| 寝る | うつ伏せ(腰が最も反る姿勢) | 横向きで膝を曲げる、仰向けで膝下にクッション |
日常動作を工夫する
日常の何気ない動作も、実は腰に大きな負担をかけています。特に「物を持ち上げる」「前かがみになる」などの動作には注意が必要です。動作の工夫だけでも、症状の悪化を防ぐことができます。以下に、日常の動作ごとの注意点をまとめました。
| 動作の場面 | 注意点・コツ |
| 物を持ち上げるとき | ・膝を伸ばしたまま腰を曲げない(最も腰に負担がかかる姿勢) ・物に体を近づけ、膝をしっかり曲げる ・物を体に引き寄せ、足の力で立ち上がる |
| 顔を洗う・台所作業 | ・前かがみになるときは膝を軽く曲げる ・片足を一歩前に出して台に乗せると腰の負担を軽減できる |
| 歩くとき | ・少し前かがみの姿勢を意識すると歩きやすくなる ・杖やシルバーカーの使用も有効(痛み軽減・転倒防止) |
最近の研究では、運動療法は専門的なマッサージよりも、長期的に日常生活の改善にやや有利な可能性があると報告されています。ただし、その差は大きくなく、年齢・性別・治療内容によっても結果は異なるため、一人ひとりに合った対応が重要です。
まとめ
腰部脊柱管狭窄症は、歩行時の足のしびれや痛み、筋力低下などを引き起こす病気で、放置すると日常生活に支障をきたすことがあります。症状は姿勢や動作によって変化しやすく、神経の圧迫が原因です。
治療はまず保存療法(薬・リハビリテーション)から始め、症状が改善しない場合は体への負担を抑えた低侵襲手術が検討されます。日常動作や姿勢を工夫することで、症状の悪化を防ぐことも可能です。早期の診断と適切な対応が、快適な生活への基本になります。気になる症状がある方は、自己判断せず早めに専門医に相談しましょう。
当院の受診をご希望の方は、まずはお電話にてご予約ください。詳しいアクセス方法は、当院の公式サイトをご覧ください。
>>大室整形外科へのアクセスはこちら
参考文献
Luis González-Gómez, Jose A Moral-Munoz, Abel Rosales-Tristancho, Alejandro Cuevas-Moreno, Melania Cardellat-González, Álvaro-José Rodríguez-Domínguez. Exercise Therapy Versus Manual Therapy for the Management of Pain Intensity, Disability, and Physical Function in People With Chronic Low Back Pain: A Systematic Review With Meta-Analysis and Meta-Regression. Eur J Pain, 2025, 29(8), p.e70090-e70090