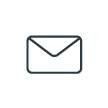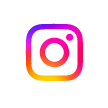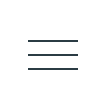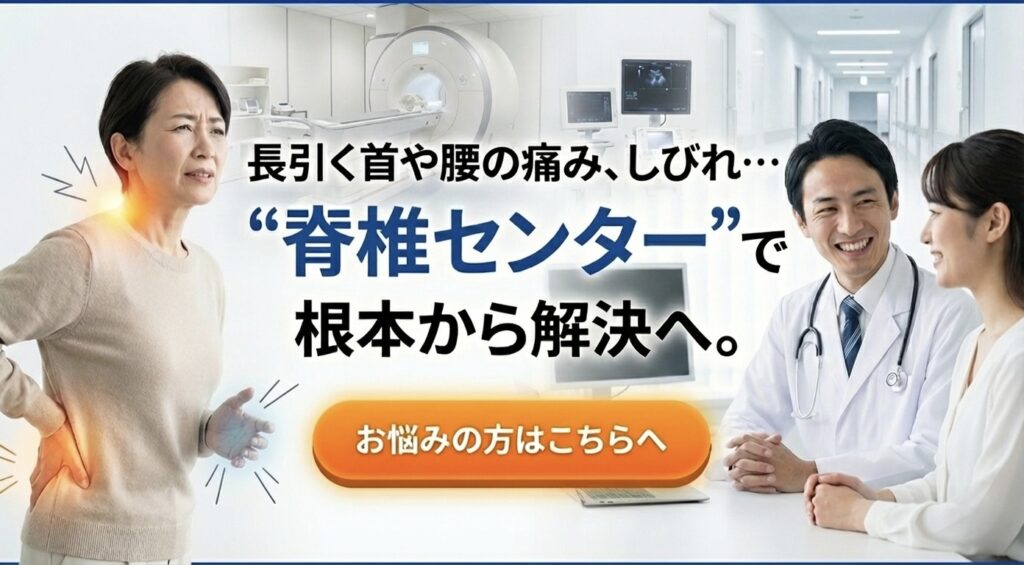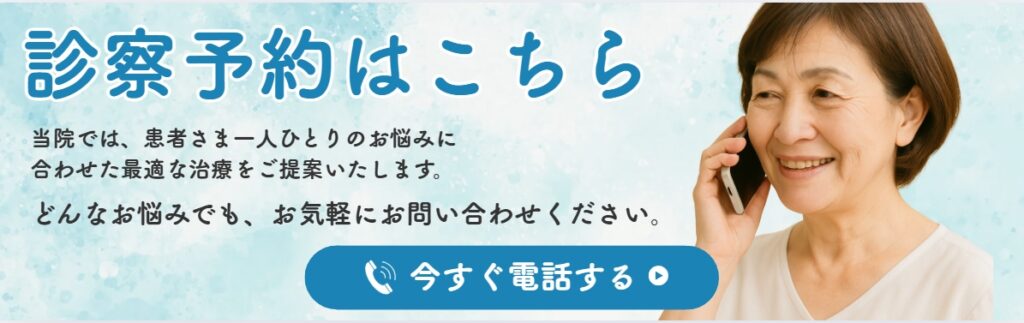【医師監修】首の痛みが1ヶ月治らない原因!何科を受診すべき?病気の可能性も解説
首の痛みが1ヶ月以上続いていませんか?「寝違えだろう」と放置することは危険です。日常の姿勢による負担や加齢変化、手足のしびれを伴う病気の可能性があります。特にスマートフォンを覗き込む姿勢は首に大きな負荷をかけているため、注意が必要です。
この記事では医師監修のもと、長引く首の痛みの原因から危険なサインの見分け方、何科を受診すべきかまで詳しく解説します。ご自身の症状と照らし合わせ、つらい痛みと不安を解消する第一歩にしてください。
当院では、首の痛みや手足のしびれなどの症状に対し、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。不安な症状がある方も安心してご相談いただけるよう、以下の記事で診察の流れや受付方法を詳しくまとめています。
>>診察のご案内について

記事監修:川口 慎治
大室整形外科 脊椎・関節クリニック 医師
経歴:
徳島大学医学部卒業後、洛和会音羽病院に勤務
京都大学医学部整形外科学教室入局
学研都市病院脊椎脊髄センター勤務
2023年より 大室整形外科 脊椎・関節クリニック勤務
専門分野:脊椎・脊髄外科
資格:
日本専門医機構認定 整形外科専門医
日本整形外科学会認定 脊椎脊髄病医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科指導医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科専門医
1ヶ月以上続く首の痛みの主な原因
1ヶ月以上続く首の痛みの主な原因は、以下のとおりです。
- デスクワークやスマホ操作による姿勢の悪化
- 加齢に伴う骨や椎間板の変化
- 交通事故・スポーツ外傷による後遺症
- ストレスによる自律神経の乱れと血行不良
デスクワークやスマホ操作による姿勢の悪化
毎日、長時間パソコンやスマートフォンを使っている方は、首に大きな負担をかけている可能性があります。人の頭は重く、体重50kgの人なら約5kgの重さがあります。うつむいてスマホを見るなど、頭が15度傾くだけで首への負担は約12kgに、60度傾くと約27kgもの負荷がかかると報告されています。
悪い姿勢が痛みを引き起こすメカニズムは以下のとおりです。
| 原因 | 説明 |
| 筋肉の過緊張 | 前に突き出た重い頭を支えるため、首から肩や背中にかけての筋肉が常に緊張し、硬直する |
| 血行不良 | 筋肉が硬くなると、筋肉の中を通る血管が圧迫され、血液の流れが悪くなる |
| 痛み物質の発生 | 血流が悪くなると、筋肉に十分な酸素や栄養が届かなくなり、乳酸などの痛みを感じさせる物質(発痛物質)が溜まる |
最初は軽い痛みでも、1ヶ月以上続くと、なかなか治らない頑固な痛みへと変わってしまいます。
加齢に伴う骨や椎間板の変化
年齢を重ねると、首の骨や周辺の組織にも少しずつ変化が現れます。代表的な病気である「頸椎症」と「頸椎椎間板ヘルニア」について、以下の表にまとめました。
| 病名 | メカニズム | 主な症状 | 特徴 |
| 頸椎症 | 加齢で椎間板が薄くなり、骨同士がこすれて骨棘(こつきょく)が発生し、神経を刺激する | 首の痛みや肩から腕の痛み、しびれ | 首を後ろに反らすと痛みが強くなる |
| 頸椎椎間板ヘルニア | 椎間板が変形し、髄核が外に飛び出し神経や脊髄を圧迫する | 首や肩の激しい痛み、腕や手のしびれ、細かい動作の障害(箸・ボタンなど) | 症状が進行すると手先の動きに支障が出る |
単なる筋肉の疲れとは違い、骨や神経が直接関係しているため、痛みが1ヶ月以上と長引きやすい傾向です。
特に加齢変化による頸椎の病気では、首を後ろに倒す動きで痛みが強まるのが特徴です。日常生活の中でも症状が悪化しやすいため、原因を正しく理解して対処することが重要です。
以下の記事では、首を後ろに倒したときの痛みの原因や、症状に応じた治し方・ストレッチについて解説しています。
>>首を後ろに倒すと痛い原因は?痛みがあるときの治し方やストレッチを解説
交通事故・スポーツ外傷による後遺症
交通事故やスポーツでは、首に強い衝撃を受けた直後は症状が軽くても、後から痛みが出てきて1ヶ月以上治らないことがあります。代表例は「むち打ち症(頸椎捻挫)」です。
むち打ち症は、追突事故などで頭が激しく揺さぶられ、首の筋肉や靭帯、神経が損傷するけがです。事故直後は心身が興奮しているため、痛みを感じにくく、数時間~数日経ってから症状が現れることがあります。首には体のバランスを保つ自律神経もあるため、首の痛み以外に頭痛やめまい、吐き気、耳鳴りの症状が現れる可能性があります。
交通事故だけでなく、ラグビーや柔道などのコンタクトスポーツでの衝突や、転倒などでも同様のけがをすることがあります。思い当たる経験がある方は、注意が必要です。
ストレスによる自律神経の乱れと血行不良
仕事や人間関係などの精神的なストレスも、長引く首の痛みの原因になります。体は、ストレスを感じると無意識のうちに、全身が緊張します。ストレスが痛みを引き起こすメカニズムは以下のとおりです。
| 段階 | メカニズム |
| 自律神経の乱れ | ストレスで交感神経が過剰に働き、副交感神経が弱まる |
| 筋肉の緊張と血管の収縮 | 交感神経が優位となり筋肉がこわばり、血管が収縮して血行が悪化する |
| 痛みの発生・悪化 | 血行不良で痛み物質が溜まる |
「痛みがなかなか治らない」こと自体が新たなストレスとなり、筋肉が緊張するという「痛みの悪循環」に陥る可能性もあります。検査で異常が見つからないのに、1ヶ月以上も首の痛みが続く場合は、ストレスが原因の可能性も考えましょう。
特に首筋の痛みは、ストレスによる筋緊張と血行不良が影響しやすい部位です。放置すると慢性化して生活に支障をきたす恐れもあるため、原因を見極めて適切に対処することが大切です。
以下の記事では、首筋が痛いときに考えられる原因や注意すべき症状、対処法について解説しています。
>>首筋が痛いときの原因と対処法!放置すると危険な症状も解説
受診すべき危険なサイン
受診すべき危険なサインは、以下のとおりです。
- 手足のしびれ
- 歩行障害
- 激しい頭痛
手足のしびれ
首の痛みと一緒に、腕や手の指先に「ジンジン」としたしびれを感じる場合、神経が圧迫されているサインです。首の骨(頸椎)の中には、脳からの命令を全身に伝える「脊髄(せきずい)」という太い神経の束が通っています。脊髄から腕や手に向かって、細い神経が枝分かれしています。
加齢による骨の変形(頸椎症)や、骨のクッションである椎間板が飛び出すヘルニアによって神経が圧迫されると、しびれや痛みが生じます。放置すると神経のダメージが大きくなり、筋力低下が起こる可能性もあります。しびれを感じたら、頸椎を専門とする整形外科医に相談し、MRI検査で原因を調べましょう。
歩行障害
「何もない平らな場所でつまずきやすい」といった症状は、首の痛みに伴う危険なサインです。歩きにくさが出ている場合、脊髄が強く圧迫されている可能性があります。脳からの「歩け」という命令が、首の神経で止められ、足まで届かない状態です。首の問題が、遠く離れた足の動きにまで影響を及ぼします。
歩行に影響が出ている場合は、放置せずに早急な対応が必要です。すぐに脊椎を専門とする整形外科を受診してください。
激しい頭痛
首の痛みに伴う頭痛はよくありますが、激しい頭痛には注意が必要です。「首の痛みだから大丈夫」と自己判断してしまうと、命に関わる重大な病気を見逃す恐れがあります。命に関わる可能性のあるサインとして、以下のような症状があります。
- 突然の激痛
- 高熱や吐き気、嘔吐
- 手足のしびれ
- めまい
- 呂律が回らない
症状が現れた場合には、以下の緊急性の高い病気の可能性があります。
- くも膜下出血:脳の血管が破れる病気
- 髄膜炎(ずいまくえん):脳や脊髄を覆う膜に菌が感染する病気
- 椎骨動脈解離:首を通って脳へ向かう血管が裂ける病気
首の痛みも伴うことが多いため「いつもの首こりからくる頭痛だろう」と軽く考えてしまうのは危険です。激しい頭痛を感じた場合は、様子を見ずに、ただちに救急車を呼ぶか、脳神経外科などの救急外来を受診してください。
症状に合わせた診療科の選び方
症状に合わせた診療科の選び方について、以下の内容を解説します。
- 基本は「整形外科」の受診を
- 症状で判断する専門の診療科
基本は「整形外科」の受診を
まず、首の痛みが続く場合は整形外科を受診しましょう。整形外科は、骨や関節、筋肉、神経など、体を動かす仕組み(運動器)の専門家です。長引く首の痛みの多くは、頸椎や周辺の筋肉、神経に原因があります。運動器の専門家である整形外科が、最初の相談窓口として適しています。
症状で判断する専門の診療科
首の痛み以外に気になる症状がある場合は、他の診療科が適していることもあります。以下の表を参考に、ご自身の症状に合う診療科を選びましょう。
| 診療科 | こんな症状のときにおすすめ |
| 整形外科 | ・首や肩、背中の痛み全般 ・首を動かすと痛みが強くなる ・腕や手に軽いしびれや痛みがある ・レントゲンやMRIで骨や神経の状態を詳しく調べたい |
| 神経内科 | ・手足のしびれや感覚の鈍さが主な症状 ・手に力が入りにくく、細かい作業が難しい ・歩きにくさや、ふらつきがある ※脳や脊髄、末梢神経の病気を専門とします。 |
| 脳神経外科 | ・「バットで殴られたような」突然の激しい頭痛 ・吐き気や嘔吐、めまいを伴う ・言葉がうまく話せない、視野が狭くなる ※緊急性の高い脳の病気が疑われる場合に受診します。 |
| ペインクリニック科 | ・いろいろな治療を試しても痛みがとれない ・とにかく今のつらい痛みを早く和らげたい ・痛みが原因で夜も眠れない ※神経ブロック注射など、痛みを抑える治療を専門とします。 |
どの科を受診すべきか迷った場合は、まず整形外科を受診してください。整形外科で詳しい検査を行えば、痛みの原因を突き止められる可能性があります。
他の専門的な治療が必要だと判断された場合でも、適切な診療科を紹介してもらえます。
医療機関で行う主な検査や治療法
医療機関で行う主な検査や治療法について、以下の内容を解説します。
- 痛みの原因を特定する検査
- 保存療法
- リハビリテーション
- 手術が必要になるケース
痛みの原因を特定する検査
正しい治療への第一歩は、痛みの原因を見つけ出すことです。問診・診察などの医師との対話から精密な画像検査まで、いくつかの方法を組み合わせて診断します。問診・診察は「いつから、どこが、どのように痛むのか」を把握するための重要な情報です。画像検査は体の内部を「見る」ことで、痛みの原因となる証拠を探します。
痛みの原因となる証拠を探す画像検査の種類と特徴は、以下のとおりです。
| 検査の種類 | 特徴 |
| レントゲン検査 | ・骨の形や並び、骨と骨の間隔を確認する基本的な検査 ・骨の変形や骨折の有無などを調べる際に使用される |
| MRI検査 | ・磁石の力を利用して体の断面を詳しく見る検査 ・レントゲンでは見えない神経や椎間板、筋肉を映せる ・軟らかい組織の状態を鮮明に確認できる ・椎間板ヘルニアや神経圧迫の診断に重要 |
| CT検査 | ・レントゲンを使い、体を輪切りのように撮影する検査 ・骨の状態を立体的かつ詳細に調べられる ・交通事故による骨折の確認に有効 ・骨の細かい変形を詳しく見るのに適している |
検査結果を総合的に判断し、痛みの原因を特定したうえで、最適な治療方針を決定します。
保存療法
手術をしない治療法を「保存療法」と呼びます。1ヶ月以上続く首の痛みの治療は、多くの場合、保存療法からスタートします。保存療法の目的は、痛みを和らげ、体の機能を回復させることです。保存療法の種類は薬物療法と神経ブロック注射があります。
薬物療法は症状に合わせて薬を使い分け、つらい痛みの悪循環を断ち切る治療法です。飲み薬には炎症による痛みや腫れを抑える「消炎鎮痛薬」や、硬くなった筋肉の緊張をほぐす「筋弛緩薬」などがあります。貼り薬・塗り薬には痛む場所に直接使用することで、皮膚から有効成分が浸透し、炎症や痛みを抑える効果が期待できます。
神経ブロック注射は痛みの原因となっている神経のすぐ近くに、局所麻酔薬などを直接注射する治療法です。特に痛みが強い場合に、興奮して過敏になっている神経を落ち着かせ、つらい症状を和らげることを目指します。痛みの悪循環を断ち切ることで、リハビリテーションを円滑に進めやすくなるという利点もあります。
リハビリテーション
リハビリテーションは、単に痛みを和らげるだけでなく、首の本来の機能を取り戻し、痛みの再発を防ぐために重要な治療です。国家資格を持つ専門家である理学療法士が、一人ひとりの体の状態に合わせて最適なプログラムを作成し、マンツーマンで指導します。
リハビリテーションは、患者さん自身が体を動かす運動療法です。首や肩周りの筋肉を鍛えて首を安定させ、硬くなった筋肉をストレッチで柔軟にします。最近の研究で首の神経が原因で起こる痛み(頸部神経根症)に対して、複数のリハビリ手法を組み合わせることでより良い効果が期待できることが報告されています。
神経の滑りを良くする神経モビライゼーションや、首を優しく引っ張る頸部牽引、関節の動きを改善する手技などがあります。
手術が必要になるケース
首の痛みの多くは保存療法で改善が期待できますが、一部のケースでは手術が必要となることがあります。以下のような症状がある場合は、手術が検討されます。
- 数か月間、保存療法で改善しない
- 麻痺(まひ)が進行している
- 歩行や排泄に障害が出た
放置すると、しびれや麻痺が後遺症として残ってしまう可能性もあります。手術が必要と判断した場合でも、患者さんのご希望や生活背景を丁寧にお伺いします。医師は十分に話し合ったうえで、最適な治療法を一緒に選択していきますのでご安心ください。
日常生活でできるセルフケア
日常生活でできるセルフケアは以下のとおりです。
- 首に負担をかけない姿勢を意識する
- 自分に合う枕を選ぶ
- 手軽なストレッチを行う
首に負担をかけない姿勢を意識する
長時間のデスクワークやスマートフォン操作は、無意識のうちに首に大きな負担をかける「悪い姿勢」になりがちです。正しい姿勢を意識することが、痛みを和らげる第一歩です。デスクワーク中は、椅子に深く腰掛け、足の裏全体を床につけ、お尻と背中を背もたれにしっかりつけるように意識しましょう。
パソコン画面の上端を目線の高さにし、肘の角度が90度くらいになるように、机や椅子の高さを調整しましょう。スマートフォンを使うときは、画面を顔の高さまで持ち上げ、うつむく角度をできるだけ浅くするように意識しましょう。
少なくとも30分に一度は休憩をとり、遠くの景色を見たり、首をゆっくり回したりして、同じ姿勢が続くのを防ぐことが大切です。
姿勢改善の工夫は、首全体だけでなく、特に負担が集中しやすい首の付け根の痛みを和らげるためにも効果が期待できます。日常的に意識することで慢性化を防ぐことにつながります。
以下の記事では、首の付け根が痛いときの原因や改善法について、より詳しく解説しています。
>>首の付け根が痛い原因は?症状の特徴や効果が期待できる改善法を解説
自分に合う枕を選ぶ
睡眠は疲れた体を休ませ、傷ついた組織を修復するための時間です。体に合わない枕を使っていると、寝ている間も首の筋肉が緊張し続け、負担をかけます。朝起きたときの痛みの原因になったり、症状を悪化させたりすることがあります。自分に合った枕を見つけるポイントは以下のとおりです。
| 寝姿勢 | 枕の高さの目安 |
| 仰向け | ・敷布団やマットレスと首のカーブの隙間を自然に埋める高さが理想 ・楽に呼吸できる状態 ・あごが上がりすぎたり引けすぎたりしない ・頸椎の自然なカーブを支えられる |
| 横向き | ・横向きに寝たとき、首から背骨までが一直線になる高さ ・肩幅があるため、仰向け時より少し高め |
枕を選ぶ際は、高さだけでなく、寝返りをうっても頭が落ちないか、頭が沈み込みすぎない適度な硬さがあるかも確認しましょう。枕を当てるときは、肩口までしっかり引き寄せ、首から頭全体を支えるように使いましょう。
手軽なストレッチを行う
痛みが少し落ち着いてきたら、硬くなった首や肩周りの筋肉を優しくほぐし、血行を良くするストレッチを取り入れましょう。筋肉を強化する運動や、神経モビライゼーションは、痛みを和らげるのに有効である可能性があります。安全に行うための注意点は、以下のとおりです。
- 痛みやしびれが少しでも強まる場合は、すぐに中止する
- 「痛いけれど気持ちいい」と感じる範囲で、ゆっくりと行う
- 呼吸を止めずに、心と体をリラックスさせた状態で行う
- 反動をつけず、20〜30秒かけて伸ばすことを意識する
ストレッチは症状を和らげるための補助的な手段です。痛みが改善しない、または悪化するような場合は、自己判断で続けずに専門の医療機関にご相談ください。具体的なストレッチの例は、以下のとおりです。
| ストレッチ名 | 方法 |
| 首の横伸ばし | 1.ゆっくりと首を真横に倒す
2.倒した側の手で頭を軽く押さえて15秒ほどキープする 3.反対側も同様に行う |
| 肩甲骨寄せ | 1.両ひじを90度に曲げて体の横につける
2.ゆっくりと背中側で肩甲骨を寄せ、胸を張る 3.5秒ほどキープして、ゆっくり元に戻す |
| あご引き体操 | 1.背筋を伸ばしてまっすぐ前を向く
2.あごをゆっくりと水平に引いて首の後ろを伸ばす |
まとめ
長引く首の痛みは、単なる肩こりではなく、姿勢の悪化や加齢、神経に関わる病気が隠れている可能性があります。特に、手足のしびれや歩きにくさ、経験したことのない激しい頭痛などの症状は、見過ごしてはいけない重要なサインです。
どんな原因であっても、自己判断で放置することは危険です。症状に少しでも不安を感じたら、まずは骨や神経を専門とする整形外科を受診しましょう。
当院(大室整形外科 脊椎・関節クリニック)は、脊椎センター・人工関節センターの2つを軸にしたクリニックです。首や腰、関節の痛み、リハビリなどでお悩みの方へ、専門医が丁寧に相談に応じます。JR姫路駅からは無料送迎バスを利用できますので、お気軽にご来院ください。
>>診察のご案内について
参考文献
- Kenneth K. Hansraj. Assessment of stresses in the cervical spine caused by posture and position of the head. Surg Technol Int, 2014, 25, p.277-279.
- Sergio Núñez de Arenas-Arroyo, Dimitris Mavridis, Vicente Martínez-Vizcaíno, Ana Torres-Costoso, Sara Reina-Gutiérrez, Eva Rodríguez-Gutiérrez, Iván Cavero-Redondo, Irene Sequí-Domínguez. What components and formats of rehabilitation interventions are more effective to reduce pain in patients with cervical radiculopathy? A Systematic review and component network meta-analysis. Clin Rehabil, 2025, 39, 10, p.1296-1310