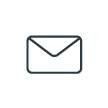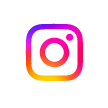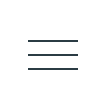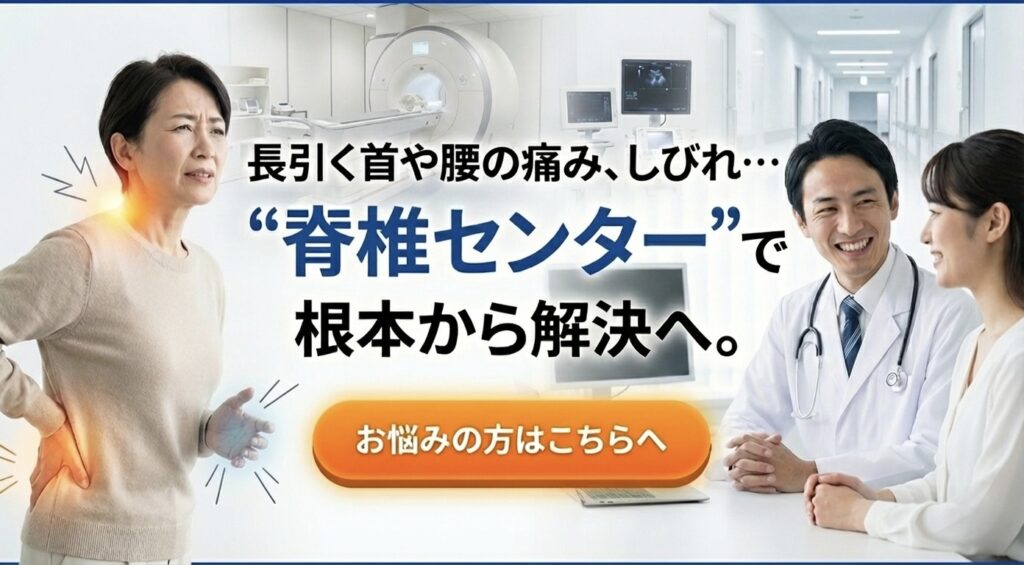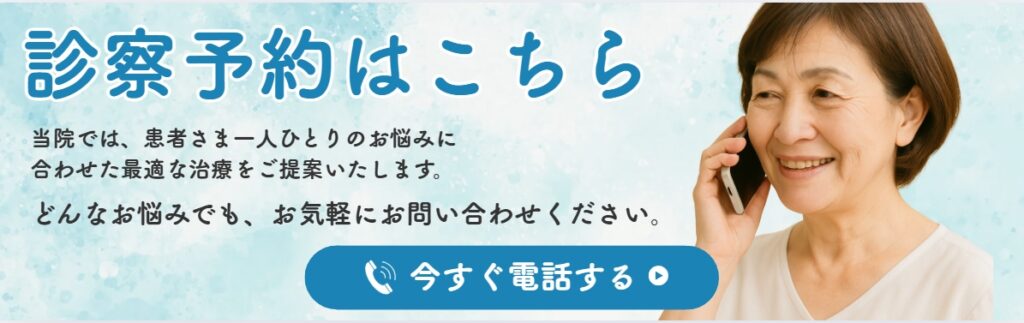首を後ろに倒すと痛い原因は?痛みがあるときの治し方やストレッチを解説
うがいをするときや上を向いたとき、首の後ろに痛みが走ることはありませんか?原因は、肩こりだけではありません。姿勢の癖や加齢による変化も原因として考えられ、放置するとしびれや麻痺につながる病気の可能性があります。
本記事では、首を後ろに倒すと痛む代表的な5つの原因や病院へ行くべきサイン、痛みを和らげるセルフケアを解説します。ご自身の症状と照らし合わせ、痛みの根本原因や治療法について知り、痛みの不安を解消しましょう。
当院では、首の痛みや肩こり、頸椎椎間板ヘルニアなどの症状に対し、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。不安な症状がある方も安心してご相談いただけるよう、以下の記事で診察の流れや受付方法を詳しくまとめています。
>>診察のご案内について

記事監修:川口 慎治
大室整形外科 脊椎・関節クリニック 医師
経歴:
徳島大学医学部卒業後、洛和会音羽病院に勤務
京都大学医学部整形外科学教室入局
学研都市病院脊椎脊髄センター勤務
2023年より 大室整形外科 脊椎・関節クリニック勤務
専門分野:脊椎・脊髄外科
資格:
日本専門医機構認定 整形外科専門医
日本整形外科学会認定 脊椎脊髄病医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科指導医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科専門医
首を後ろに倒すと痛いときに考えられる5つの原因
首を後ろに倒すと痛いときに考えられる代表的な原因は、以下の5つです。
- 加齢による変化が原因の頸椎症
- 椎間板が飛び出す頸椎椎間板ヘルニア
- 不良姿勢が招くストレートネック(スマホ首)
- 急な痛みは寝違え・むちうちの可能性
- 骨や関節以外の病気が隠れているケース
加齢による変化が原因の頸椎症
「頸椎症(けいついしょう)」は、年齢による変化が原因で首の痛みや手のしびれが起こる状態です。首の骨(頸椎)は、重い頭を支え続けています。年齢を重ねると、骨や周りの組織が少しずつ変化していきます。
椎間板は骨と骨の間にあり、衝撃を吸収し背骨の動きを支え、体を安定させる軟骨です。経年変化で水分を失い、すり減って薄くなります。骨のふちが、トゲのように変形する「骨棘(こつきょく)」が形成されると、神経の通り道を狭めます。頸椎症でみられる症状は、以下のとおりです。
- 首や肩、肩甲骨まわりの慢性的な痛みやこり
- 首を後ろに倒すと腕から手にかけて走る鋭い痛み
- 指先のしびれや細かい作業のしにくさ
- うがい、上を向くなどの特定の動きの痛み
首を後ろに反らす動きは、神経の通り道を狭くするため、症状が出やすいのが特徴です。
椎間板が飛び出す頸椎椎間板ヘルニア
「頸椎椎間板ヘルニア」は、椎間板の中にある組織(髄核)が外側の膜を破って飛び出している状態です。ヘルニアは、腰だけでなく、頸椎でも起こります。飛び出したヘルニアは、近くを通っている重要な神経を圧迫することで、首の痛みや腕や手にかけての痛みやしびれを引き起こします。頸椎椎間板ヘルニアの主な原因は、以下のとおりです。
- 加齢による椎間板の質の低下:椎間板の弾力性が失われ、傷つきやすくなる
- 猫背などの悪い姿勢の継続:首へ不自然な圧力がかかり続ける
- スポーツや事故による首への強い衝撃:コンタクトスポーツで起こりやすい
- 重いものを持ち上げるなどの急な負荷:くしゃみだけでも発症することがある
多くの場合、安静や薬物療法により改善が期待されますが、症状が強い場合は専門的な治療が必要となります。
無理をせず適切に対処することが、回復や再発予防のために重要です。以下の記事では、頸椎椎間板ヘルニアの痛みを和らげる方法や効果が期待できる対処法について解説しています。
>>頸椎椎間板ヘルニアの痛みを和らげる方法!効果が期待できる対処法と注意点
不良姿勢が招くストレートネック(スマホ首)
「ストレートネック(スマホ首)」は、頸椎の緩やかなS字カーブが失われ、骨がまっすぐ(カーブの減少)になる状態です。頸椎のS字カーブは、重たい頭の衝撃を吸収する役割があります。
うつむき姿勢でのスマートフォンの長時間使用や猫背によるパソコン作業は、首まわりの筋肉に負担がかかる原因となります。症状は、慢性的な肩こりや頭痛、めまい、吐き気などです。首への負担が増えることで、将来的には頸椎症や頸椎椎間板ヘルニアの発症リスクも高まります。
ストレートネックは、首だけではなく、背中全体の姿勢が影響している点が問題です。研究では、首の痛みに対して背中(胸椎)の柔軟性を高めるアプローチが有効であることが示唆されています。首の不調を改善するには、首だけでなく背骨の胸の部分(胸椎)の動きを良くすることも重要です。
特に首の付け根はストレートネックによる負担が集中しやすく、痛みやこりの原因となる部位です。慢性化すると頭痛や肩の不快感にもつながるため、適切な改善方法を知ることが大切です。
以下の記事では、首の付け根が痛いときの原因や、効果が期待できる改善法について解説しています。
>>首の付け根が痛い原因は?症状の特徴や効果が期待できる改善法を解説
急な痛みは寝違え・むちうちの可能性
急な首の痛みの多くは「寝違え」です。首の筋肉や靭帯に過度な負担がかかり、軽い肉離れの炎症を起こしている状態です。睡眠中の不自然な姿勢や枕の高さが合っていないことで起こります。ほとんどの場合は数日〜1週間ほどで自然に良くなります。
痛みが強いときは無理に動かしたり、マッサージしたりしないようにしましょう。交通事故やスポーツなどで首に強い衝撃が加わって起こる痛みを「むちうち(外傷性頸部症候群)」といいます。首が前後に大きくしなることで、筋肉や靭帯、神経まで損傷する状態です。
痛みだけでなく、頭痛やめまい、吐き気、手足のしびれなど、さまざまな症状が現れることがあります。事故直後に症状がない場合も、数時間後や翌日以降に痛みが出てくることがあります。強い衝撃を受けた場合は、症状がなくても早めに整形外科を受診することが重要です。
骨や関節以外の病気が隠れているケース
まれに整形外科以外の病気が隠れている可能性もあります。考えられる病気と注意が必要な症状は、表のとおりです。
| 考えられる病気 | 注意が必要な症状 |
| 椎骨(ついこつ)動脈解離による脳梗塞 | ・突然の激しい後頭部痛や首の痛みがある
・めまいがある ・ろれつが回らない |
| 髄膜炎 | ・発熱や激しい頭痛、嘔吐を伴う
・首が硬直し前に曲げられない(項部硬直) |
| 心臓の病気(関連痛) | ・左肩や首、顎に広がる痛みがある
・胸の圧迫感や息苦しさがある |
| 悪性腫瘍 | ・安静時に痛みがある
・夜中に痛みで目が覚める ・徐々に痛みが悪化する |
症状がある場合は、自己判断で様子を見ず、医療機関に相談しましょう。強い症状がある場合は、早めの受診が必要です。
首を後ろに倒すと痛いときの危険サイン
首を後ろに倒したときに痛みだけでなく、他の症状が一緒に出ている場合は注意が必要です。症状は、単なる筋肉の問題ではなく、神経や血管に異常が起きている可能性があります。危険なサインについて、以下の3つを解説します。
- 首の痛みと一緒にしびれを感じる
- めまいや吐き気を伴う
- 手足に力が入らない・感覚が鈍い
首の痛みと一緒にしびれを感じる
首の痛みに加え、腕や手に走るしびれは、首の神経が圧迫されていることを示す可能性があります。しびれを伴う場合に考えられる主な病気は、以下のとおりです。
- 頸椎椎間板ヘルニア:椎間板の一部が飛び出し、神経を直接圧迫
- 頸椎症性神経根症:骨棘(骨が変形しできたトゲ)が神経の出口を狭くし、圧迫
頸椎の中には、脳から腕や手へ向かう大切な神経の通り道があります。神経の通り道が狭くなり、神経が圧迫されると、痛みやしびれといった症状が現れます。首の痛みの原因は1つとは限らず、専門的な検査と診断が必要です。
自己判断でのマッサージや痛い部分を強く揉むのは、注意が必要です。神経の圧迫を強めてしまい、症状を悪化させる可能性があります。しびれを感じたら、整形外科を受診し、痛みの原因を調べることが大切です。
めまいや吐き気を伴う
首を動かしたときに、目が回るようなめまいや吐き気を感じる場合も注意が必要です。椎骨動脈解離で見られる、注意すべき主な症状は以下のとおりです。
- 突然の激しい頭痛や首の痛み
- 激しいめまい
- 吐き気
- ものが二重に見える
- 言葉がうまく話せない(ろれつがまわらない)
頸椎の中には、脳に血液を送る血管(椎骨動脈)が通っており、体のバランスを保つ働きをする小脳や脳幹に血液を供給しています。椎骨動脈解離は、椎骨動脈の血管壁が裂けてしまう状態で、脳梗塞につながる恐れがあります。
手足に力が入らない・感覚が鈍い
首の痛みとともに手足に力が入りにくくなる症状は、注意が必要です。中枢神経である「脊髄」が圧迫されている可能性があります。脊髄が圧迫されている際は、以下のようなサインが現れます。
- お箸がうまく使えなくなる
- ペットボトルの蓋が開けにくくなる
- 字が下手になる
- シャツのボタンがかけづらくなる
- 歩行時に足がもつれ、何もないところでつまずきやすくなる
- 階段の上り下りが怖くなる
- 手足の広範囲がしびれる
- 尿が出にくくなる、または頻尿になる
症状は「頸椎症性脊髄症」や重度の「頸椎椎間板ヘルニア」で見られます。ゆっくりと進行することが多いため、ご自身では「歳のせい」と見過ごしてしまいがちです。脊髄への圧迫を放置すると麻痺が進行し、歩行が困難になるなど日常生活に支障をきたす可能性があります。気になる症状がある場合は、脊椎を専門とする整形外科を受診しましょう。
当院(大室整形外科 脊椎・関節クリニック)は、脊椎センターを持つクリニックです。痛みやしびれ、リハビリなどでお悩みの方へ、専門医が丁寧に相談に応じます。JR姫路駅からは無料送迎バスを利用できますので、お気軽にご来院ください。
>>診察のご案内
首の痛みを和らげるセルフケア
自宅でできる痛みを和らげる方法(セルフケア)について、以下の3点を解説します。
- まずは安静にして冷やす・温める
- 首のストレッチ方法
- 日常でできる姿勢改善と生活習慣の見直し
まずは安静にして冷やす・温める
首に痛みがあるときに大切なのは「安静」です。無理に動かしたり、強く揉んだりすると、筋肉の炎症を広げることがあります。痛みの種類に応じ「冷やす」か「温める」かを選びましょう。冷やしたほうがよいのは、次のような場合です。
- 寝違えや首をひねった直後(急性期)
- 脈打つように痛むとき
- 痛む部分が熱を持っているとき
急な痛みは、筋肉の繊維が傷つき、炎症を起こしています。冷やすことで血管が収縮し、炎症や腫れを抑える効果が期待できます。タオルで包んだ保冷剤や氷のうを、15分ほど痛む部分に優しく当てましょう。以下のような症状の場合は、温めるようにしましょう。
- じんわりとした鈍い痛みが続いているとき(慢性期)
- 首や肩の筋肉がこわばっているとき
- お風呂などで温まると痛みが楽になるとき
慢性的な痛みは、筋肉の緊張による血行不良によることが多いです。温めることで血管が広がり、血液循環が良くなります。蒸しタオルやカイロを当て、ぬるめのお風呂に浸かりましょう。
首のストレッチ方法
首のストレッチ方法について、以下の2つを解説します。
- 僧帽筋ストレッチ
- 後頭下筋群ストレッチ
僧帽筋ストレッチは、首から肩にかけての大きな筋肉を伸ばします。手順は、以下のとおりです。
- 椅子に浅めに座り、背筋を伸ばす
- 右手で頭の左側を持ち、ゆっくりと真横(右側)に倒す
- 左肩が一緒に上がらないよう、左手でお尻の下の椅子をつかむ
- 首の左側が伸びているのを感じながら、20秒ほどキープする
- ゆっくりと頭を元に戻し、反対側も同様に行う
後頭下筋群ストレッチは、首の付け根にある細かい筋肉をほぐすことができ、以下の流れで行います。
- 椅子に座り、両手を頭の後ろで組む
- 背中が丸まらないよう、両手の重みを使ってゆっくりと頭を前に倒す
- 顎を胸に近づけるようなイメージで、首の後ろが伸びるのを感じる
- 気持ちよく伸びているところで、20秒ほどキープする
お風呂上がりに行うと効果が期待できます。痛みが増す場合は、無理せず中止しましょう。
日常でできる姿勢改善と生活習慣の見直し
痛みの根本的な原因となっている生活習慣の見直しは、痛みを繰り返さない体づくりにとって大切です。首を守るために以下のような生活習慣を見直しましょう。
- パソコン・スマートフォンの使い方
- 睡眠習慣
- 姿勢
パソコンのモニターは、目線が少し下がる高さに調整しましょう。スマートフォンは顔の高さまで上げて操作し、うつむき姿勢を避けます。30分に一度は立ち上がり、遠くを見たり軽く肩を回したりする時間を作るのも大切です。
睡眠時の枕の高さは、仰向けで頸椎が背骨と一直線になる高さが理想です。首をねじるうつ伏せ寝は、首への負担が大きいため避けます。
長時間のデスクワークや車の運転での同一姿勢では、意識的に休憩を取り、こまめに姿勢を変えましょう。バッグを同じ肩にかける癖がある場合、左右交互に持つ心がけも大切です。小さな積み重ねが、首の痛みの予防に役立つ可能性があります。
整形外科で行う治療法
整形外科で行う治療法について、以下の内容を解説します。
- 注射療法(ブロック注射)
- リハビリテーション
- 手術療法(保存療法で改善しない場合)
注射療法(ブロック注射)
ブロック注射は、痛みの原因となる神経の近くに、局所麻酔薬などを直接注射する治療法です。飲み薬や湿布で痛みがコントロールできない、夜も眠れないほど痛みが強い場合に検討されます。痛みの信号が脳に伝わるのを一時的に「ブロック」することで、症状の軽減が期待されます。
治療はクリニックの外来で行うことができ、注射後は安静後、そのまま帰宅できます。効果の持続時間には個人差があり、痛みが和らいでいる間にリハビリなどを行うことで、症状の改善につながる可能性があります。
リハビリテーション
リハビリテーションは、首の痛みを根本的に改善し症状を繰り返さないために大切です。研究では、慢性的な首の痛みを改善するために、患者さん自身が積極的に行動を変えていく治療法が有効であると示されています。
報告では、75%の患者さんに症状の大幅な改善がみられました。薬やマッサージなどの標準的な治療だけを受けた場合の回復率(35%)と比べて、高い数値です。リハビリテーションは、以下の方法を組み合わせて用いられます。
- 徒手療法:理学療法士により、筋肉をほぐし関節の動きを滑らかにする
- 運動療法:首をしっかりと支えられる体作りを目指す
- 物理療法:温熱療法や電気治療などを用いて血の巡りを良くし、痛みを和らげる
- 生活指導:日常生活での痛みの原因を見つけ出し、改善へのアドバイスをする
外科手術(保存療法で改善しない場合)
手術が検討されるのは、以下のケースです。
- 強い痛みが長時間続き、日常生活が困難になっている
- 手や腕のしびれ、麻痺が進行している
- 足がもつれて歩きにくい
- 階段の上り下りが怖い
- 画像検査で神経が強く圧迫されていることが確認できる
手術の目的は、椎間板ヘルニアや変形した骨など、神経を圧迫している原因を物理的に取り除くことです。痛みやしびれを根本から解消することを目指します。代表的な手術方法は、以下の2つです。
- 頸椎前方除圧固定術:首の前から原因を取り除いて骨を固定する
- 頸椎椎弓形成術:首の後ろから神経の通り道を広げる
患者さんの年齢や症状、原因となる病気の種類により、手術方法は選択されます。手術は体への負担も伴います。医師から手術の必要性や内容、メリット・デメリットについて十分に説明を受け、ご自身が納得したうえで決定することが大切です。
保存療法で改善しない首の痛みは自己判断せず、まず原因を正しく知ることが重要です。以下の記事では、首の痛みが1ヶ月以上続く場合に考えられる病気や、受診すべき診療科について詳しく解説しています。
>>【医師監修】首の痛みが1ヶ月治らない原因!何科を受診すべき?病気の可能性も解説
まとめ
上を向いたときの痛みの原因は、1つではありません。日常生活の何気ない習慣が積み重なって起こるものから、年齢による自然な変化、骨や関節以外の病気が隠れていることもあります。腕や手のしびれやめまい、力の入りにくさを伴う場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
痛みが数日続いたり、セルフケアで改善しなかったりする場合も、我慢せず整形外科を受診しましょう。痛みの原因を正しく知り、ご自身に合った適切なケアを受けることがつらい症状を繰り返さないために大切です。
当院は、脊椎センターをもつクリニックです。痛みやしびれ、リハビリなどでお悩みの方へ、専門医が丁寧に相談に応じます。JR姫路駅からは無料送迎バスを利用できますので、お気軽にご来院ください。
>>診察のご案内
参考文献
- Jongmin Seo, Changho Song, Doochul Shin.A Single-Center Study Comparing the Effects of Thoracic Spine Manipulation vs Mobility Exercises in 26 Office Workers with Chronic Neck Pain: A Randomized Controlled Clinical Study.Med Sci Monit,2022,28,,p.e937316
- Taweewat Wiangkham, Sureeporn Uthaikhup, Alison Rushton.Effectiveness of an active behavioural physiotherapy intervention (ABPI) for chronic non-specific neck pain: an internal pilot cluster-randomised double-blind clinical trial.Musculoskelet Sci Pract,2025,79,,p.103389