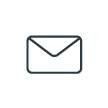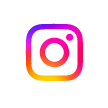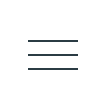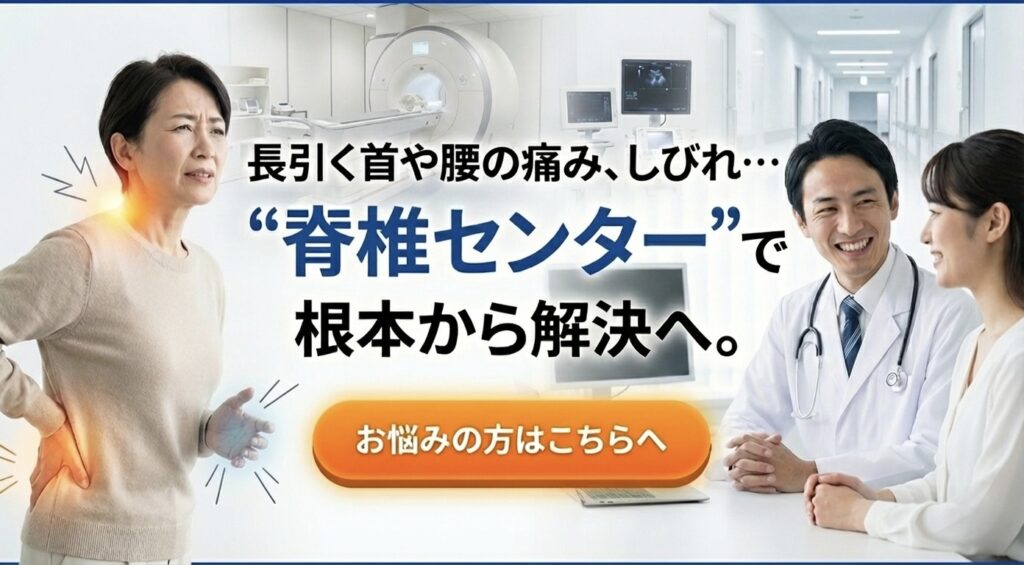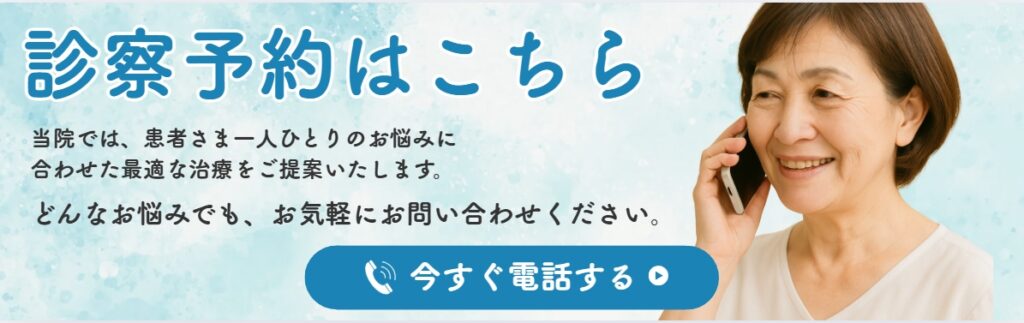後縦靱帯骨化症とは?寝たきりになる?原因や初期症状、進行を緩やかにする治療法
手足のしびれや箸の使いにくさを、加齢が原因と考える方が多い傾向です。症状を感じる方は、背骨の靱帯が神経を圧迫する後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)の可能性があります。
2020年度の政府統計では、後縦靱帯骨化症で医療費の助成を受ける患者さんは、全国に約36,000人います。珍しい病気ではなく、ゆっくり進むため気づきにくいのが特徴です。放置すると歩行が難しくなり、転倒をきっかけに症状が進行する可能性があります。
この記事では、後縦靱帯骨化症の初期症状や原因、治療法をわかりやすく解説します。病気について正しい知識を持ち、ご自身の体を守りましょう。
当院では、後縦靱帯骨化症をはじめとした整形外科疾患に対し、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。不安な症状がある方も安心してご相談いただけるよう、以下の記事で診察の流れや受付方法を詳しくまとめています。
>>診察のご案内について

記事監修:川口 慎治
大室整形外科 脊椎・関節クリニック 医師
経歴:
徳島大学医学部卒業後、洛和会音羽病院に勤務
京都大学医学部整形外科学教室入局
学研都市病院脊椎脊髄センター勤務
2023年より 大室整形外科 脊椎・関節クリニック勤務
専門分野:脊椎・脊髄外科
資格:
日本専門医機構認定 整形外科専門医
日本整形外科学会認定 脊椎脊髄病医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科指導医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科専門医
後縦靱帯骨化症の主な特徴
後縦靱帯骨化症は、背骨を支える組織「後縦靱帯」が硬くなる病気です。主な特徴について、以下の4点を解説します。
- 国の指定難病で脊髄を圧迫する病気
- 原因は不明だが遺伝や生活習慣病が関与
- 症状進行による歩行困難や排尿障害
- 転倒や外傷をきっかけに急激に悪化する危険性
国の指定難病で脊髄を圧迫する病気
後縦靱帯骨化症は国が定める「指定難病」の一つです。骨のように硬くなった靱帯が、脳からの指令を全身に伝える「脊髄」を圧迫するのが特徴です。
背骨は椎骨(ブロック状の骨)が積み重なってできています。後縦靱帯が硬くなると神経が通るトンネル(脊柱管)の内側が狭くなり、神経機能に異常が生じる可能性があります。後縦靱帯骨化症は首の骨である「頸椎」に多く発生し、胸の骨(胸椎)や腰の骨(腰椎)に起こることもある症状です。
原因は不明だが遺伝や生活習慣病が関与
ご家族に後縦靱帯骨化症の方がいる場合、発症する確率がやや高いことが報告されています。血糖値が高いと骨の形成に影響を与えるため、糖尿病や肥満の方も発症頻度が高くなる場合があります。
他に考えられる要因は以下のとおりです。
- カルシウムやビタミンDの代謝異常
- 特定のホルモンの影響
- 加齢に伴う体の変化
- 背骨への継続的なストレス
複数の要因が重なることで発症につながる可能性もあります。
症状進行による歩行困難や排尿障害
後縦靱帯骨化症は数年単位でゆっくり進行するため、初期の段階では自覚症状がない方も多いです。脊髄の圧迫が強まることで現れる主な症状は、以下のとおりです。
| 影響が出やすい部分 | 具体例 |
| 手や指の感覚・動き | ・しびれを感じる ・感覚が鈍くなる ・シャツのボタンがかけにくい ・箸がうまく使えない ・字が震えて書きにくくなる ・小銭がつまみにくい |
| 歩行 | ・足がもつれる ・何もない所でつまずきやすくなる ・足が前に出にくく、スリッパがよく脱げる ・階段の上り下りが怖く感じる |
| 排尿・排便 | ・トイレの回数が増える ・尿が出にくい ・残尿感がある ・便秘になりやすくなる |
神経が圧迫されると、手足のしびれや歩行の不安定さにつながる可能性があります。症状が進行すると自力での歩行が難しく、日常生活の多くの場面で介助が必要になることもあります。
転倒や外傷をきっかけに急激に悪化する危険性
後縦靱帯骨化症と診断された方は、転倒や事故による急激な症状の悪化に注意が必要です。転んで頭を打つ、尻もちをつくなどの小さな衝撃でも注意が必要です。
脊髄が損傷されると、手足が動かなくなる「四肢麻痺」などの重い後遺症が残ることがあります。日常生活で転ばないように、細心の注意を払うことが大切です。症状のわずかな変化も見逃さないために、定期的に専門医の診察を受けましょう。
後縦靱帯骨化症の初期症状
後縦靱帯骨化症はゆっくり進むため、初期段階では症状に気づきにくい特徴があります。注意が必要な初期症状は以下の4つです。
- 手足のしびれ・痛み
- 首のこり
- 歩行時のふらつき
- 指先を使った動作が困難
手足のしびれ・痛み
後縦靱帯骨化症でよく見られる初期症状が、手足のしびれや痛みです。硬くなった靱帯によって神経の通り道が狭くなり、脊髄が圧迫されることで起こります。指先や足先がジンジン、ピリピリとした違和感を覚えるようになります。
腕や足に鋭い痛みが走ることもあり、進行すると皮膚の感覚が鈍くなり、水やお湯の温度がわかりにくくなることもあります。はじめは片側だけに出ることが多いですが、病気が進むにつれて両方の手足に広がる場合があります。
こうしたしびれや痛みは自然に良くなることが少なく、放置すると日常生活に支障をきたす可能性があります。症状が続く場合は早めに医師へ相談し、原因を確かめて適切な治療を受けることが大切です。
首のこり
何気ない首のこりや痛みも、後縦靱帯骨化症が原因の場合があります。症状の特徴は以下のとおりです。
- 痛む範囲:首筋だけでなく肩や背中まで広がる
- 動きの制限:首を前後左右に動かすのが硬くなる
- しびれの誘発:動かすと手や腕にしびれや痛みが出る
- 症状の持続:マッサージで一時的に和らいでも再発する
靱帯が硬くなると首の動きが悪くなり、筋肉に負担がかかります。強いこりや痛みを感じている方は注意が必要です。放置すると症状が慢性化する場合や、重大な病気が隠れていることもあるため、原因を見極めて適切に対処することが大切です。
以下の記事では、首筋が痛いときに考えられる原因やセルフケア、注意すべき危険な症状について解説しています。
>>首筋が痛いときの原因と対処法!放置すると危険な症状も解説
歩行時のふらつき
後縦靱帯骨化症によって足のしびれや筋力低下が起こり、歩行が不安定になることがあります。症状の特徴は以下のとおりです。
- つまずきやすい:平らな道や何もない所でつまずく
- 階段が怖い:上り下りの際に足元が不安で手すりを必要とする
- 歩き方が変化する:足がもつれ、歩き方を家族から指摘される
- 速く歩けない:小走りが難しく、スリッパが脱げやすくなる
後縦靱帯骨化症の方が転倒すると脊髄に強い負担がかかり、症状が進行する場合があります。歩行中のふらつきは転倒のリスクとなるため、特に注意が必要です。
指先を使った動作が困難
手を動かす神経が圧迫されると、指先を使った細かな作業が難しくなることがあります。症状の特徴は以下のとおりです。
- 食事:箸で食べ物をつかめず、こぼしやすい
- 文字:ペンをうまく握れず、字が震える
- 着替え:ボタンの着脱に時間がかかる
- その他:小銭を取り出せず、キャップが開けにくい
加齢のせいと思いがちですが、脊髄が圧迫されている可能性があるため注意が必要です。
後縦靱帯骨化症の診断方法
後縦靱帯骨化症を正確に診断するためには、複数の検査で背骨の状態を詳しく調べることが重要です。主な検査は以下の3つです。
- レントゲン(X線)検査
- CT検査
- MRI検査
レントゲン(X線)検査は、背骨の「骨組み」を外側から確認する検査です。後縦靱帯の骨化(骨化巣)の有無や、背骨全体のバランスをチェックします。初期の小さな骨化は見つけにくいことがあるため、注意が必要です。
CT検査は、骨を輪切りにした断面や3D画像を用いて確認する検査です。レントゲンではわかりにくい骨化した靱帯の形や大きさ、脊柱管の狭さの評価が期待できます。手術を検討する際は、CTの情報を元に治療計画を立てることがあります。
MRI検査は、神経(脊髄)や椎間板など、柔らかい組織の状態を詳しく見る検査です。骨化した靱帯が神経を圧迫する程度や、神経に損傷が起きていないかも確認します。症状の原因を突き止め、治療方針を決めるうえで重要です。
医師が検査で得られた情報をもとに総合的に判断し、初めて正確な診断が下されます。最近の研究でも、CTやMRIなどの画像診断が治療計画に必要であると報告されています。
背骨や椎間板の変性は後縦靱帯骨化症に限らず、椎間板ヘルニアの発症リスクにも深く関係しています。生活習慣や体質によってもリスクが高まるため、あらかじめ特徴を理解しておくことが予防につながります。以下の記事では、椎間板ヘルニアになりやすい人の特徴やリスク要因、日常でできる予防法を解説しています。
>>椎間板ヘルニアになりやすい人の特徴とは?リスクを高める要因と予防法を解説
進行を緩やかにする治療法
後縦靱帯骨化症は適切な治療で病気の進行を穏やかにし、つらい症状を和らげる効果が期待できます。主な治療法について、以下の2種類を解説します。
- 保存療法:薬物療法やリハビリテーション
- 手術療法:頚椎椎弓形成術(後方手術)や前方除圧固定術
保存療法:薬物療法やリハビリテーション
症状が軽い場合や手術を希望されない場合は、保存療法から始めます。保存療法で行う薬物療法は以下のとおりです。
- 消炎鎮痛剤(NSAIDs):痛みや炎症を抑え、首や手足の痛みを和らげる
- 筋弛緩薬:硬く緊張した首や肩、背中の筋肉をほぐす
- ビタミンB12製剤:圧迫によって傷ついた末梢神経の回復を助ける
- 神経障害性疼痛治療薬:神経由来のしびれや痛みを和らげる
薬と合わせて行うリハビリテーションとして、以下が挙げられます。
- 装具療法:頸椎カラーなどを使って首を安静に保ち、神経への負担を減らす
- 温熱療法:首まわりを温めて血行を促し、筋肉のこわばりや痛みを和らげる
- 運動療法:ストレッチや軽い運動を行い、首や肩の柔軟性と筋力を保つ
保存療法で症状が落ち着いている間も、定期的に診察や画像検査を受けましょう。
手術療法:脊柱管拡大術や前方除圧固定術
保存療法で症状が改善しない場合や、手足の麻痺が進行した場合は、手術療法を検討します。骨化した場所や大きさ、形によって選択される手術が異なります。主な手術方法は以下の2つです。
| 切開場所 | 手術名 | 特徴 |
| 首の後ろ側 | ・椎弓形成術 | ・脊柱管の後方の骨(椎弓)を削って狭くなった脊柱管を拡大 ・広範囲の圧迫に対応 |
| 首の前側 | 前方除圧固定術 | ・骨化した靱帯を前方から直接除去することが可能 ・骨や金属器具で固定 |
神経の通り道が狭くなっている重度の圧迫では、首の前側の切開を推奨する場合があります。近年の研究では、患者さん一人ひとりの状態に合わせた手術計画の重要性が示されています。
手術の有無にかかわらず首の痛みは日常生活で悪化することがあり、動作や姿勢が症状に影響します。特に首を後ろに倒したときの痛みは注意が必要で、背景にさまざまな原因が隠れていることもあります。以下の記事では、首を後ろに倒すと痛みが出る原因や、症状に応じた治し方・ストレッチについて解説しています。
>>首を後ろに倒すと痛い原因は?痛みがあるときの治し方やストレッチを解説
治療後・日常生活で気をつけたいこと
後縦靱帯骨化症の手術や保存療法で症状が和らいでも、治療後の状態維持が重要です。日々の過ごし方で知っておきたいこととして、以下の4つを解説します。
- 転倒予防
- 首に負担をかけない姿勢
- 症状悪化を防ぐ生活習慣
- 指定難病の医療費助成制度や社会的支援
転倒予防
後縦靱帯骨化症の方は、軽く転んだだけでも脊髄に深刻なダメージにつながるため注意が必要です。ご自宅でできる転倒予防策は以下のとおりです。
- 床の安全確保:物を置かず、コードや新聞は片付ける
- 段差対策:敷居やカーペットの段差をなくす、スロープを使う
- 滑り防止:水回りに滑り止めマット、滑りにくい靴下やスリッパを使う
- 明るさ確保:廊下や階段、寝室に足元灯を置く
- 手すり設置:玄関や廊下、階段、トイレなどに付ける
- 福祉用具:杖や歩行器を体に合ったものを使う
日々の生活を意識し、転倒のリスクを下げることが大切です。できるところから少しずつ取り入れて、安全な生活スペースを作りましょう。
首に負担をかけない姿勢
骨化が起きている首の骨(頸椎)に、過度な負担や衝撃をかける動作には注意が必要です。首に負担をかけないポイントは、以下のとおりです。
- 座っているとき:スマホや本は目の高さに上げ、椅子に深く腰かけて背筋を伸ばす
- 寝るとき:枕は首から肩の自然なカーブを保てる高さを選び、高すぎや低すぎを避け、うつ伏せ寝はしない
- 日常の動作:後ろを振り向くときは体ごと動かし、床の物は膝と股関節を曲げて拾う
首をポキポキと鳴らす行為は、骨化した部分に強い力を加える場合があります。症状を悪化させる可能性があるため避けましょう。
症状悪化を防ぐ生活習慣
後縦靱帯骨化症の進行を緩やかにするには、日々の生活習慣を見直すことが大切です。ウォーキングや軽いストレッチで筋力を維持しつつ、転倒の危険がある激しい運動は避けましょう。食事は野菜や魚、大豆製品などを取り入れ、骨や筋肉、神経の健康を保つと同時に血糖値の管理にも気を配ることが重要です。
定期的に医療機関を受診し、レントゲンやCTで骨化の状態を確認することも欠かせません。自己判断で通院をやめてしまうと、進行を見逃す恐れがあります。無理のない範囲で生活習慣を整えることが、安心して毎日を過ごすための第一歩です。
指定難病の医療費助成制度や社会的支援
後縦靱帯骨化症は、国が定める「指定難病」の一つです。治療にかかる経済的な負担を軽くするため、公的な支援制度を利用できる場合があります。主な制度は以下のとおりです。
| 制度 | 特徴 | 相談・申請窓口 |
| 指定難病医療費助成制度 | 医療費の自己負担額に上限が設けられる | 地域の保健所 |
| 身体障害者手帳 | 基準を満たすと交付され、税控除や交通、施設割引が受けられる | 市区町村の障害福祉担当窓口 |
| 障害年金 | 病気で生活や就労に制限がある場合、20~64歳の方でも年金を受給できる | ・年金事務所 ・年金相談センター |
各支援制度は、ご自身で申請手続きを行う必要があります。制度を上手に活用し、安心して治療に専念できる環境を整えましょう。
まとめ
後縦靱帯骨化症は、背骨を支える後縦靱帯が硬くなり、脊髄を圧迫する国の指定難病です。全国で約36,000人が医療費助成を受けており、ゆっくり進行するため気づきにくいのが特徴です。
主な初期症状は、以下のとおりです。
- 手足のしびれ・痛み
- 首のこり
- 歩行時のふらつき
- 指先の動作困難
原因は解明されていませんが、複数の要因が絡み合っている可能性があります。レントゲン検査やCT検査、MRI検査で診断され、保存療法や手術療法の治療が検討されます。転倒の予防や首に負担をかけない姿勢、バランスの良い食事、定期的な受診を心がけましょう。
手足のしびれや歩きにくさを感じたら、自己判断せず専門医へご相談ください。当院(大室整形外科 脊椎・関節クリニック)は、脊椎センター・人工関節センターの2つを軸にしたクリニックです。腰や関節の痛み、リハビリなどでお悩みの方へ、専門医が丁寧に相談に応じます。兵庫県のJR姫路駅からは無料送迎バスを利用できますので、お気軽にご来院ください。
>>診察のご案内
参考文献
- e-Stat 政府統計の相互窓口:特定医療費(指定難病)受給者証所持者数
- 理化学研究所:後縦靭帯骨化症の原因遺伝子を発見
- Cui S, Li J, Yu X, Zhao H, Jian F.Ossification of posterior longitudinal ligament of the cervical spine: A review article.Neurocirugia,2025,36,5,p.500668