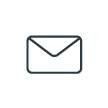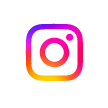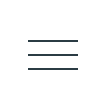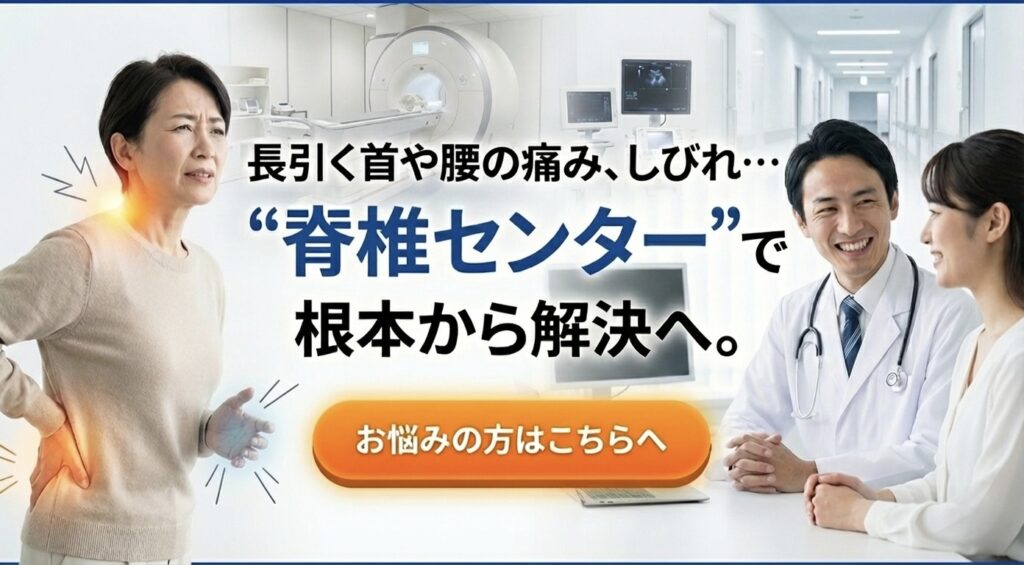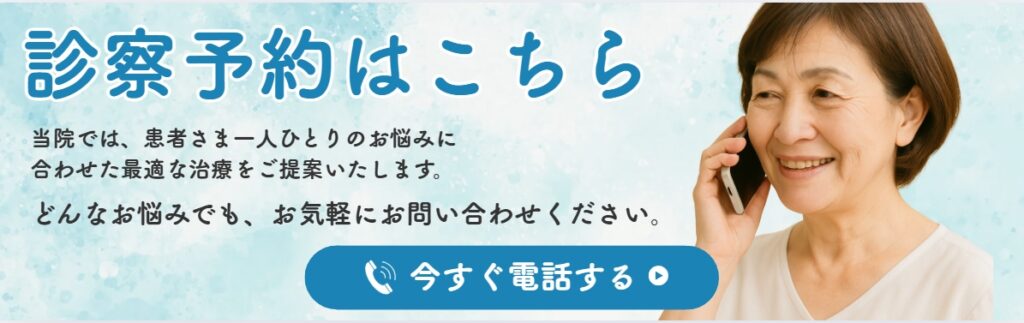腰椎すべり症は手術すべきか?判断基準と治療の選択肢を医師が解説
腰の痛みや足のしびれが続くと、治療のタイミングや手術の必要性に迷う方も多いのではないでしょうか。腰椎すべり症と診断された場合に「手術すべきかどうか」は大きな悩みです。
実は、医師が手術を判断する際には「保存療法で改善が見られない」「日常生活に支障がある」など、明確な基準があります。これを知らずに放置すれば、症状が悪化する恐れもあります。
この記事では、手術が必要とされる判断基準や治療の選択肢を、医師の視点からわかりやすく解説します。負担の少ない手術法や費用・制度の情報も網羅しています。ご自身の状況と照らし合わせ、後悔のない最適な治療を選択するために、ぜひ最後までご一読ください。
当院では、腰椎すべり症をはじめとした整形外科疾患に対し、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。不安な症状がある方も安心してご相談いただけるよう、以下の記事で診察の流れや受付方法を詳しくまとめています。
>>診察のご案内について

記事監修:川口 慎治
大室整形外科 脊椎・関節クリニック 医師
経歴:
徳島大学医学部卒業後、洛和会音羽病院に勤務
京都大学医学部整形外科学教室入局
学研都市病院脊椎脊髄センター勤務
2023年より 大室整形外科 脊椎・関節クリニック勤務
専門分野:脊椎・脊髄外科
資格:
日本専門医機構認定 整形外科専門医
日本整形外科学会認定 脊椎脊髄病医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科指導医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科専門医
腰椎すべり症で手術を判断する3つの基準
腰椎すべり症で手術を判断する3つの基準は以下のとおりです。
- 保存療法で症状が改善しない
- 日常生活への支障(歩行困難・排尿障害など)
- MRI検査結果(脊椎の不安定性・神経の圧迫度)
保存療法で症状が改善しない
腰椎すべり症の治療は、まず「保存療法」から始めます。薬やリハビリテーションなどで症状を和らげ、日常生活を快適にすることを目的とします。保存療法の主な方法は以下のとおりです。
- 薬物療法:痛みや炎症を抑える飲み薬・貼り薬を使用
- リハビリテーション:筋肉をほぐし、体幹を鍛えて腰椎を安定化
- ブロック注射:神経の近くに薬を注射し、強い痛みを抑える
- 装具療法:コルセットを用いて腰への負担を軽減
上記を組み合わせて症状の改善を目指しますが、保存療法はあくまで「対症療法」であり、骨のずれ自体を治すものではありません。そのため、3か月以上続けても改善がない場合や症状が悪化する場合には、手術を検討する目安です。これは、神経のダメージが慢性化するのを防ぐためでもあります。
以下の記事では、腰椎すべり症の主な原因や、年代によって異なるリスク、治療法の選択肢をわかりやすく解説しています。
>>腰椎すべり症の原因と特徴!年代別リスクと治療法を解説
日常生活への支障(歩行困難・排尿障害など)
手術を検討するうえで重要なのは、症状の強さに加えて「生活への影響」も重要です。我慢できると思っても、以下のサインがあれば生活の質(QOL)は大きく低下しています。
- 歩行に問題がある:少し歩くと足がしびれて痛み、しゃがんで休まないと歩けない(間欠性跛行)
- 足の感覚や力に異常がある:階段が怖い、スリッパが勝手に脱げる、段差でつまずきやすい
- 排尿・排便の異常:尿が出にくい、頻尿、残尿感、便秘、尿失禁や便失禁
- 家事・趣味が困難:立ち仕事や掃除がつらい、ゴルフや散歩が難しい
足の麻痺や排尿・排便の異常は「馬尾神経」が強く障害されている危険なサインです。この場合は「絶対的適応」と呼ばれ、緊急手術が必要になるケースもあります。
以下の記事では、腰椎すべり症の悪化を防ぐために、日常生活で避けるべき行動や注意点を詳しく解説しています。知らずにやっている行動が症状を悪化させるリスクもあるため、ぜひご確認ください。
>>腰椎すべり症でやってはいけないこと!悪化を防ぐ対策や生活のポイント
MRI検査結果(脊椎の不安定性・神経の圧迫度)
手術を検討する際には、画像検査による客観的な情報が不可欠です。特にレントゲンとMRIは、症状の原因や重症度を見極めるために重要です。どのような検査で何を確認するかは以下のとおりです。
- レントゲン検査:腰椎のずれ(すべりの程度)や、前後に動かしたときの「ぐらつき(不安定性)」を評価
- MRI検査:神経や椎間板の状態を詳しく確認し、脊柱管の狭さや神経圧迫の程度を立体的に把握
上記の検査で不安定性が強い・神経圧迫が明らかな場合は、手術の必要性が高いと判断されます。検査結果だけでなく、保存療法の効果や日常生活への支障、患者さんの希望を総合的に考慮し、最適な治療方針を決めていきます。
以下の記事では、腰部脊柱管狭窄症の代表的な症状や、痛み・しびれが起こる原因、治療の選択肢などを詳しく解説しています。
>>腰部脊柱管狭窄症の症状とは?痛くなる原因やしびれの特徴、治療法まで解説
腰椎すべり症の主な治療法
腰椎すべり症の主な治療法は、以下のとおりです。
- 保存療法(薬・リハビリテーション・ブロック注射)
- 手術療法(除圧術・固定術)
- 低侵襲手術(内視鏡・OLIF/XLIF・PPS)
保存療法(薬・リハビリテーション・ブロック注射)
腰椎すべり症では、まず手術をせず体への負担が少ない保存療法を行うのが基本です。骨のずれ自体を治すことはできませんが、多くの方が数か月の継続で症状改善が期待できます。代表的な方法は以下のとおりです。
| 治療法 | 内容 |
| 薬物療法 | ・消炎鎮痛剤で炎症を抑え腰痛を軽減 ・神経障害性疼痛治療薬でしびれやピリピリ感を改善 |
| リハビリテーション | ・ストレッチで筋肉の緊張を和らげ負担を軽減 ・筋力トレーニングで体幹を鍛えて背骨を安定 |
| ブロック注射 | 強い痛みの原因になる神経近くに麻酔薬を注入し、痛みを直接緩和 |
| 装具療法 | コルセットを装着し腰を安定させ、動きを制限して負担を軽減 |
保存療法は「症状を和らげること」が目的で、骨のずれを根本的に治すわけではありません。3か月程度続けても改善が乏しい場合や生活に大きな支障がある場合には、手術を検討することになります。
手術療法(除圧術・固定術)
保存療法を3か月以上続けても症状が改善しない場合や、重い神経症状がある場合には、手術療法を検討します。主な手術療法として、以下の2つの方法があり、背骨のずれや不安定性の程度によって選択されます。
| 手術方法 | おすすめな方 | 期待できること |
| 除圧術 | 背骨の不安定性が少ない方 | 神経への圧迫を取り除き、痛みやしびれを和らげる |
| 固定術 | 背骨の不安定性が大きい方 | 背骨を安定させ、動作時の痛みを根本から改善する |
低侵襲手術(内視鏡・OLIF/XLIF・PPS)
従来法に比べ、体への負担が少なく回復が早いのが低侵襲手術の最大の特徴です。近年は内視鏡に加え、腰の筋肉への侵襲をできるだけ小さくしながら行う固定術(OLIF/XLIF)や経皮的に挿入できるスクリュー(PPS)も選択肢として広がっています。それぞれの特徴は以下のとおりです。
| 手術法 | 特徴 | メリット |
| 内視鏡手術 | 数cmの小切開からカメラと細い器具を挿入し、モニター映像を見ながら精密に操作 | ・傷が小さいため回復が早い ・術後の痛みが少ない |
| OLIF/XLIF | ・お腹や背中を大きく切らず、側方(体の横)から椎間板に到達して固定を行う手術法 ・神経を直接触らずに椎間板を入れ替えるため、神経損傷リスクが少ない |
・低侵襲で出血量が少ない ・術後の回復が早く、早期離床が可能 ・大きなケージを挿入でき、強固な固定と良好な矯正効果が得られる |
| PPS | ・皮膚に小さな切開をあけ、X線透視やナビゲーションを用いて椎弓根スクリューを挿入する手術法 ・従来の大きな切開を伴う固定術に比べて筋肉の損傷が少ない |
・筋肉へのダメージが少なく、術後の疼痛が軽減 ・回復が早く、入院期間の短縮が期待できる ・他の低侵襲手術(OLIF/XLIFなど)と組み合わせることで、より安定した固定が可能 |
低侵襲手術は、痛みの軽減・早期退院・社会復帰のしやすさという点で大きな利点があります。合併症のリスクは従来法と大きな差はなく、安全性も確認されています。研究によると、ロボット支援手術は、精密性と安全性を兼ね備えた新しい選択肢として期待されています。
手術を選ぶ前に知っておくべきこと
手術のメリットだけでなく、リスクも理解することが大切です。手術を選ぶ前に知っておくべきことは以下のとおりです。
- 手術のメリット(痛み改善・QOL向上)
- 手術のリスク(合併症)
- 入院期間と社会復帰までのスケジュール
- 手術費用:利用可能な制度(高額療養費・傷病手当金)
手術のメリット(痛み改善・QOL向上)
手術の最大のメリットは、神経への圧迫を直接取り除けることです。これにより、保存療法では改善が難しかった症状が和らぐ可能性があります。手術によって改善できる可能性がある点は以下のとおりです。
- 激しい痛みの軽減:お尻や足に走る強い痛みやしびれが和らぐ
- 歩行能力の向上:休み休みしか歩けなかった状態(間欠性跛行)が改善し、長距離を歩けるようになる
- 神経症状の改善:足に力が入りにくい、感覚が鈍いといった麻痺症状が改善する
- 活動範囲の拡大:痛みで諦めていた家事・仕事・趣味を再び楽しめるようになる
上記の改善は、身体的な負担を軽くするだけでなく、気持ちを前向きにし、生活の質を高める効果につながります。旅行やスポーツの再開など、活動的な生活を取り戻せる可能性も広がります。
手術のリスク(合併症)
どの手術でもリスクはゼロにはできません。手術を検討する際は、期待できる効果と起こりうるリスクを両方理解し、納得して判断することが大切です。主なリスクは以下のとおりです。
- 感染症:手術部位に細菌が入り、腫れや発熱を起こすことがある
- 神経の損傷:まれに神経を傷つけ、しびれや麻痺が悪化することがある
- 血栓症(エコノミークラス症候群):長時間動かないことで足の血管に血栓ができる
- 固定術に伴う問題:金属で背骨を固定した場合、隣の背骨に負担がかかり「隣接椎間障害」を起こす可能性がある
リスクを最小限に抑えるため、当院は予防策と万全の安全体制を整えています。ご不安な点があれば、小さなことでも遠慮なくご相談ください。
入院期間と社会復帰までのスケジュール
手術後の入院や復帰の目安は、手術法と回復のスピードによって異なります。以下に一般的なスケジュールをまとめました。
| 手術方法 | 入院期間の目安 | 仕事復帰の目安(デスクワーク) | 仕事復帰の目安(体を動かす仕事) |
| 除圧術(内視鏡など) | 約1~2週間 | 約2週間~1か月 | 約1~3か月 |
| 固定術(スクリュー固定など) | 約2~4週間 | 約1~3か月 | 約3~6か月 |
スケジュールに関して知っておきたいことは次のとおりです。
- 上記はあくまで目安であり、年齢・持病・回復具合によって個人差がある
- 入院中は理学療法士とともにリハビリテーションを行い、筋力回復を目指す
- 退院後もしばらくは重い荷物や体をひねる動作を避ける
焦らず、ご自身の体の状態に合わせて一歩ずつ日常生活に戻りましょう。
手術費用:利用可能な制度(高額療養費・傷病手当金)
日本の医療保険制度を活用すれば、手術費用の自己負担を大きく抑えることができます。代表的なものに「高額療養費制度」と「傷病手当金」があります。
高額療養費制度は、1か月の医療費が自己負担の限度額を超えた場合、その超過分が払い戻される仕組みです。事前に「限度額適用認定証」を申請しておけば、窓口での支払いも上限額までに軽減されます。
傷病手当金は、会社員や公務員が病気やけがで休職し、給与が減った場合に支給される制度です。経済的な不安を和らげる支えとなるため、加入している健康保険組合や勤務先に事前確認をしておくことが大切です。
これらの制度をうまく活用することで、経済的な負担を軽減し、安心して治療に専念することができます。当院では身体面だけでなく経済面にも配慮し、患者さんに最適な治療を提案しています。費用に不安がある方も、遠慮なくご相談ください。
まとめ
大切なのは、すぐに手術を決めるのではなく、まずは薬やリハビリテーションなどの「保存療法」を試すことです。3か月以上続けても症状が改善しない場合や、歩行困難・排尿障害など生活に大きな支障が出ている場合は、手術が有効な選択肢です。
近年では、内視鏡など体への負担が少ない手術も進歩しています。ご自身の症状、ライフスタイル、そして手術のメリット・リスクを総合的に理解したうえで、納得できる治療法を選ぶことが何よりも重要です。
一人で抱え込まず、まずは専門の医師にあなたの不安や希望を遠慮なく相談しましょう。当院の受診をご希望の方は、まずはお電話にてご予約ください。詳しいアクセス方法は、当院の公式サイトをご覧ください。
>>大室整形外科へのアクセスはこちら
参考文献
Gu X, Zhang S, Liu Y, Qi J, Gu Y, Ma W. Mid-term efficacy of non-contact orthopedic robot navigation in the treatment of lumbar spondylolisthesis. BMC Musculoskelet Disord, 2024, 25(1), p.898.