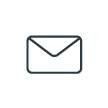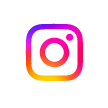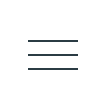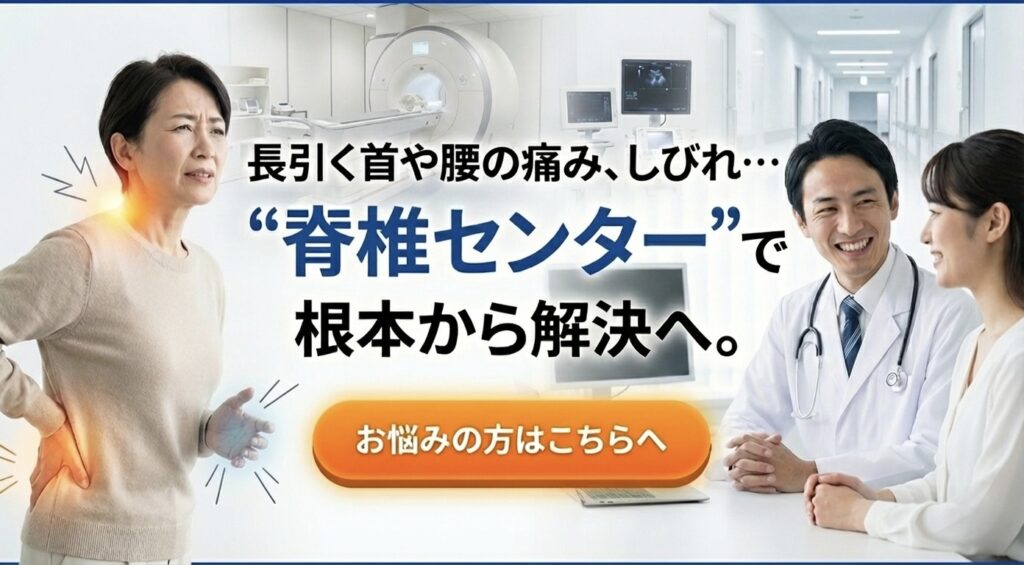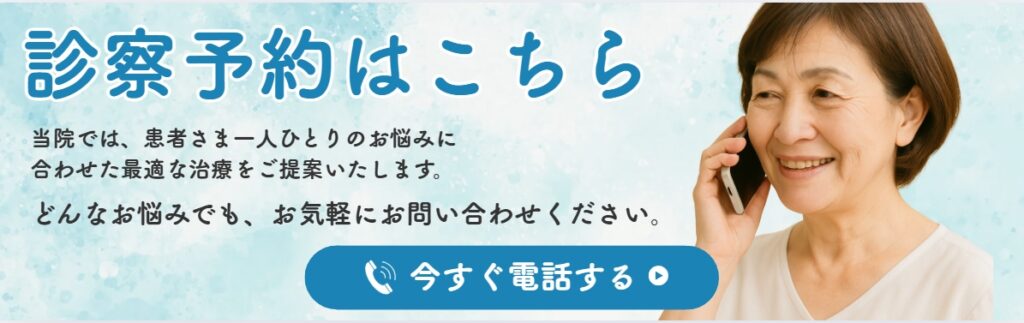腰部脊柱管狭窄症の手術成功率は?リスクや回復までの流れを解説
腰部脊柱管狭窄症と診断されて手術を考えるとき、不安を感じるのは当然のことです。一般的に手術の成功率は概ね70〜80%と高いとされていますが、数字だけで判断するのは避けましょう。再発して再手術が必要になる例もあり、その際は改善が得られにくい傾向や、硬膜損傷といった合併症リスクがあることも報告されています。
この記事では、手術の成功率の本当の意味から、後悔しないために知っておくべきリスク、回復までの具体的な流れを解説します。ご自身が納得して治療に臨むために、ぜひ参考にしてください。
当院では、腰部脊柱管狭窄症をはじめとした整形外科疾患に対し、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。不安な症状がある方も安心してご相談いただけるよう、以下の記事で診察の流れや受付方法を詳しくまとめています。
>>診察のご案内について

記事監修:川口 慎治
大室整形外科 脊椎・関節クリニック 医師
経歴:
徳島大学医学部卒業後、洛和会音羽病院に勤務
京都大学医学部整形外科学教室入局
学研都市病院脊椎脊髄センター勤務
2023年より 大室整形外科 脊椎・関節クリニック勤務
専門分野:脊椎・脊髄外科
資格:
日本専門医機構認定 整形外科専門医
日本整形外科学会認定 脊椎脊髄病医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科指導医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科専門医
腰部脊柱管狭窄症の手術成功率は70〜80%
腰部脊柱管狭窄症の手術は、症状の改善や生活の質の向上を目指す治療であり、多くの報告で成功率は70〜80%とされています。手術の成功は「症状の改善」「生活の質(QOL)の向上」「患者さんの満足度」の3点から総合的に判断されます。ただし、状態により効果に差があり、再手術では成功率が下がる傾向です。
成功率に影響を与える要因については以下のとおりです。
- 圧迫が軽度〜中等度なら成功率は高い
- 神経が長期間強く圧迫されていた場合、回復が穏やか
- 再手術は初回より成功率が下がりやすい
そのため、初回の治療選択とタイミングが重要です。専門医と相談のうえ、適切な判断を行うことが回復への第一歩となります。
以下の記事では、腰部脊柱管狭窄症の代表的な症状や、痛み・しびれが起こる原因、治療の選択肢などを詳しく解説しています。
>>腰部脊柱管狭窄症の症状とは?痛くなる原因やしびれの特徴、治療法まで解説
腰部脊柱管狭窄症手術のリスク
どのような手術にも「100%安全」ということはありません。腰部脊柱管狭窄症手術のリスクとして、以下の3つを解説します。
- 合併症リスク(神経損傷・感染症・血栓症など)
- 術後のしびれ・痛み再発
- 再手術の可能性
合併症リスク(神経損傷・感染症・血栓症など)
合併症は、誰にでも起こるわけではありませんが、可能性はゼロではありません。以下に主な合併症と注意点をまとめます。
| 合併症の種類 | 起こりうること | 注意が必要なケース |
| 神経損傷 | 足のしびれ・麻痺・筋力低下 | まれだが、すべての患者さんに可能性あり |
| 感染症 | 傷口の化膿、腫れ、膿の排出 | 糖尿病・高齢者など免疫力が低下している場合 |
| 血栓症 | 血管内に血栓ができ肺に詰まる(肺塞栓症) | 術後に長時間安静が続く場合 |
神経損傷は、手術中に神経やその周囲を操作するため、まれに損傷することがあります。細心の注意を払い、顕微鏡を使用し、術者が細心の注意を払って手術を行います。
感染症は、術後の傷口から細菌が入ることで発生します。持病のある方や高齢の方は特に注意が必要で、清潔な手術環境と抗生物質の使用でリスクを抑えます。
血栓症は、長時間の安静で足の静脈内に血のかたまりができ、肺の血管に詰まることがあります。予防のため、術後は早期からリハビリテーションを開始します。
術後のしびれ・痛み再発
手術により神経の圧迫は取り除かれ、多くの場合、歩行時の痛みは大きく改善します。ただし、すべての症状が完全になくなるわけではなく、特にしびれに関しては術後も残ることがあります。
長期間圧迫されていた神経はダメージを受けており、術後すぐに回復するとは限りません。しびれは術後3-6ヶ月で大幅に軽減するものの、完全に消失しない軽度のしびれが1年後にも残る方は50~75%程度と報告されており、年齢や発症からの期間なども影響します。これは手術の失敗ではなく、傷ついた神経が少しずつ回復していく過程で起こる自然な反応です。
再手術の可能性
一度手術を受けても、数年後に症状が再び現れることがあります。これを「再狭窄」と呼び、手術した部位の上下に新たな負担がかかることで生じることがあります。再手術は初回よりも難易度が高く、症状の改善が限定的になる場合があります。手術の回数が増えるほど、治療効果が得られにくくなる傾向です。
そのため、初回の治療法の選択や手術のタイミングは重要です。患者さん一人ひとりの症状や生活背景をふまえて、慎重に判断することが大切です。不安な点があれば、いつでもご相談ください。
手術を受けるべき判断基準
手術を受けるべき判断基準は、以下のとおりです。
- 保存療法(薬物療法・ブロック注射)が効かない場合
- 日常生活に支障が出る場合
体への負担が少ない治療から始め、その効果を見極めます。納得して治療に臨むための参考にしてください。
保存療法(薬物療法・ブロック注射)が効かない場合
腰部脊柱管狭窄症の治療は、まず手術以外の「保存療法」から始めるのが一般的です。症状の緩和を目的とした主な保存療法は以下のとおりです。
- 薬物療法:血流を改善する薬や、痛みを抑える薬を使用
- 神経ブロック注射:神経の近くに薬剤を注射し、痛みや神経の興奮を抑える
- リハビリテーション:ストレッチや筋トレを行い、腰への負担を軽減する
- 装具療法:コルセットなどで腰を支え、安定させる
保存療法を数か月続けても症状が改善しない・悪化する場合は、薬やリハビリテーションだけでは対応できない状態の可能性があります。その際に手術を検討します。ただし、手術はあくまで最終手段です。
つらい症状は我慢せず、医師と一緒に治療効果を確認しながら、最適なタイミングと方法を選びましょう。
日常生活に支障が出る場合
手術を検討するかどうかは、症状によって日常生活にどれだけ影響が出ているかが判断基準になります。次のようなことに心当たりがある方は、医師への相談をおすすめします。
- スーパーでの買い物がつらい(歩くと足が痛み、何度も休憩が必要)
- 料理や洗い物など、短時間立っているだけで足がしびれる
- 夜間の痛みやしびれで眠れない
- 旅行や趣味など、楽しみをあきらめるようになった
- 仕事に集中できず、このまま続けられるか不安を感じる
以下のような症状は、神経が重度に圧迫されている「馬尾(ばび)症候群」と呼ばれる危険な状態です。
| 症状の内容 | なぜ危険か |
| 尿が出にくい、漏れてしまう | 排泄をコントロールする神経が麻痺しかけている |
| お尻まわりの感覚異常(しびれ・灼熱感) | 感覚を伝える重要な神経に異常が起きている |
| 足に力が入らない(つまずきやすい等) | 歩行に関わる神経が麻痺し、歩けなくなる可能性あり |
上記の症状は、放置すると神経のダメージが回復困難になる恐れがあります。「まだ大丈夫」と我慢せず、早めに専門医へご相談ください。当院では「再び立ち上がり、人生を楽しむ」ことを目指し、必要に応じて手術という選択肢も含めて、最適な治療をご提案しています。
以下の記事では、特に朝起きたときに感じる腰の痛みについて、考えられる原因や対処法を詳しく解説しています。
>>朝起きると腰が痛いのは病気のサイン?考えられる原因と治療法を解説
手術方法の主な選択肢
手術の目的は、神経を圧迫している原因を確実に取り除くことです。手術方法の主な選択肢として、以下の2つがあります。
- 従来法(椎弓切除術)
- 低侵襲手術(内視鏡)
従来法(椎弓切除術)
椎弓切除術は、昔から行われている確実性の高い手術方法です。背中を数センチ切開し、医師が直接目で確認しながら、神経を圧迫している骨(椎弓)や靭帯を取り除きます。広い範囲にわたる狭窄や、複雑な状態にも対応できます。
椎弓切除術の特徴を以下の表にまとめています。
| 区分 | 特徴 | 解説 |
| メリット | ・確実性が高い ・幅広い症状に対応 |
・医師が直接目で見て、神経の圧迫を確実に取り除ける ・狭窄の範囲が広い場合や、複雑なケースでも対応可能 |
| デメリット | ・体への負担が大きい ・回復に時間がかかる |
・皮膚や筋肉を大きく開くため、手術後の痛みが出やすい傾向 ・入院期間が長くなり、社会復帰までに時間を要する場合あり |
椎弓切除術は、長年続いた痛みやしびれの根本的な原因を取り除くことを目的としています。体への負担が大きいため、術後の経過や回復期間も考慮しながらの選択が重要です。
低侵襲手術(内視鏡)
「低侵襲」とは、体への負担が少ない治療を意味します。内視鏡手術はその代表で、背中に1〜2cmほどの小さな穴を開け、カメラと器具を挿入して神経の圧迫を取り除きます。筋肉への損傷が少なく、痛みや回復への影響が抑えられるのが特徴です。
内視鏡手術の特徴を以下の表にまとめています。
| 区分 | 特徴 | 解説 |
| メリット | ・体への負担が少ない ・回復が早い |
・傷口が小さく、筋肉をほとんど傷つけずに済むため、術後の痛みが軽い ・出血が少なく、入院期間が短くて済み、早期の社会復帰が可能 |
| デメリット | ・適応が限られる ・高度な技術が必要 |
・狭窄の場所や状態によっては、この手術法が適さない場合あり ・専門的な技術や設備が必要なため、すべての病院で受けられるわけではない |
出血を抑えるために「流動性ゼラチン」などの止血材を活用することで、手術時間や出血量の軽減にもつながり、安全性がさらに高まっています。
ただし、誰にでも適応できる方法ではないため、手術法の選択は症状や体の状態を見ながら慎重に判断する必要があります。まずは専門医にご相談ください。
手術後の回復期間における生活上の注意点
手術はゴールではなく、痛みのない快適な生活を取り戻すための新しいスタートです。手術後の回復期間における生活上の注意点として、以下の4つを解説します。
- 入院期間の目安
- 退院後のリハビリテーション
- 活動再開の目安(仕事・運転など)
- 術後の再発予防のためにできること
入院期間の目安
手術後の入院期間は、手術の種類や回復のスピードによって異なります。以下は一般的な目安です。
- 従来法(椎弓切除術):約2〜3週間
- 低侵襲手術(内視鏡):数日(1泊2日)
当院では、手術翌日からリハビリテーションを開始します。最初は足首を動かすなどの軽い運動から始め、段階的に歩行訓練へと進みます。高齢の方や持病のある方は回復にやや時間がかかることがありますが、ご自宅で安心して生活できるよう、医師・看護師・理学療法士が連携してサポートします。
不安やご質問がある場合は、いつでもお気軽にご相談ください。
退院後のリハビリテーション
退院後もリハビリテーションを継続することは、機能の回復と再発の予防の両面で重要です。焦らず、段階的に無理のないペースで進めていくことが大切です。リハビリテーションの時期ごとの計画目安として、以下にまとめています。
| 時期 | 目標 | 内容 | 注意点 |
| 退院直後〜術後1か月 | 日常生活に慣れる | ・家の中での短距離歩行練習 ・家事の再開は無理のない範囲で |
痛みやしびれを感じたらすぐに休む |
| 術後1〜3か月 | 筋力をつけて体を安定させる | ・体幹を鍛える軽い筋トレ ・毎日のストレッチ継続 |
腰を保護するコルセットを着用(3か月程度) |
| 術後3か月以降 | 活動的な生活への復帰 | ・軽いスポーツや趣味の再開 ・日常の活動範囲を広げる |
再開の内容は医師や理学療法士と相談して決定する |
リハビリテーションは、やる気も大切ですが、体の声に耳を傾けることが最優先です。特に退院後の初期は無理をせず、安全に生活に戻ることを第一の目標にしましょう。不安や疑問があれば、医師や理学療法士に気軽に相談してください。
活動再開の目安(仕事・運転など)
「いつから仕事に戻れるか」「運転はいつ再開できるか」などは、よくある質問です。ただし、回復には個人差があるため、再開時期は目安であり、主治医の許可を得てから判断してください。
以下に一般的な目安をまとめていますが、個々の状態で異なる場合があることを理解して確認しましょう。
| 活動内容 | 再開の目安 | 注意点 |
| デスクワーク | 術後2週間〜1か月 | 長時間の座位は避け、30分ごとに立ち上がって軽く体を動かす |
| 軽作業(立ち仕事など) | 術後1〜3か月 | 腰に負担がかからないか様子を見ながら、徐々に作業時間を延ばす |
| 肉体労働 | 術後3〜6か月以降 | 重い物を扱う作業は腰への負担が大きいため、医師と相談しながら慎重に判断する |
| 車の運転 | 術後2週間〜1か月 | 30分以上痛みなく座れ、急ブレーキが安全に踏めることが再開の条件 |
| 趣味(旅行・畑仕事など) | 術後3か月以降 | 長時間の移動や中腰の作業は控え、まずは短時間から徐々に再開する |
手術後、1〜2週間で軽い家事や運転を再開できる方もいますが、順調に回復した場合に限られます。自己判断での再開はリスクを伴うため、必ず医師の診察を受け、適切な指示に従うことが大切です。
無理なく、安心して日常生活に戻るためにも、焦らず段階的な回復を心がけましょう。
以下の記事では、腰への負担を軽減するためのコルセットの効果や正しい使い方について詳しく解説しています。
>>椎間板ヘルニアにコルセットの効果はある?正しい装着法と選び方を徹底解説
術後の再発予防のためにできること
手術で症状が改善しても、再発のリスクはゼロではありません。しかし、日々の生活習慣の見直しにより、再発の可能性を大きく減らすことが可能です。再発予防の習慣チェックリストを、以下の表にまとめています。
| 項目 | 理由(なぜ必要か) | 実践ポイント |
| 正しい姿勢を意識する | 猫背や反り腰は背骨の一部に負担を集中させる | ・椅子に深く腰掛け、背筋を伸ばす ・立つときはお腹に力を入れる |
| 腰に負担をかけない動作 | 腰を曲げて物を持つと、てこの原理で大きな負担がかかる | ・物を拾うときは膝を曲げてしゃがむ ・急なひねり動作は避ける |
| 適度な運動を続ける | 体幹の筋肉は背骨を安定させる働きがあり、腰への負担軽減に重要な役割 | ・ウォーキングなど軽い運動を習慣化 ・医師の許可が出たら筋トレも行う |
| 適正体重を維持する | ・体重1kg増えると、腰への負担は数倍になる ・肥満は再発のリスク |
栄養バランスの良い食事を心がけ、体重を管理する |
手術を良い機会と捉え、ご自身の体と向き合う習慣を身につけることが大切です。再発を防ぐためには、日常生活の意識改革が鍵になります。無理をせず、自分のペースで取り組みましょう。
当院では、退院後の生活指導や運動サポートも行っております。ご不安な点があれば、いつでもご相談ください。
まとめ
手術の成功率は80〜90%と高いですが「痛みがゼロになる」ことだけではなく、つらい症状が和らぎ「生活の質が向上する」ことを指します。一方で、どのような手術にもリスクはあり、再発の可能性もゼロではありません。
手術を受けて終わりではなく、その後のリハビリテーションや生活習慣がとても大切になります。手術は、再びご自身の足で歩き、人生を楽しむための大切な一歩です。
不安や疑問があれば、決して一人で抱え込まず、専門の医師に相談してみましょう。ご自身の状態を正しく理解し、納得のいく治療を選択することが、未来の健康へとつながっていきます。
当院の受診をご希望の方は、まずはお電話にてご予約ください。詳しいアクセス方法は、当院の公式サイトをご覧ください。
>>大室整形外科へのアクセスはこちら
参考文献
- J-STAGE:「腰部脊柱管狭窄症再手術例の検討」
- Thornes E, Ikonomou N, Grotle M. Prognosis of Surgical Treatment for Degenerative Lumbar Spinal Stenosis: A Prospective Cohort Study of Clinical Outcomes and Health-Related Quality of Life Across Gender and Age Groups . Open Orthop J, 2011; 5: .
- Zou, T., Chen, H., Wang, PC. et al. Predictive factors for residual leg numbness after decompression surgery for lumbar degenerative diseases. BMC Musculoskelet Disord 23, 910 (2022).