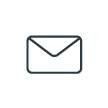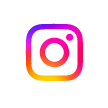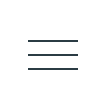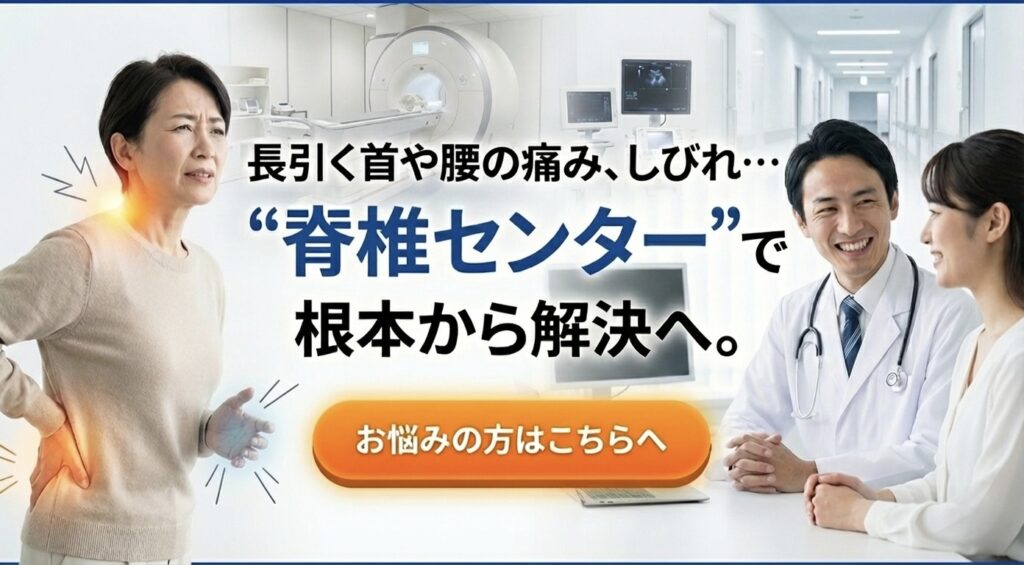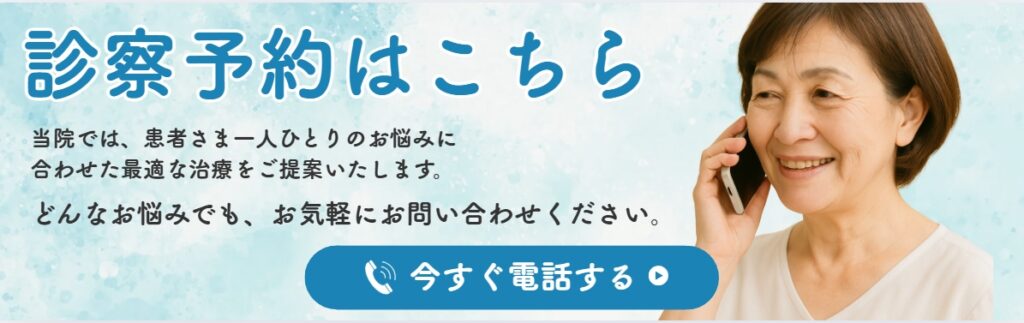頚椎椎間板ヘルニアで仕事は休める?手術後の休む期間や職場復帰のタイミングを解説
首や肩、腕に痛みやしびれが出ている場合、頚椎椎間板ヘルニアの可能性があります。症状が悪化すると日常生活に支障をきたし、仕事を休まざるを得ないケースもあります。この記事では、頚椎椎間板ヘルニアによる休職の目安や経済的支援、職場復帰のタイミング、さらに再発を防ぐための方法まで幅広く解説します。
「痛みを我慢して働くべきか」「復職の判断基準がわからない」と悩んでいる方にとって、今後の生活の指針となる情報です。ご自身の症状と照らし合わせながら参考にしてください。
当院では、頚椎椎間板ヘルニアをはじめとした整形外科疾患に対し、丁寧な診察とわかりやすい説明を心がけています。不安な症状がある方も安心してご相談いただけるよう、以下の記事で診察の流れや受付方法を詳しくまとめています。
>>診察のご案内について

記事監修:川口 慎治
大室整形外科 脊椎・関節クリニック 医師
経歴:
徳島大学医学部卒業後、洛和会音羽病院に勤務
京都大学医学部整形外科学教室入局
学研都市病院脊椎脊髄センター勤務
2023年より 大室整形外科 脊椎・関節クリニック勤務
専門分野:脊椎・脊髄外科
資格:
日本専門医機構認定 整形外科専門医
日本整形外科学会認定 脊椎脊髄病医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科指導医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科専門医
頚椎椎間板ヘルニアで仕事を休む目安
頚椎椎間板ヘルニアで仕事を休む目安について、症状別に解説します。
- 痛みやしびれで仕事が難しい
- 筋力低下がある
- 馬尾症候群を伴っている
痛みやしびれで仕事が難しい
痛みやしびれの感じ方には個人差があります。軽度であれば我慢できても、強い症状があると仕事に大きな支障をきたすことがあります。痛みの程度を評価する指標として「痛みスケール」があります。0〜10の数値で痛みを表し、0が無痛、10が最大の痛みを示します。
痛みスケールは、休職の要否や勤務形態を検討する際の参考の一つになりますが、痛みやしびれ、仕事内容などを総合的に考慮して判断されます。以下は一例です。
- 痛みスケール7〜10(激痛):3〜7日間の安静と薬物療法を検討
- 痛みスケール4〜6(中等度):半日勤務や在宅勤務を検討
- 痛みスケール1〜3(軽度):業務に支障がなければ出勤可能
最終的な判断は、医師の診断や個々の状態に合わせて行われます。
以下の記事では、椎間板ヘルニアで歩行困難になるほどの激痛が出た際の応急処置や、緊急受診の目安について詳しく解説しています。
>>【椎間板ヘルニア】激痛で歩けないときの緊急対処法と受診目安
筋力低下がある
筋力低下や巧緻動作障害(細かい動きが困難)がみられる場合は、休職を検討する必要があります。頚椎椎間板ヘルニアによって神経の働きが妨げられると、筋力低下や巧緻動作障害が生じ、業務に大きな支障をきたす可能性があります。休む期間は、症状の程度や担当する業務内容によって異なるため、医師と相談のうえ、適切な休職期間を決めましょう。
手術を受けた場合、手術方法によっても休職期間は異なります。ACDF(前方頸椎椎間板切除術)や人工椎間板置換術を受けた場合、一般的な休職期間の目安は、以下のとおりです。
- デスクワーク:2~4週間
- 立ち仕事:4~6週間
- 重量物を扱う仕事:8~12週間
後方除圧固定術を受けた場合は、以下のとおりです。
- デスクワーク:3~6週間
- 立ち仕事:6~8週間
- 重量物を扱う仕事:12週間以上
低侵襲PECD(経皮的内視鏡下椎間板摘出術)は、従来の開腹手術と比較して入院期間が短く、社会復帰も早いと報告されています。低侵襲PECD(経皮的内視鏡下椎間板摘出術)の一般的な休職期間は、以下のとおりです。
- デスクワーク:1~2週間
- 立ち仕事:2~4週間
- 重量物を扱う仕事:6~8週間
休職中の経済的支援
休職中に利用できる代表的な経済的支援は、以下のとおりです。
- 傷病手当金
- 労災保険
- 高額療養費制度
傷病手当金
傷病手当金は、病気やけがで会社を休む場合に支給される給付金です。健康保険に加入している会社員や公務員が対象です。連続して3日間休み、4日目以降も就労できない状態が続いたときに支給されます。支給額は標準報酬日額の3分の2で、最長で1年6か月、受給可能です。
受給するためには、医師の診断書が必要です。診断書には、病名や症状、就労が困難な期間などが記載されます。会社を通して健康保険組合に申請することで、傷病手当金が支給されます。診断書の作成費用は自己負担となる場合があるため、事前に医療機関に確認しておきましょう。
労災保険
労災保険は、業務中や通勤中のけがや病気による経済的負担を軽減するための国の制度です。該当する場合、治療費の自己負担はなく、休業補償給付として給与の約8割が支給されます。労災保険が適用されるためには、業務や通勤との因果関係が認められる必要があります。
医師の診断書や事故発生状況の報告書などが必要になるため、早めに会社へ報告し、適切な手続きを進めましょう。
高額療養費制度
高額療養費制度は、1か月(月の初めから終わりまで)の医療費が一定額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。自己負担限度額は年齢や所得により異なります。申請は、加入している健康保険組合または国民健康保険の窓口で行います。必要書類(領収書や保険証、印鑑、振込口座など)を事前に確認しておくと手続きがスムーズです。
あらかじめ「限度額適用認定証」を取得しておくと、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までにできます。現在は、マイナンバーカードを保険証として登録し、オンライン資格確認に対応した医療機関で受診すれば、限度額適用認定証の提示は不要です。
対応していない医療機関や登録が済んでいない場合は、従来通り限度額適用認定証の提出が必要です。医療費の負担が心配な方は、ご自身の状況に合わせて事前に手続きを確認しておくと安心です。
職場復帰の3つのタイミング
職場復帰のタイミングについて、以下の3つを解説します。
- 医師が復職できると判断したとき
- リハビリテーションで可動域が復活したとき
- 痛み止めがなくても日常生活を送れるとき
医師が復職できると判断したとき
医師が復職可能と判断する基準は、神経学的検査の結果と患者さんの自覚症状です。神経学的検査では、握力測定や上肢の挙上テストなどを行い、神経の回復度合いを確認します。痛みやしびれの程度に加え、食事や更衣、排泄、入浴といった日常生活動作に支障がないかどうかも判断材料です。
検査結果と生活状況の両面から総合的に評価し、安全かつ無理のない職場復帰の時期が決定されます。自己判断は避け、医師の指示に従って復帰を目指しましょう。
リハビリテーションで可動域が復活したとき
リハビリテーションは、手術後の職場復帰を目指すうえで重要です。手術によって一時的に低下した頸部の可動域を回復させるだけでなく、筋力強化や柔軟性の向上にもつながります。理学療法士の指導のもと、首のストレッチや筋力トレーニングなどを行います。
可動域が80%以上回復すると、日常生活動作に支障が少なくなり、デスクワークのような比較的負担の軽い仕事であれば、復帰できる可能性が高まります。立ち仕事や重量物を扱う職種では、より高い回復度が求められるため、復帰時期は慎重に検討する必要があります。
痛み止めがなくても日常生活を送れるとき
痛み止めが不要になることは、職場復帰の大きな目安です。痛み止めを服用せずに日常生活を送れる状態であれば、痛みによる集中力の低下や作業効率の悪化も起こりにくくなります。痛みが残っている段階での復職は、業務中のパフォーマンス低下や体調の悪化につながるおそれがあるため、慎重な判断が求められます。
痛み止めが不要な状態で、日常生活に支障がなければ、本格的な職場復帰の検討段階と言えます。
以下の記事では、頚椎椎間板ヘルニアにおける痛みを和らげるための具体的な対処法や、日常生活で注意すべきポイントについて詳しく紹介しています。首まわりの症状に悩んでいる方はぜひご覧ください。
>>頚椎椎間板ヘルニアの痛みを和らげる方法!効果が期待できる対処法と注意点
頚椎椎間板ヘルニアの再発を防ぐ方法
頚椎椎間板ヘルニアの再発を防ぐ方法は、以下のとおりです。
- 頚椎の過度な運動を避ける
- 長時間の同じ姿勢を避ける
- 正しい姿勢を意識する
- 禁煙する
頚椎の過度な運動を避ける
頚椎の過度な運動は首に負担をかけるのでできるだけ避けましょう。特に術後は組織の修復途中であり、以前のような強度はありません。負荷がかかると、再発のリスクが高まります。日常生活では、特に上を向く動作や下を向く動作を避けましょう。
長時間の同じ姿勢を避ける
デスクワークや車の運転など、同じ姿勢を続けると筋肉が緊張し、血行が悪くなります。椎間板への栄養供給が妨げられ、再発のリスクが高まります。デスクワークでは、45分ごとに短い休憩を取り、ストレッチや軽い体操を行いましょう。パソコン作業をする場合は、モニターの高さは目線に合わせ、肘は90度を意識してください。
運転や長時間移動が多い場合は、頸部ブレースを着用し、2時間ごとにストレッチを行うことをおすすめします。
正しい姿勢を意識する
正しい姿勢を意識することで、再発リスクの軽減につながります。猫背やストレートネックは、首への負担を増やす原因です。立っているときは、耳や肩、腰、くるぶしが一直線になる姿勢を保ちましょう。座っているときは背筋を伸ばし、あごを引くように意識します。
就寝時は、高さ6〜8cmの低反発まくらを使い、仰向けで寝るようにしましょう。姿勢記録アプリを活用して、日頃から自分の姿勢をチェックすることもおすすめします。
禁煙する
喫煙は、椎間板の変性を促進し、頚椎椎間板ヘルニアの再発リスクを高める場合があります。ニコチンは血管を収縮させ、椎間板への血流を阻害する作用があるため、椎間板の修復が遅れ、再発のリスクが高まります。禁煙により血流が改善され、椎間板への栄養供給も促進されます。
禁煙外来を利用することで、専門的なサポートを受けながら継続しやすくなります。
近年では、20代などの若い世代でも腰椎ヘルニアを発症するケースが増えています。デスクワークやスマートフォンの長時間使用、過度なスポーツなどがリスク要因になるため、早めの対策が重要です。以下の記事では、若い人の椎間板ヘルニアの原因や20代でもなる理由、効果が期待できる予防法を詳しく解説しています。
>>若い人の椎間板ヘルニアの原因とは?20代でもなる理由と予防法
まとめ
頚椎椎間板ヘルニアは、痛みやしびれにより仕事の継続が難しくなることがあります。症状に応じた休職の判断や、傷病手当金などの支援制度の活用、適切な復職のタイミングを知ることが大切です。再発を防ぐには、日常の姿勢や生活習慣の見直しも欠かせません。
この記事の内容が、症状に応じた判断や、安心して復職するための行動を後押しする一助となれば幸いです。
当院の受診をご希望の方は、まずはお電話にてご予約ください。詳しいアクセス方法は、以下のページをご覧ください。
>>大室整形外科へのアクセスはこちら
参考文献
Jeff D Golan, Lior M Elkaim, Qais Alrashidi, Miltiadis Georgiopoulos, Oliver Lasry. Economic comparisons of endoscopic spine surgery: a systematic review. Eur Spine J, 2023, 32, 8, p.2627-2636